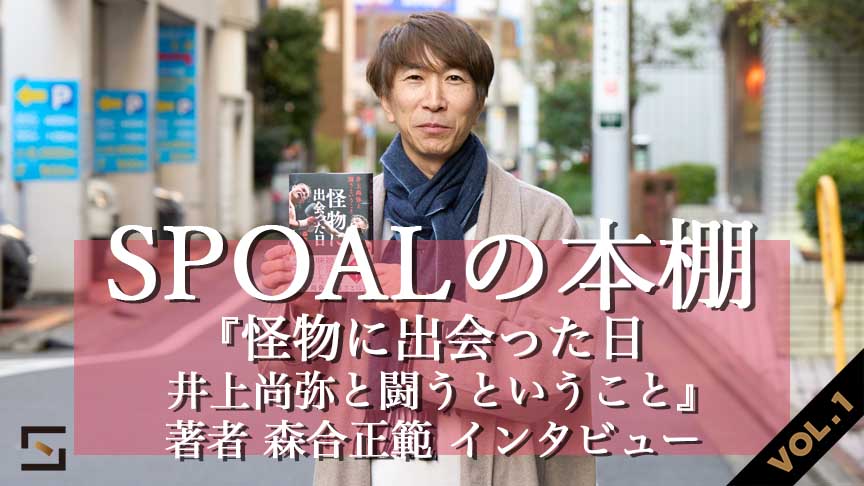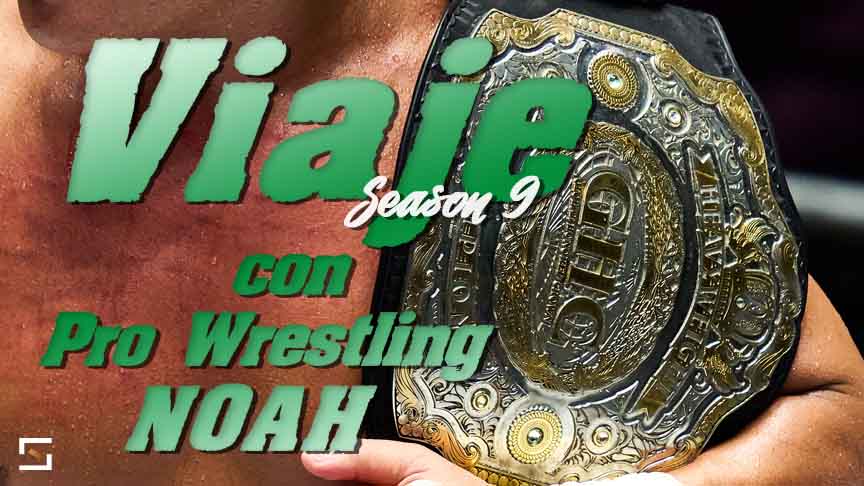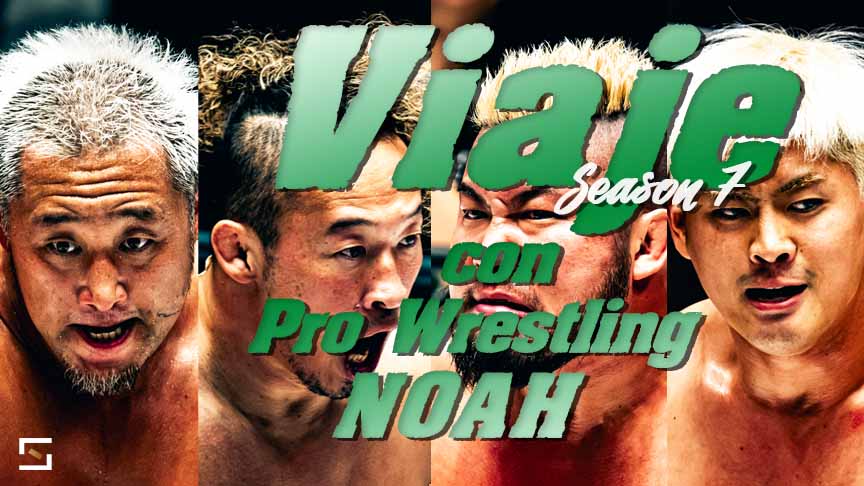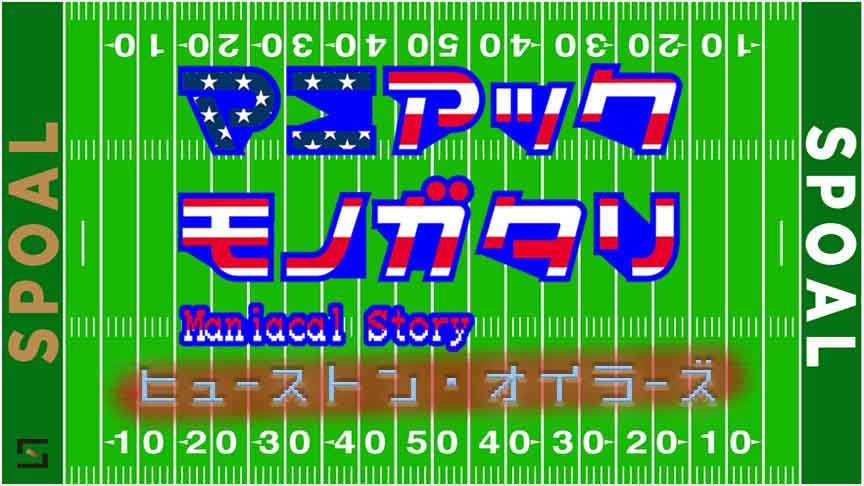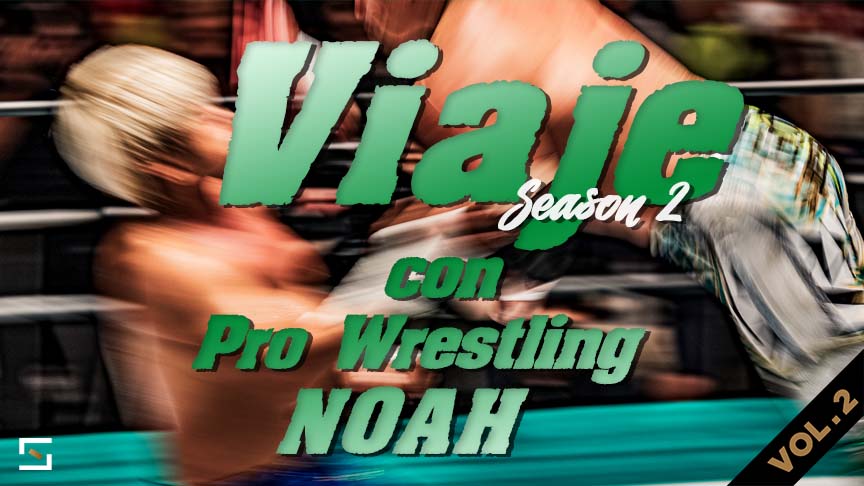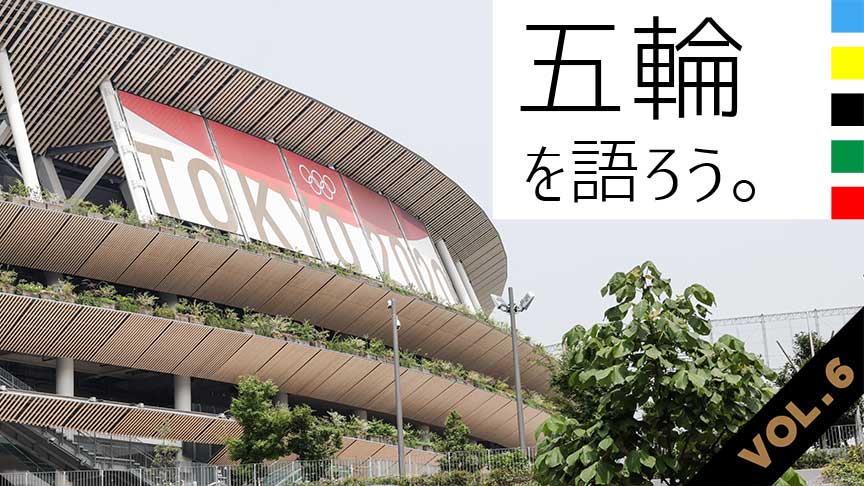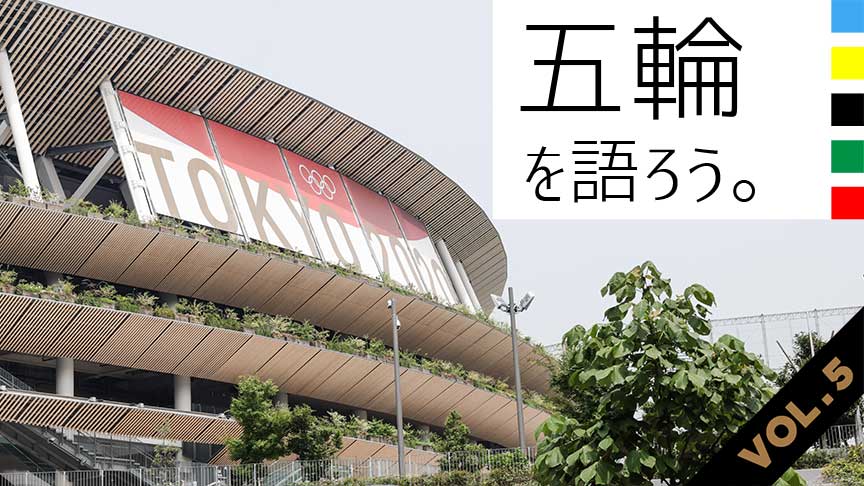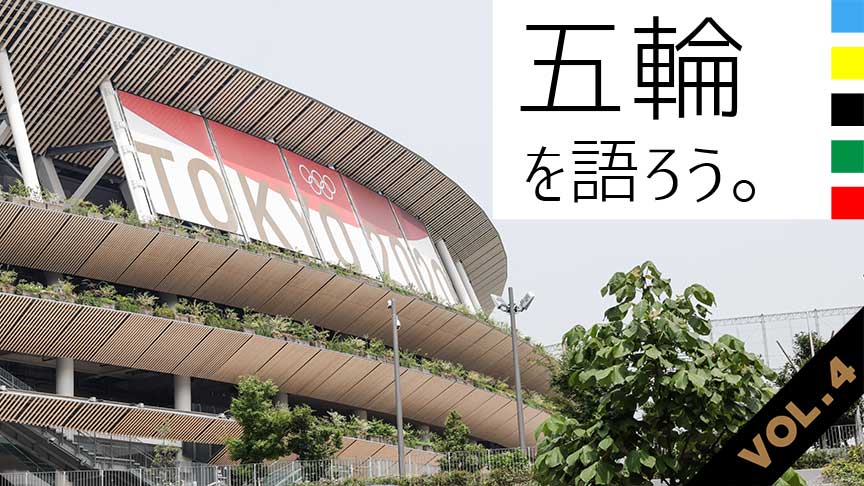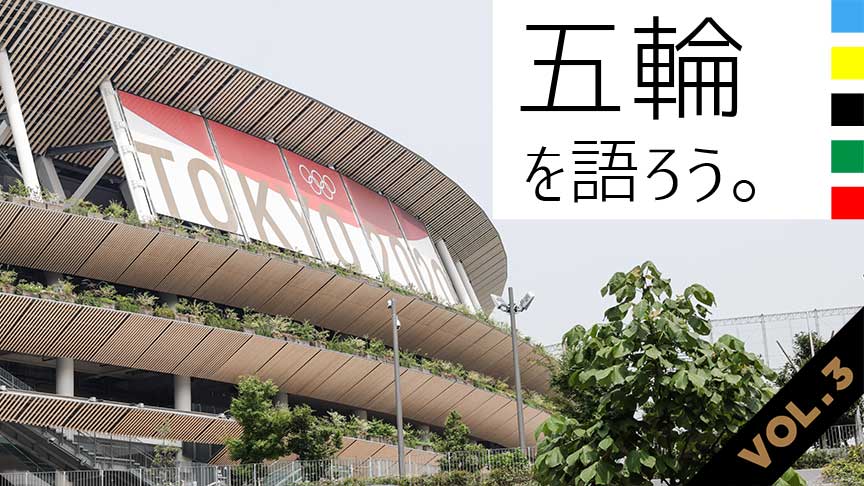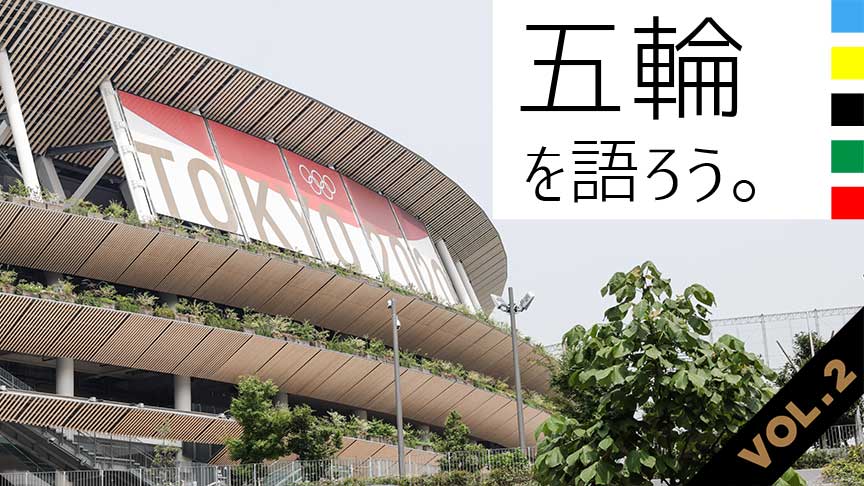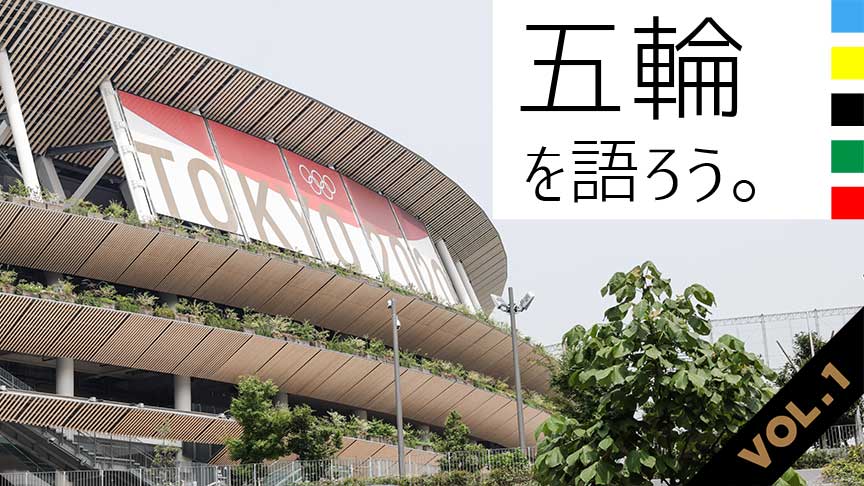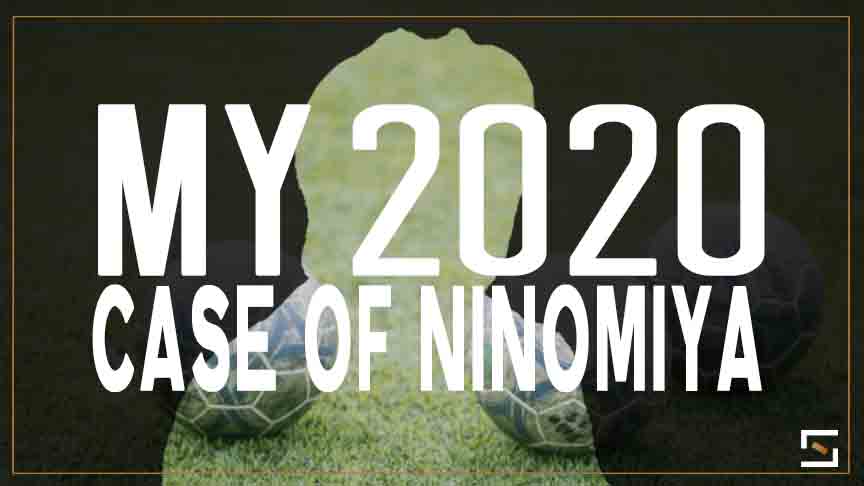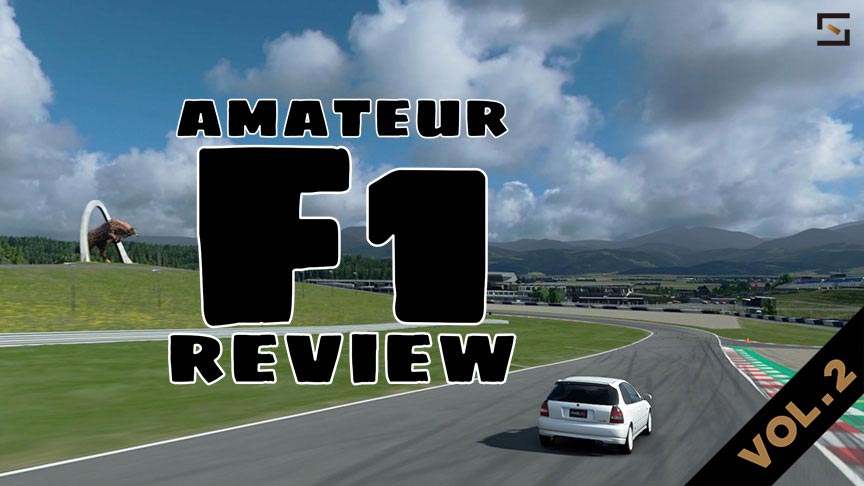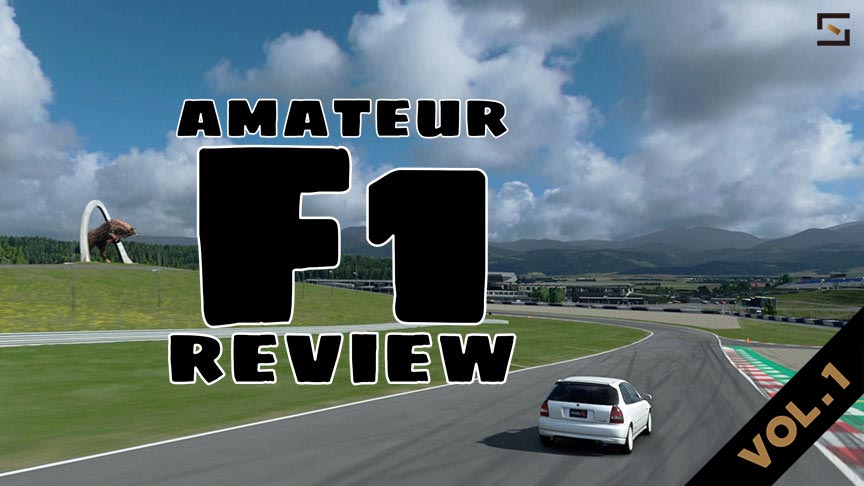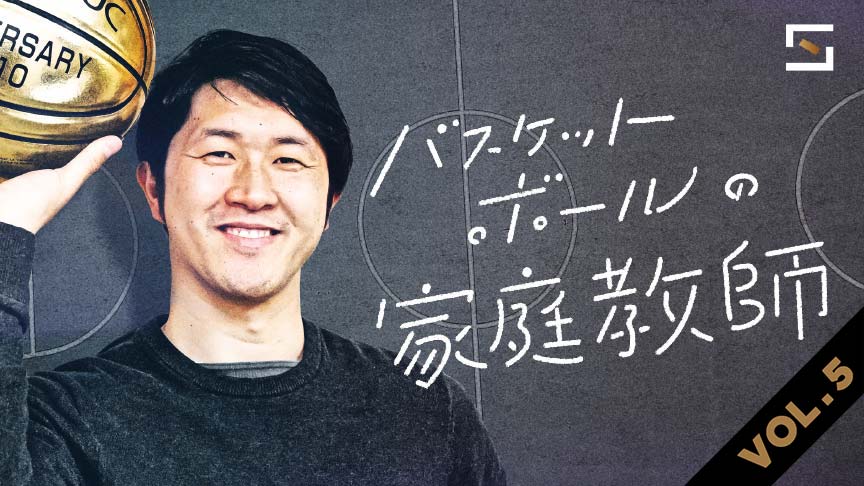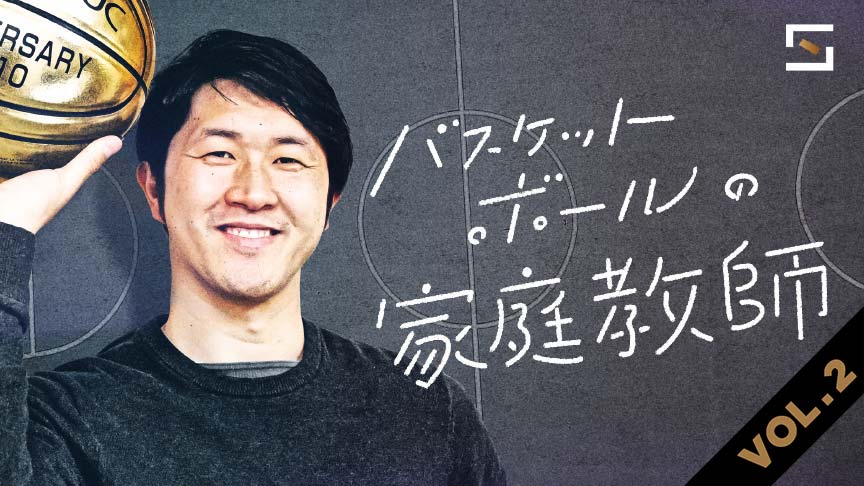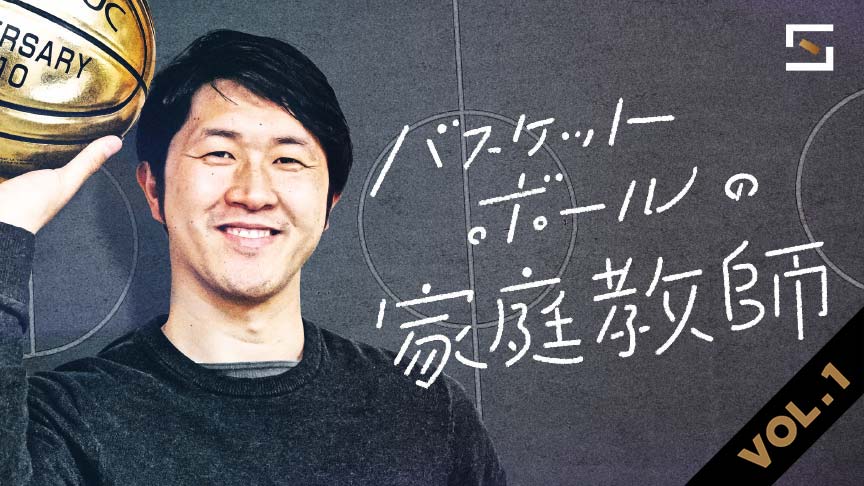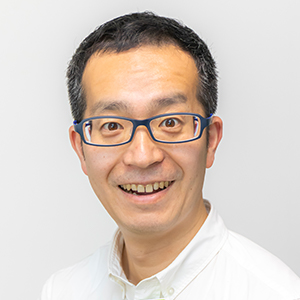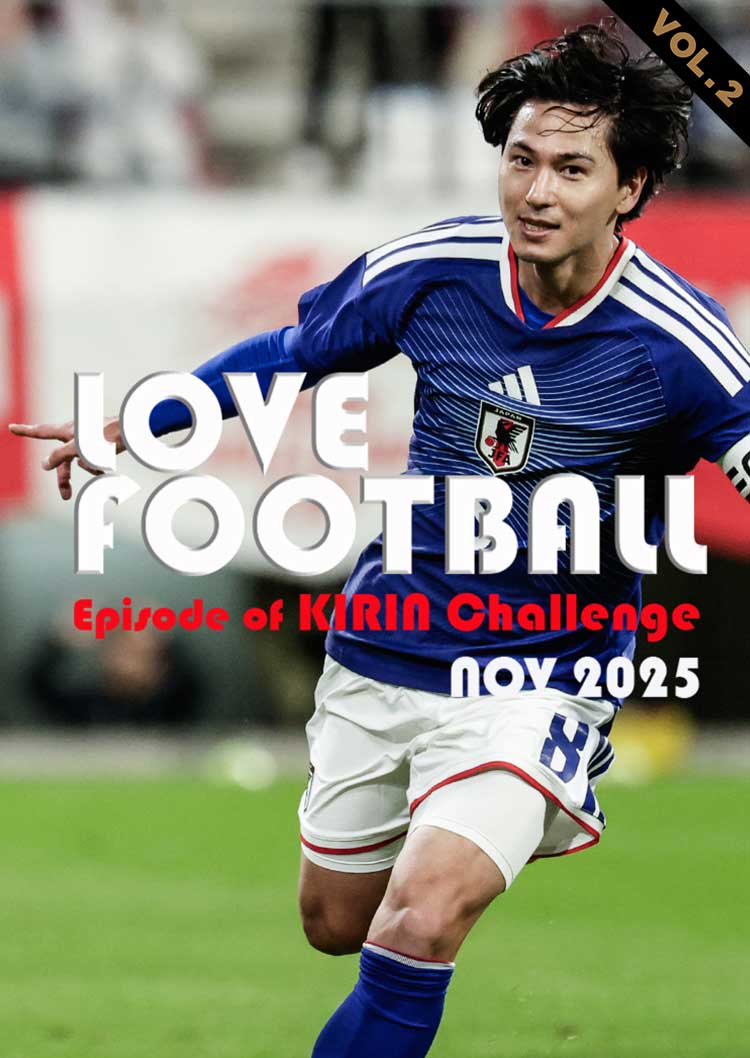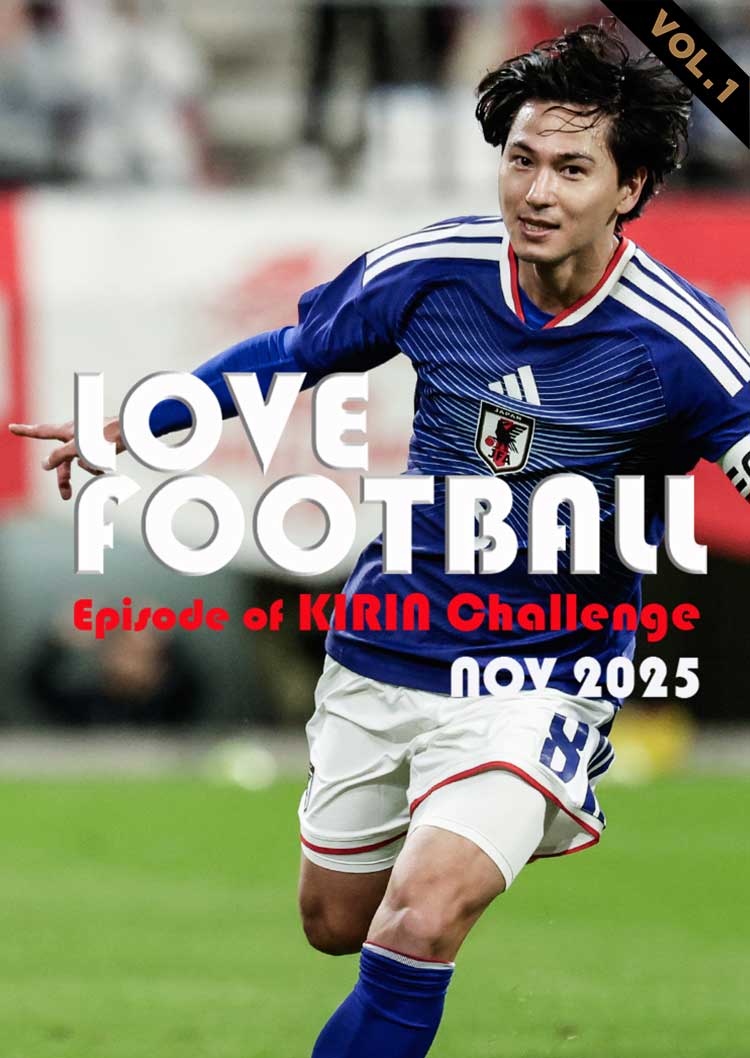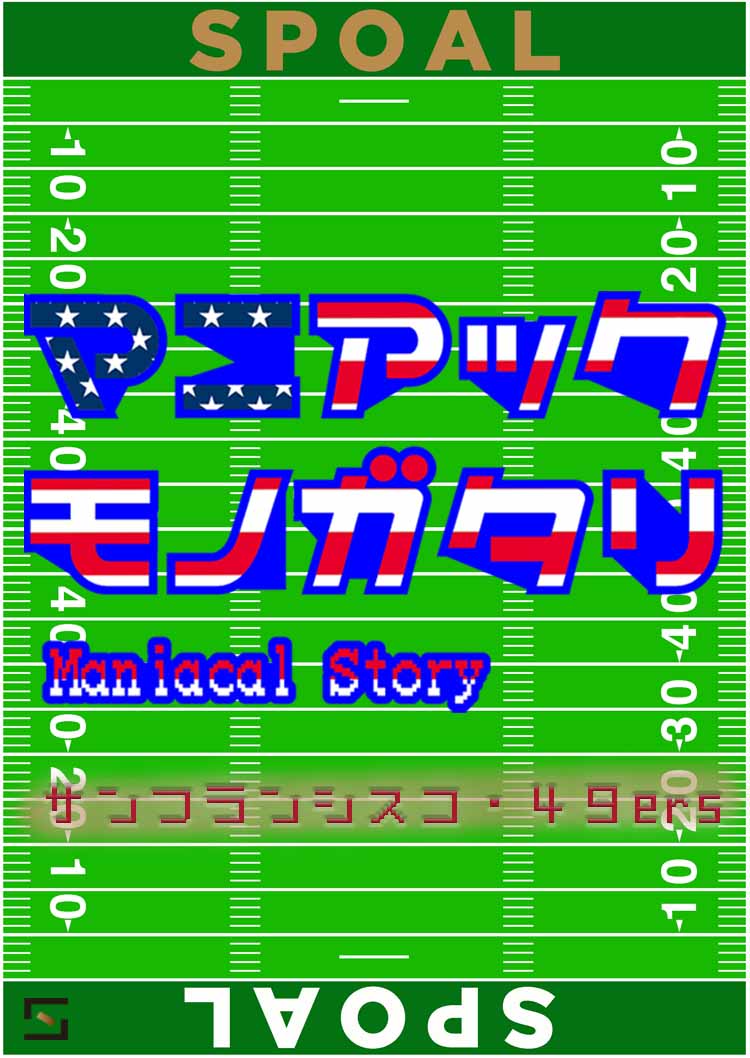いまだ読み継がれるロングセラー 植村直己著『青春を山に賭けて』
植村直己さんをご存知だろうか。1970年にエベレストの頂に日本人として初めて立ち、世界で初めて五大陸の最高峰に登頂した登山家。はたまたアマゾン川をいかだで下り、犬ぞり単独行で極地を走り、世界で初めて北極点に到達した冒険家。1970年代から80年代にかけて、日本国民の心を揺さぶったスターの一人だったと言えるだろう。
その植村さんの著書『青春を山に賭けて』は私が若き日に手にして、とても感動した一冊である。とはいえ、この本が出たのはもう半世紀近く前の話。いまさら「若い人に読んでもらいたい」なんて紹介するのも何だか押しつけがましい。それに紹介したところでもう絶版になっているんじゃないか、と思いきや…。
なんと文春文庫の『青春を山に賭けて』は今でも売っているではないか! 私の手元にある文庫本は1992年6月印刷の第25版で定価は380円。最新版は2021年3月印刷の新装版第17版で、定価は726円となっている。時の流れを感じつつも「やっぱり名作っていつまでも読み継がれるんだよな~」と妙に感心してしまった。
さて、植村さんは生存中にいくつかの冒険シリーズを記しているのだが、この本はその第1作目であり、植村さんが自らを幼少時代から振り返る自伝的ノンフィクションだ。明治大学山岳部の門を叩き、卒業後は無一文でアメリカに渡って不法労働をしたり、スキー未経験なのにアルプスのスキー場で働いたり、はては世界初となる五大陸最高峰を登頂するという快挙まで、植村さんが自らの足跡をあますところなく記している。
植村さんの魅力の一つは、偉そうなところが微塵もなく、「どうだ見たか、やってやったぜ!」みたいなマインドをまったく感じさせないところだ。そのくせやっていることと言えば、移民局の役人に追い回されたり、死と隣り合わせの極寒の冬山を登ったり、猛獣のいるジャングルを歩いたり、というのだから驚かされる。文章もまさにそうで、飾らない朴訥とした文章がハラハラ、ドキドキのエピソードを一層際立たせている。
臆病で心配性でありながら、どこまでも自由にして大胆。私たちは植村さんが夢を追いかける姿を追体験しながら、「ああ、自分もこんな人生を歩んでみたいな」と思わずにはいられない。人間やればできるんだ。この本にはそんなシンプルな考えを本気で信じさせる力がある。それがロングセラーとなりえた理由だと思う。
植村さんは1984年2月、厳冬の北米マッキンリーに世界で初めて単独登頂した後、下山中に消息を絶ち、その生涯に幕を閉じた。植村さんは当時43歳。私は中学に上がる前で、植村さんの捜索活動のニュースがテレビで流れていたことを覚えている。

その捜索活動に加わった人物に偶然にも会うことができたのは、私が30歳をすぎてからだった。植村さんと明治大学山岳部で同期だった中出水勲さんは日刊スポーツの記者だった。出会った当時はすでに運動部長などを経験してから現場に戻ってきたベテラン記者で、私の取材先であるボクシング会場でよくお見かけした。
植村さんの著作に親しみ、何かの提出種類で「尊敬する人物」と書く欄があれば植村直己と書いていた私にしてみると、中出水さんは憧れの人の隣人である。いつか植村さんの話を聞いてみたいと思いながら、亡くなった同級生の話を急に持ち出す勇気もなく、その機会はなかなか訪れなかった。
ある冬の夜、後楽園ホールでボクシングの試合が終わり、飯田橋の駅に向かう道すがら偶然2人きりになる機会を得た。思い切って植村さんのことを切り出した。「僕、昔から植村直己さんが大好きなんです」と。
「そうかあ、そんなこと言ってくれるのか。うれしいなあ」。中出水さんは自分が褒められたかのように照れながら、駅まで私と肩を並べながらこんなことを話してくれた。
1984年の冬、植村さん消息不明の報を受け、いくつかの新聞社、テレビ局がアラスカへ取材に入った。中出水さんも日刊スポーツの特派員として現地に飛んだ。同業他社と協力してセスナをチャーターし、上空から植村さんの行方を捜した。
1日の取材を終えると「今日も植村は見つからなかった」という原稿を書く。取材の拠点となった町にファクスはないため、書いた原稿を電話口で読む。それを東京のデスクが書き留めるのだが、中出水さんは毎回、植村さんのことを思い出して涙があふれ、途中で原稿が読めなくなった。近くにいる他社の記者が代わって原稿を読んでくれた。そんな話をまるで昨日のことのように語ってくれた。
「いいやつばかり先に死んで、オレみたいなろくでもないのが生き残るんだよ」。そう話していた中出水さんも2020年に鬼籍に入った。2人のご冥福を祈りながら、あらためて植村さんの著書を読み返してみた。
2022年1月公開