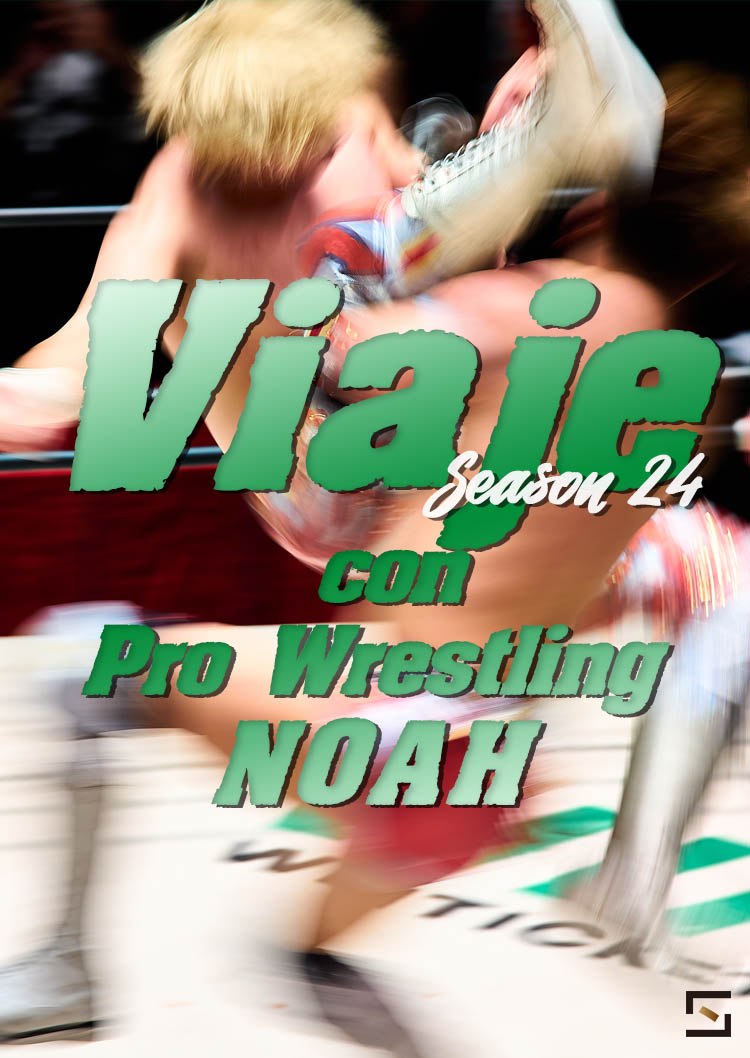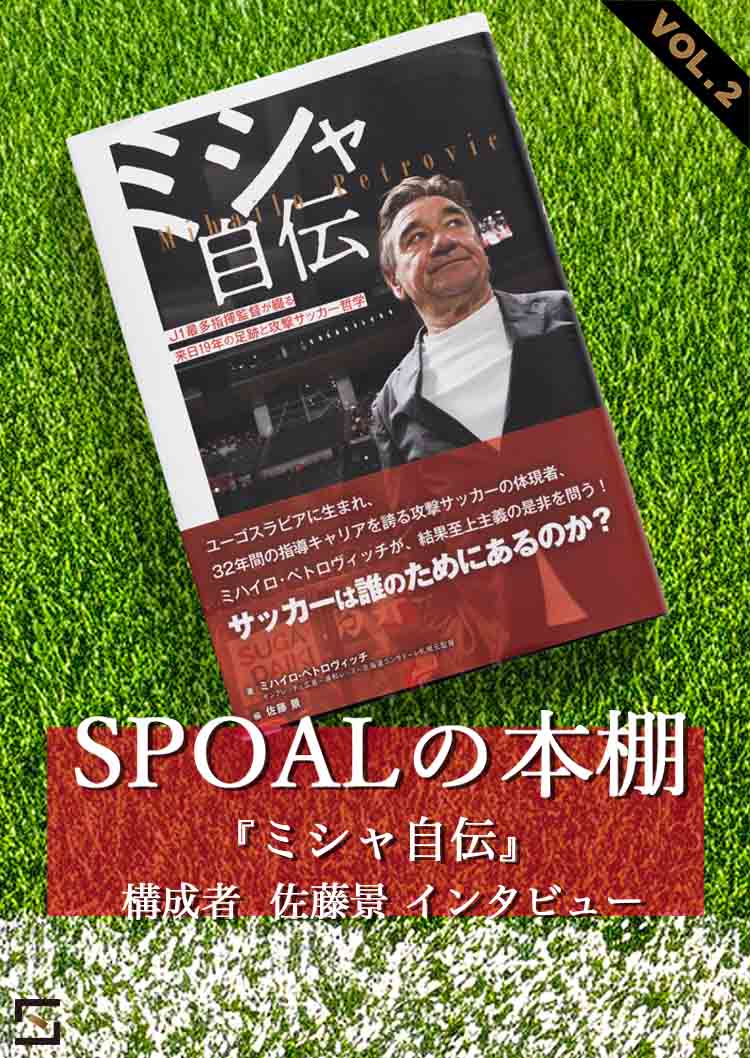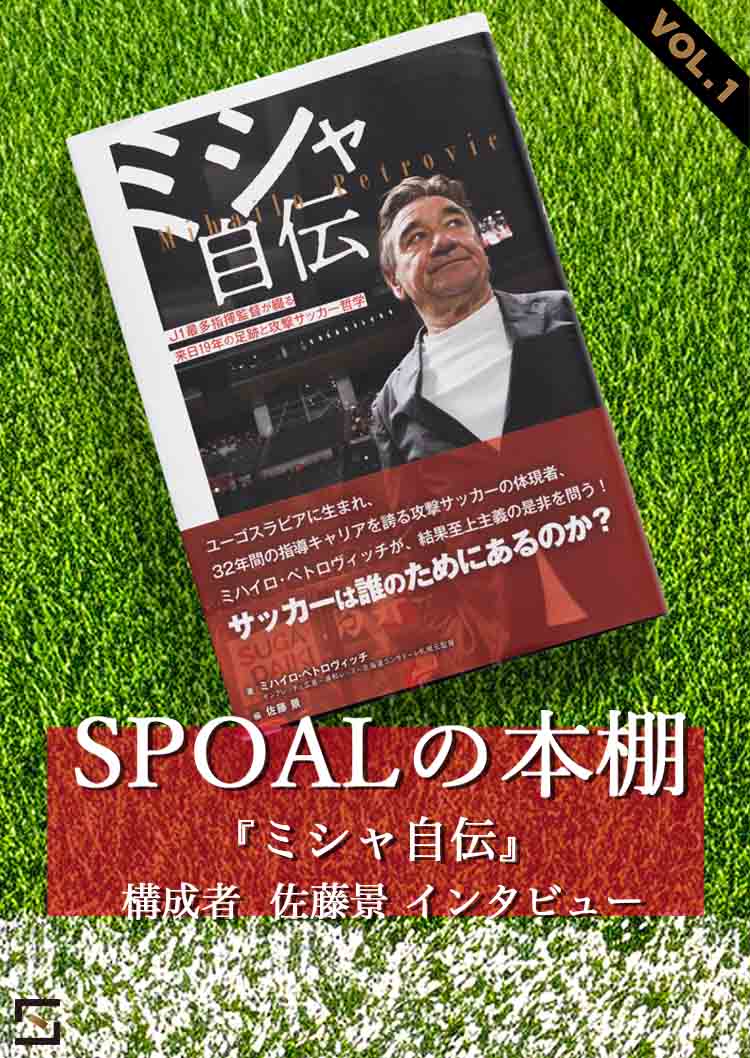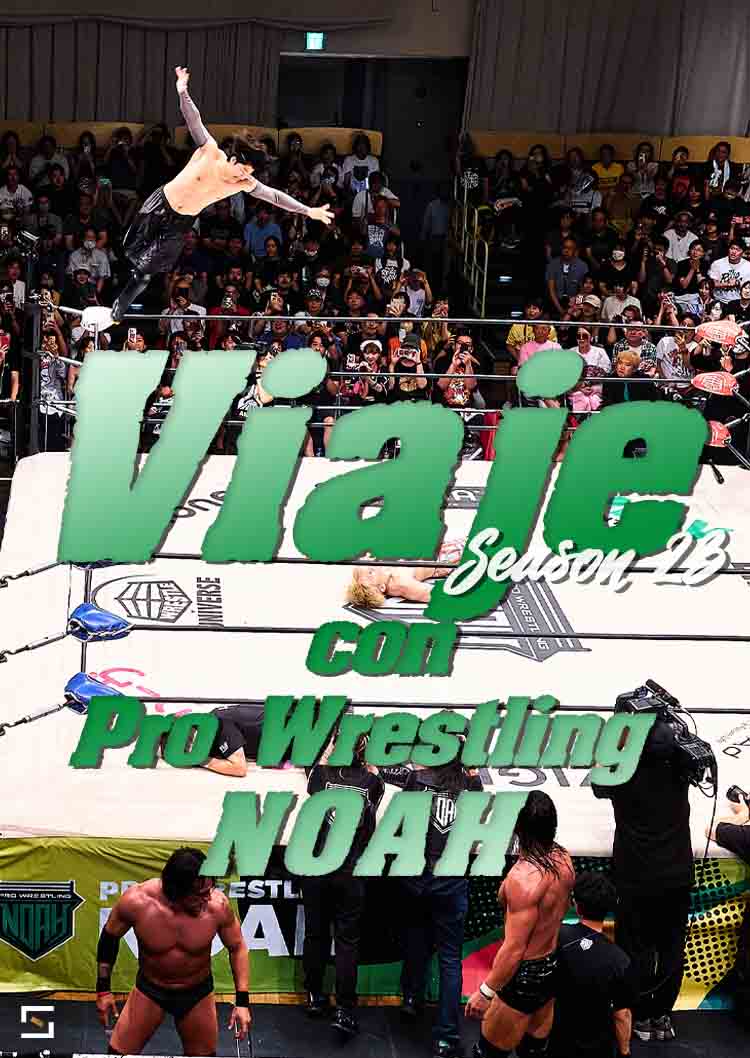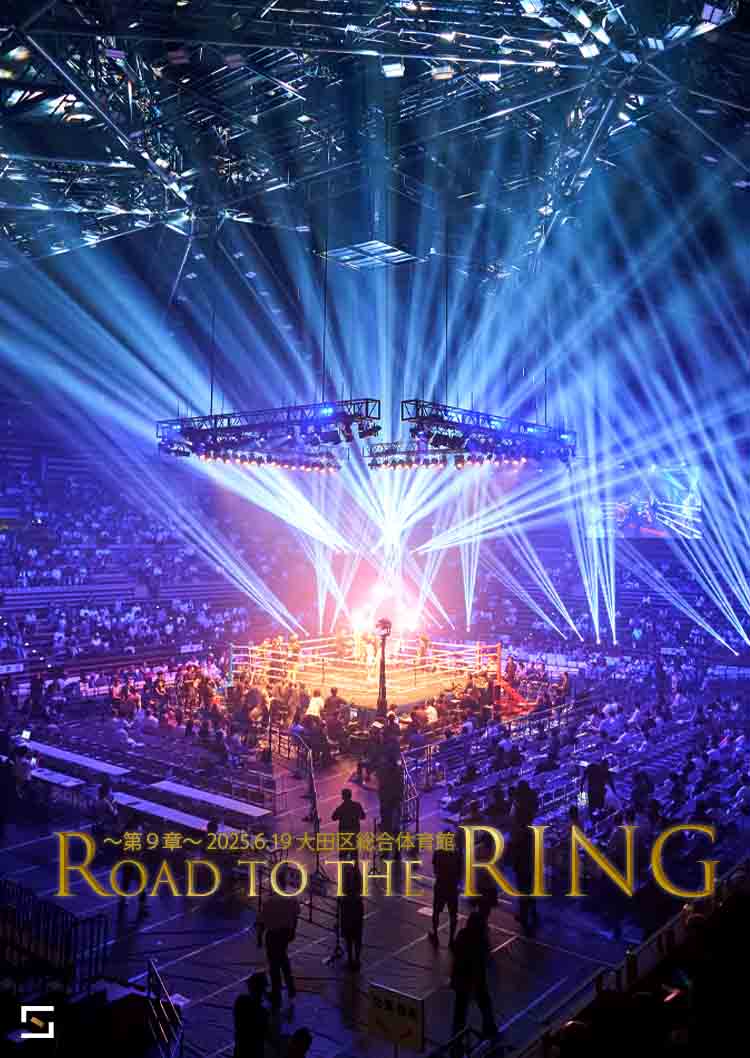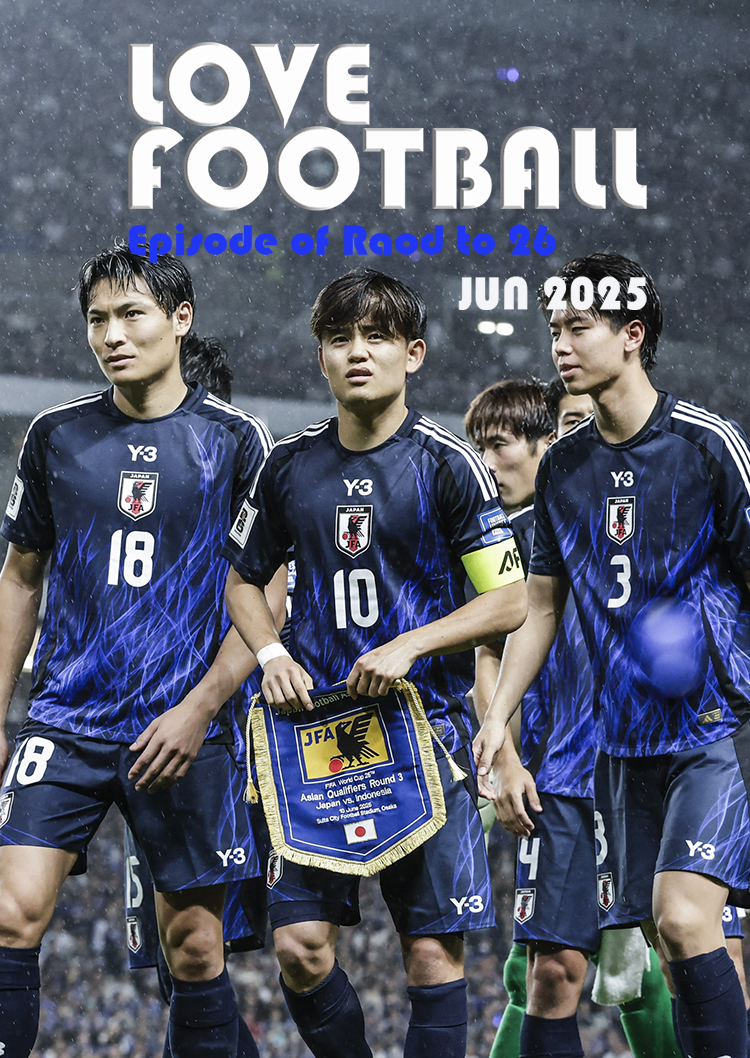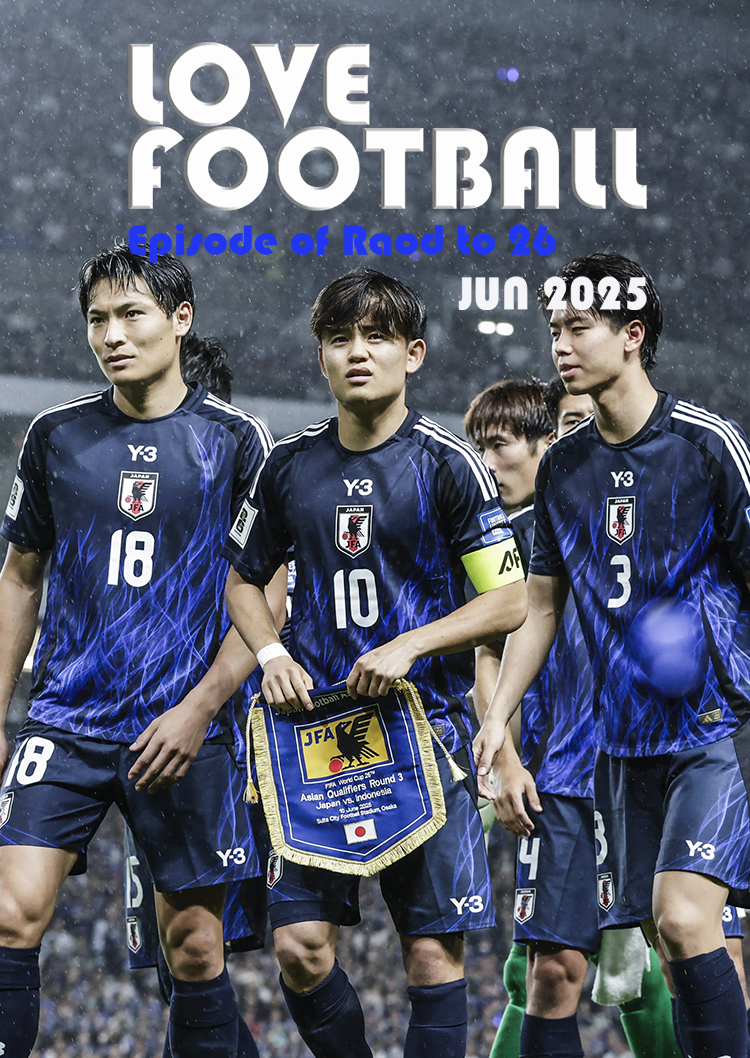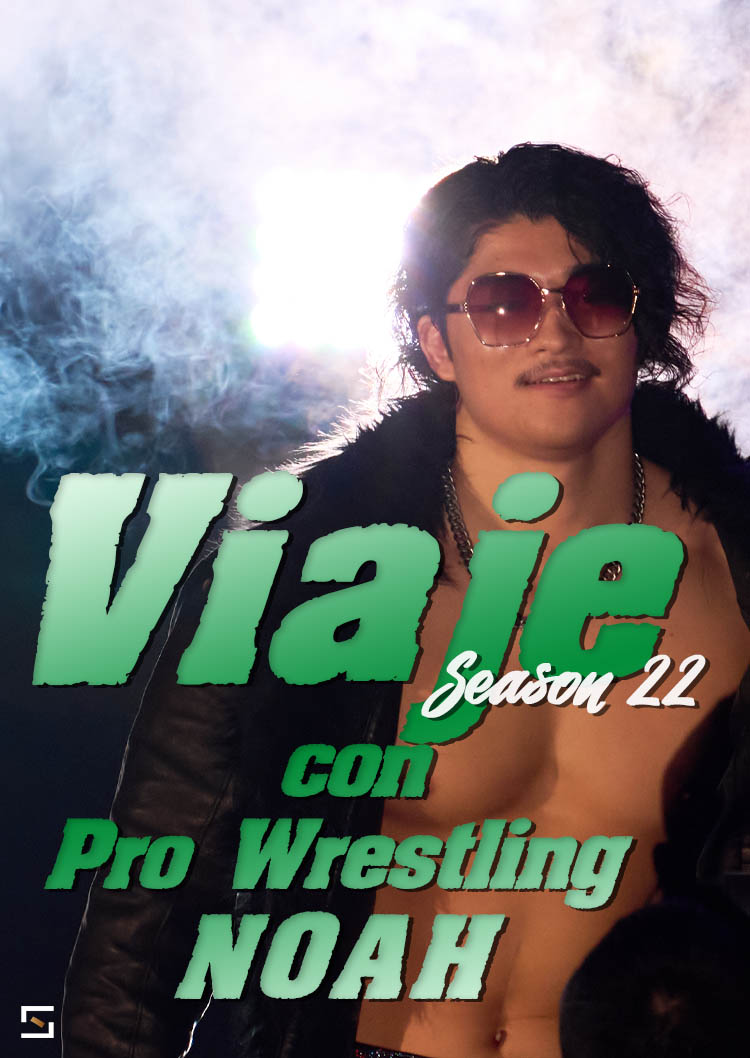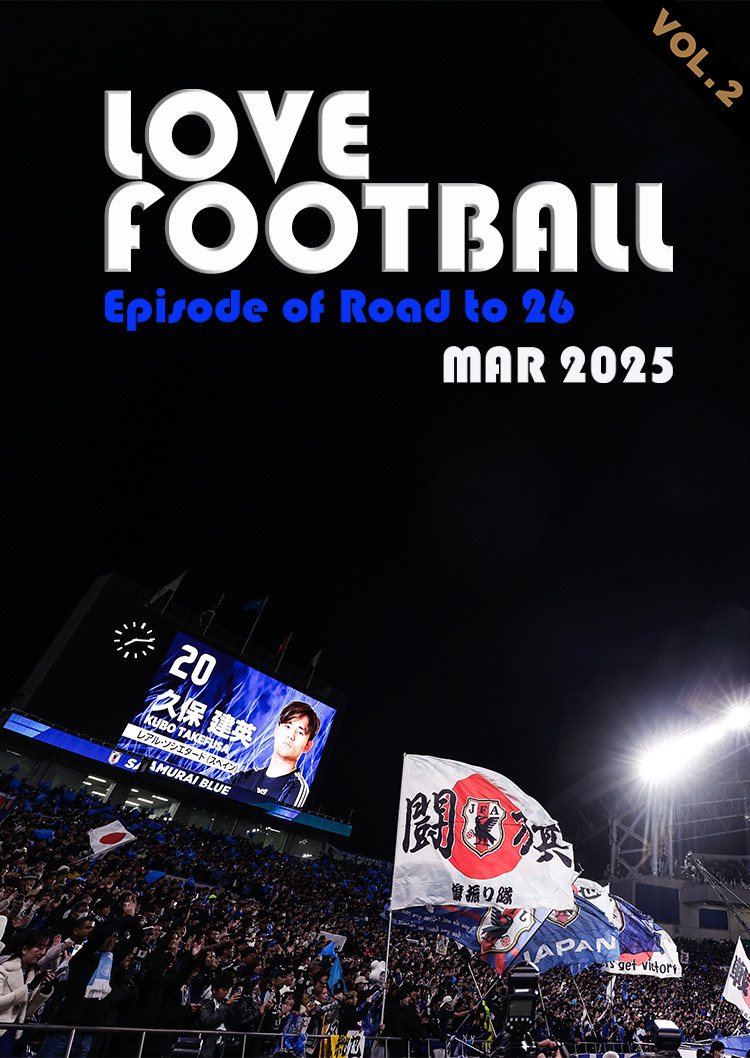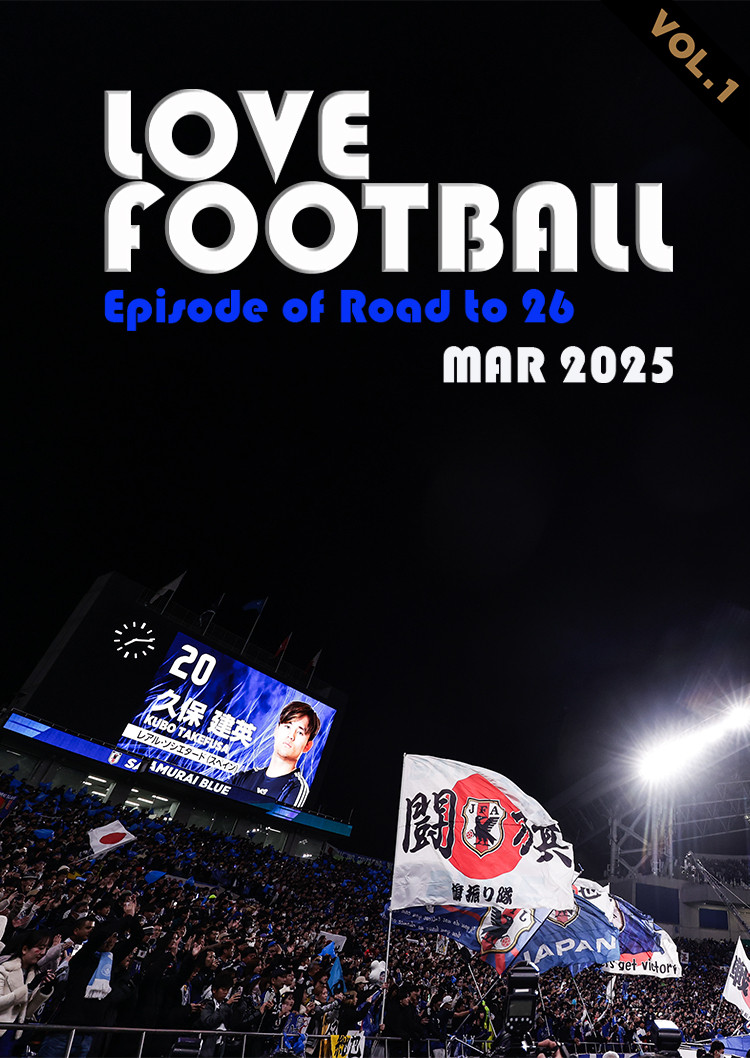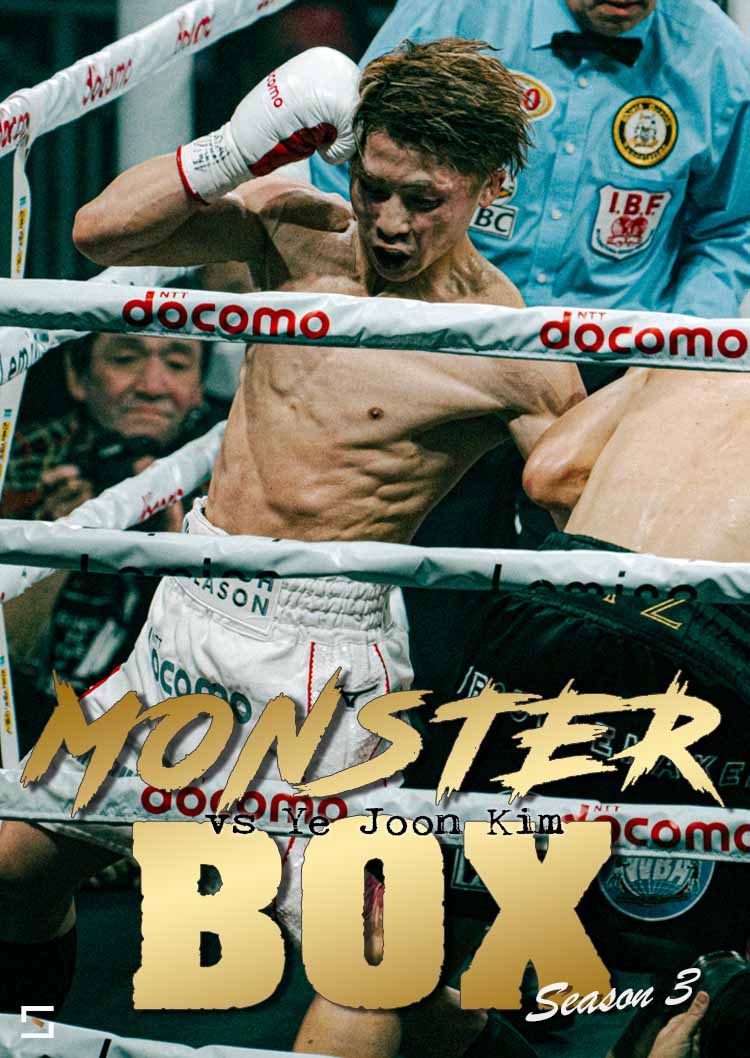栗原徹には、ちょっとした特技がある。
人の顔と名前がすぐ一致できること、その人の基本情報がパッと出てくること。そして何よりもその情報をもとに「間違ってもいいから」積極的にコミュニケーションを図ろうとすること。
2019年シーズン、母校・慶応大学ラグビー部(名称は慶應義塾體育會蹴球部)のヘッドコーチに就任した彼は、新チームの始動と併行して100人以上にも及ぶ部員と全員の面談を行なうことにした。
先にアンケート用紙を渡していた。項目は「あなたにとって蹴球部とはどんな存在か」「ここで達成したいことは何か」「どんな存在でありたいか」など。
「まずはどんなことを思っているのか、胸のうちを知りたいと考えたんです。アンケートに基づいて、学生にいっぱいしゃべってもらう。学生の情報や思いを、インプットしておくことが大切でした」
これは同級生の和田康二GMからも勧められていた。彼も監督時代に全員面談をやっていて「自分ではなかなか見えない部の情報や問題が把握できるから」とその効果を伝えられていた。

名前と顔を一度覚えたら、忘れない。
基本的に「キミ」「お前」とかは本人のなかではNG。名前で呼ぶことで、信頼関係は始まっていくと信じる。
「〇〇はお兄ちゃんいたよな」→「いや、姉ですよ」→「そうだ、そうだお姉ちゃんだったよな」
間違えることを厭わない。そこから始まるコミュニケーションがある。これには高校時代の嬉しい経験がある。和田の兄は、早稲田の選手だった。その和田兄が高校に指導に来てくれて「クリ、いいプレーだぞ」と名前で呼ばれたことがうれしかった。「あと一歩で早稲田に行きかけた」ほど、心に残る思い出になったそうだ。
現役を引退して指導者になってから、大学、高校にスポットでキックのコーチを頼まれることがあった。そこでも「名前教えて!」と聞いて、名前を呼ぶようにしてきた。尊敬する清宮克幸から教わった「大切なのは愛」は元々、資質として持ち合わせていた。名前を呼ぶことは、愛ある指導の一丁目一番地であった。
「清宮さんは言っていました。チーム、選手、自分とあるなかで、自分自身を好きだというコーチはあまりよくない、と。気持ちを向けなきゃいけないのは、選手一人ひとりだ、と。それがいいコーチだ、と」
面談で終わらせるのではなく、あくまでそれはコミュニケーションのきっかけづくりに過ぎない。和田は「100人を超える部員が、全員の部員と会話をすることというのは難しい」と話す。それを先頭に立ってヘッドコーチがやることによって、それもクリアになるかもしれない。ここは強い組織をつくるための栗原改革の狙いでもあった。
しかし一方で厳しい視線も忘れない。面談で語ったことと日頃の取り組みに整合性が取れているのかどうかも見ておかなければならない。
「僕の経験上、凄く厳しいことを言われて成長できた部分もあります。自分のためになったというのもあった。ときにはそういう言葉は必要だし、ちょっと弱っていたら、支えになるような声掛けをしてあげたい。自分もそうやって上田さんや清宮さんたちに声を掛けて助けてもらったので、自分もそうやってあげたいなって思うんです」
〝魂のタックル〟で知られる慶応の伝統は、質も量もハードなトレーニングだ。20年前、日々の厳しいトレーニングのなかで、上田監督がまさに「おい、クリ頑張れ」と名前を呼んでハッパを掛けてくれた。グラウンドには鬼も仏もいる。それが強い慶応をつくっていったのは間違いなかった。
新チームの立ち上げと同時に、彼はスローガン「UNITY」を提示した。直訳すれば、結束、一つになること。いやそれ以上でも、それ以下でもない。真の結束を成したときに、結果が伴うはずだと彼は信じた。

最初の力試しとなったのが春季大会だ。
慶応は初戦の流通経済大学戦(5月12日)において12-38で敗れると、計5試合行なって勝利は大東文化大戦のみに終わる。栗原はゴールデンウイークに「アクティブ・ラーニング」(能動的な学習)を取り入れ、受動的ではなく、母校へ帰って後輩を指導するなど部員が自由に使える時間とした。
これは大学選手権9連覇を果たした帝京大学が取れ入れていたことで参考にしたのだが、そもそも寮の都合などもあって3月末に全体始動となる慶応より1カ月半ほど始動は早い帝京だから効果が大きいという面もあった。
それは承知のうえ。「能動的」にこそ学生に対する栗原のメッセージがあったのだが、春季大会の内容と結果を見ても効果があったとは言い難かった。
栗原は言う。
「ラグビーには『チームの決めごと』と『選手の自由な判断』と大きく2つに分かれると思っています。慶応は伝統として決めごとを細かくしていくのが多くて、僕としては逆に自由な判断のほうの割合を増やそうと考えたんです。
たとえばスペースを左から1、2、3と分けて、これまでは1、2、3どの順序で攻めるかを決めていたところを、逆に選手側に渡しました。ただ、1を選択したら攻め方はこうだと、そこはトコトン細かくやります。分かりやすく言えば、大きいところの選択権と小さいところの選択権を逆にしたわけです。野球のピッチャーに置き換えればもっと分かりやすいと思います。最初は絶対にストレートで、2球目はカーブ、3球目はフォークと先に決めるんじゃなく、マウンドに立つピッチャー自身が考えてやりなさい、と。そのためにはいいボールを持っていなきゃいけない、と。実際、個々のスキルを上げる練習はかなりやりました。ただ(春季大会で)やってみて、大きな選択を任されたことに選手はちょっと混乱したところもあったとは思います。最初からはちょっと荷重だったかもしれないな、と」
しかしながら前向きなチャレンジをしたうえでのこと。修正していけばいいだけだ。
「グラウンド上のことはすべてヘッドコーチに任せてある」と語る和田にとっても想定内の結果ではあった。そして選手たちにはこう伝えることも忘れなかった。
「結果が出ないと、今やっていることを疑いかねない。心配しなくていい。リーダーを信じてやってほしい」
ただ和田の心配は杞憂に終わる。
チームにネガティブな空気は生まれていなかった。今は「新しい慶応」を生み出す苦しみにあるのだと、学生たちも理解していた。
2020年3月掲載