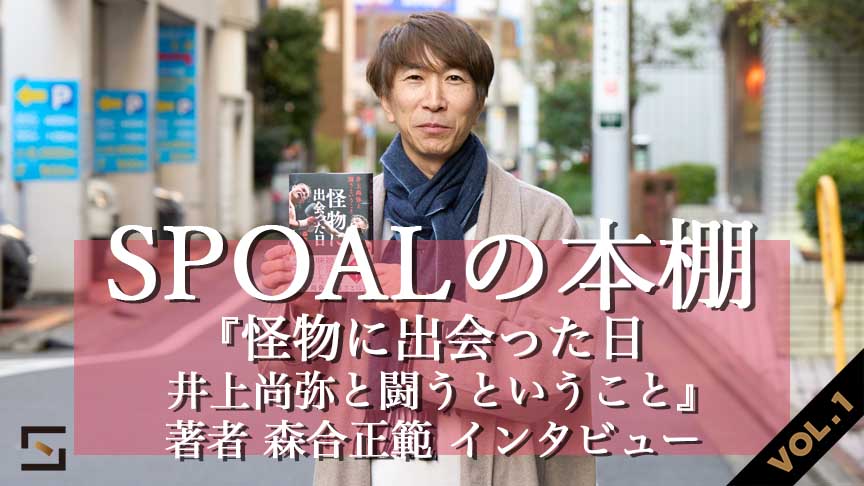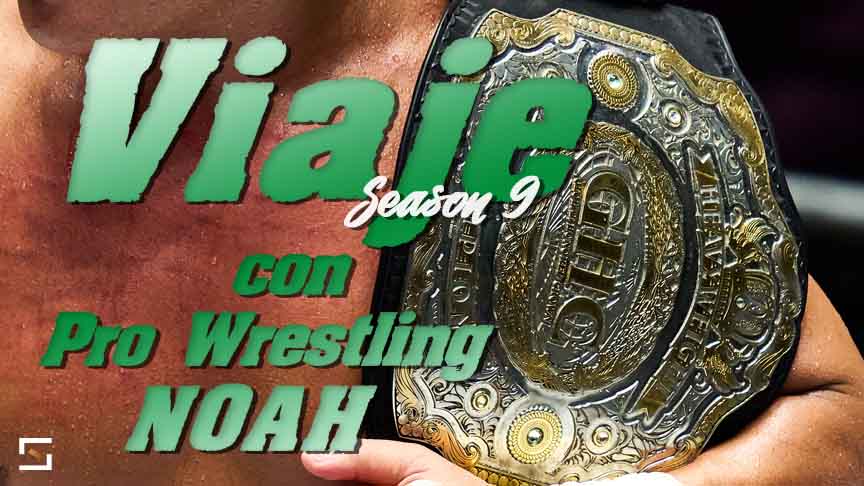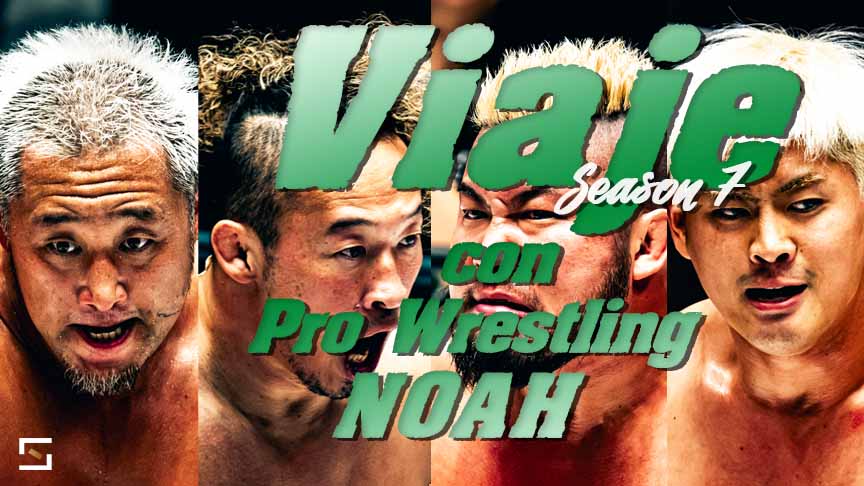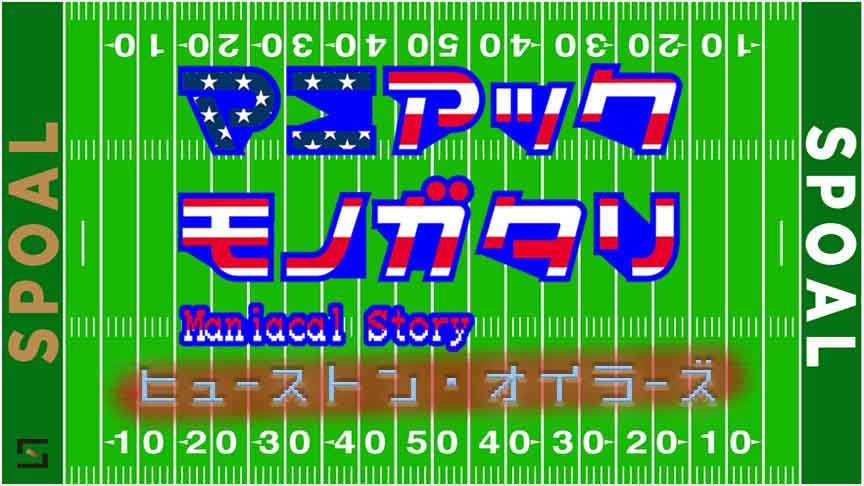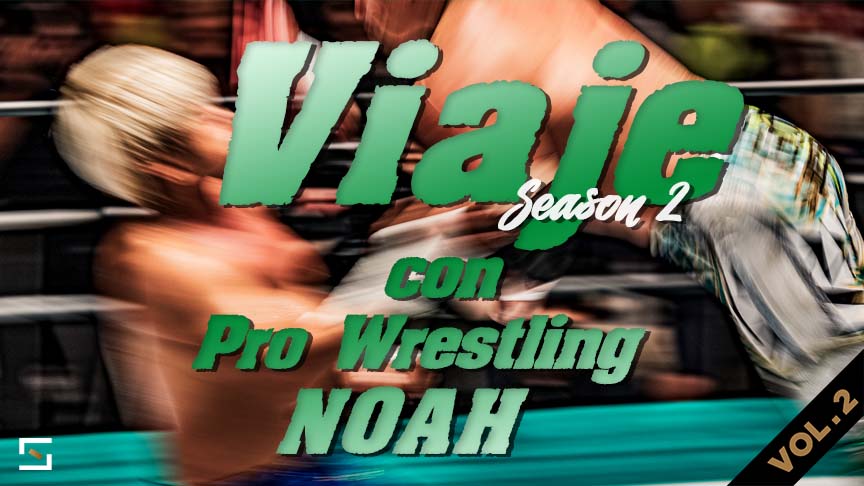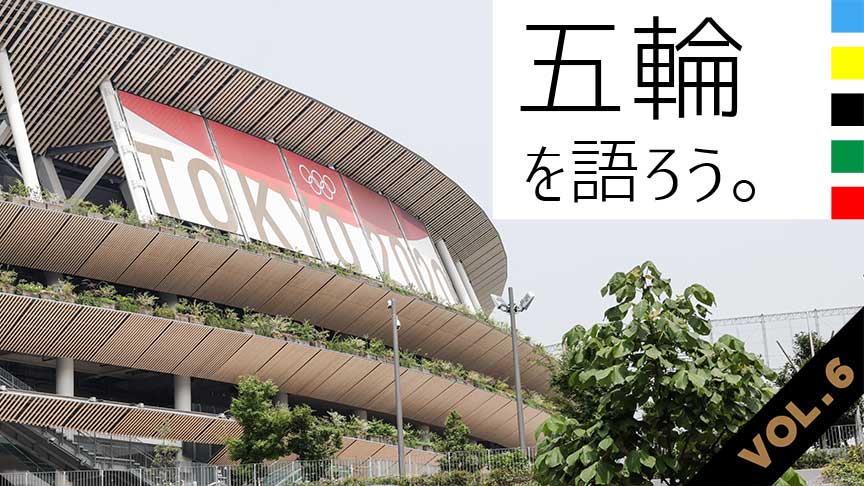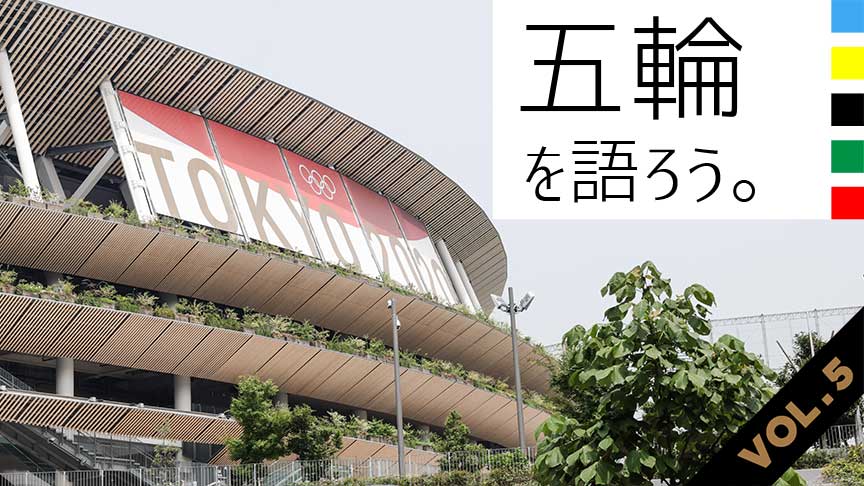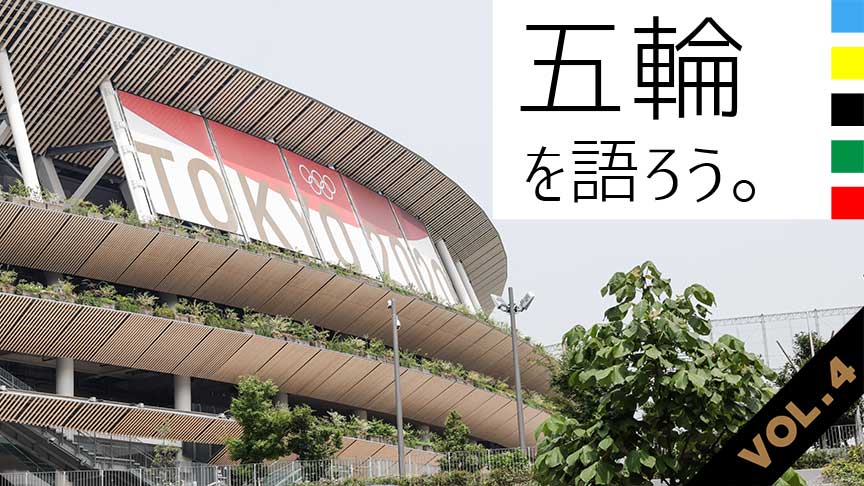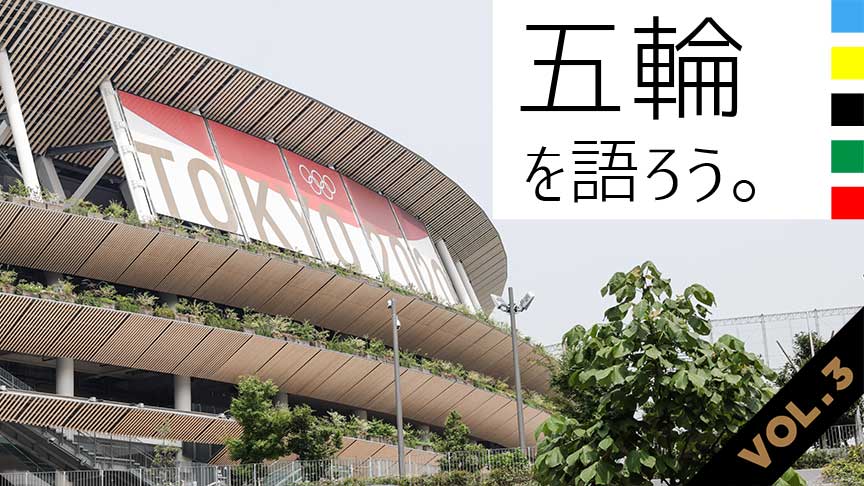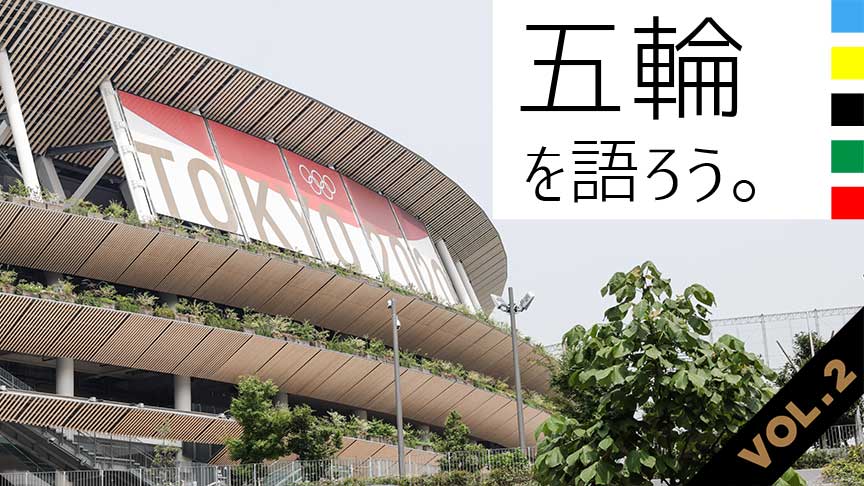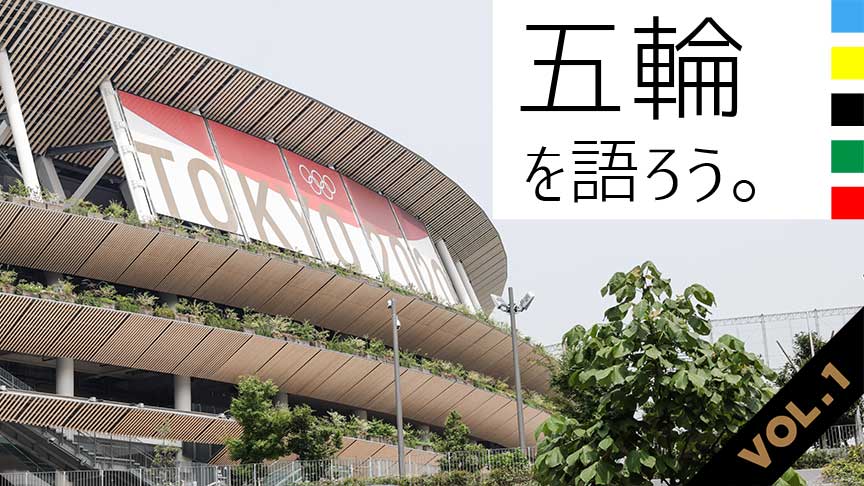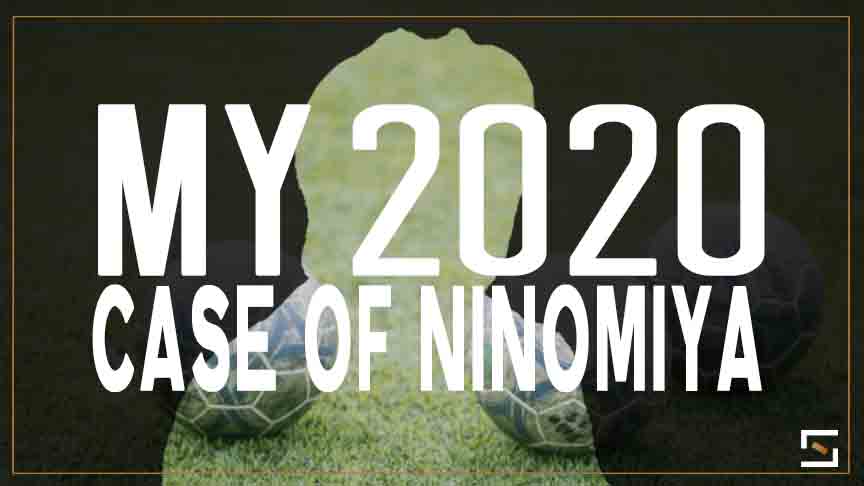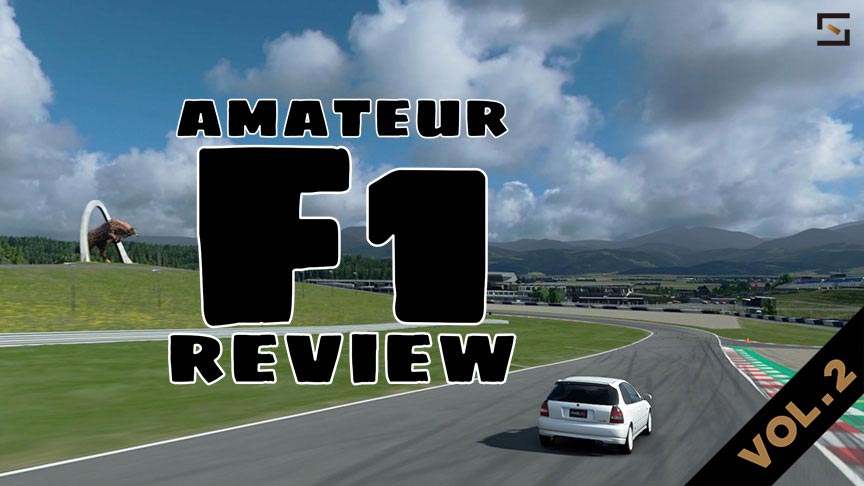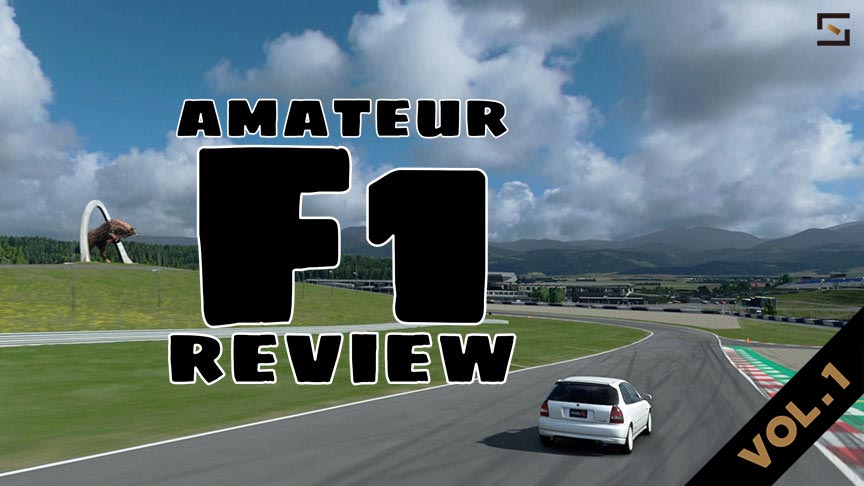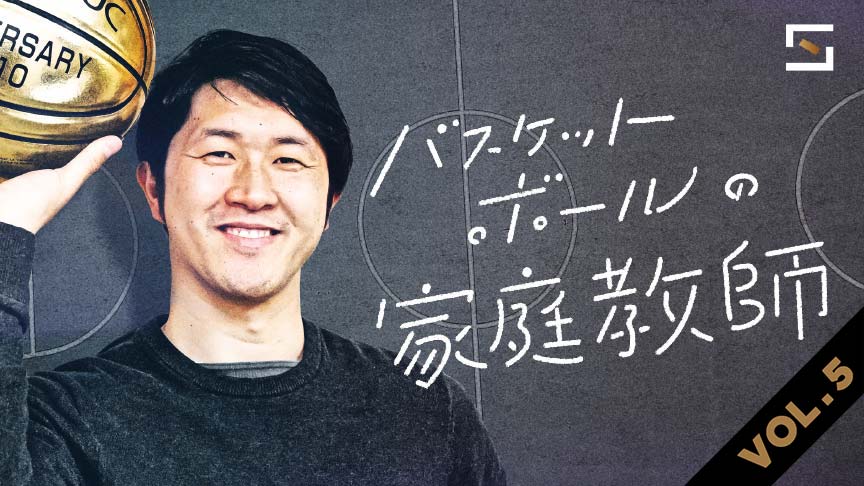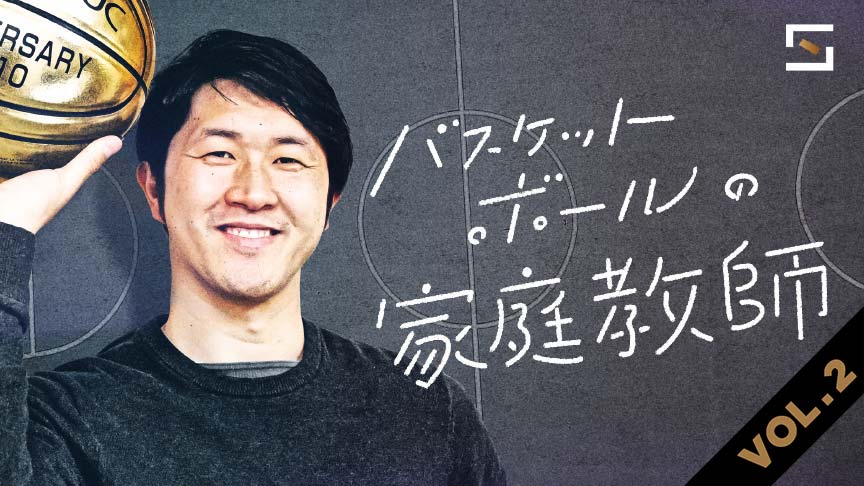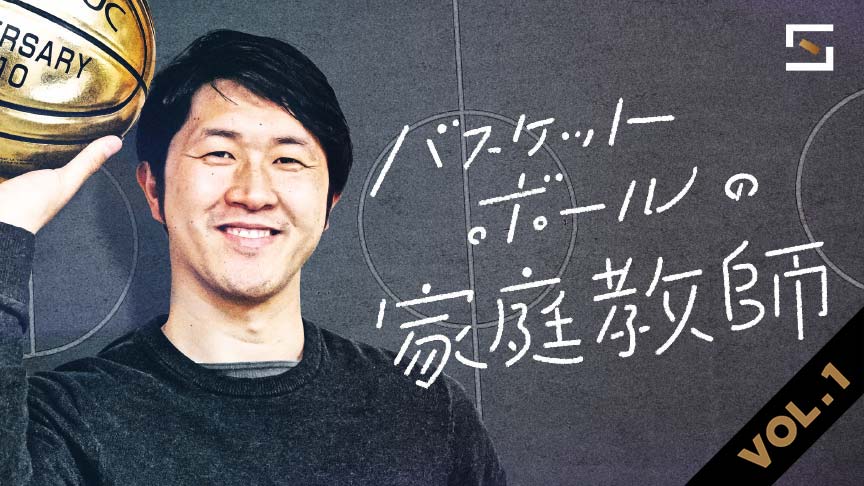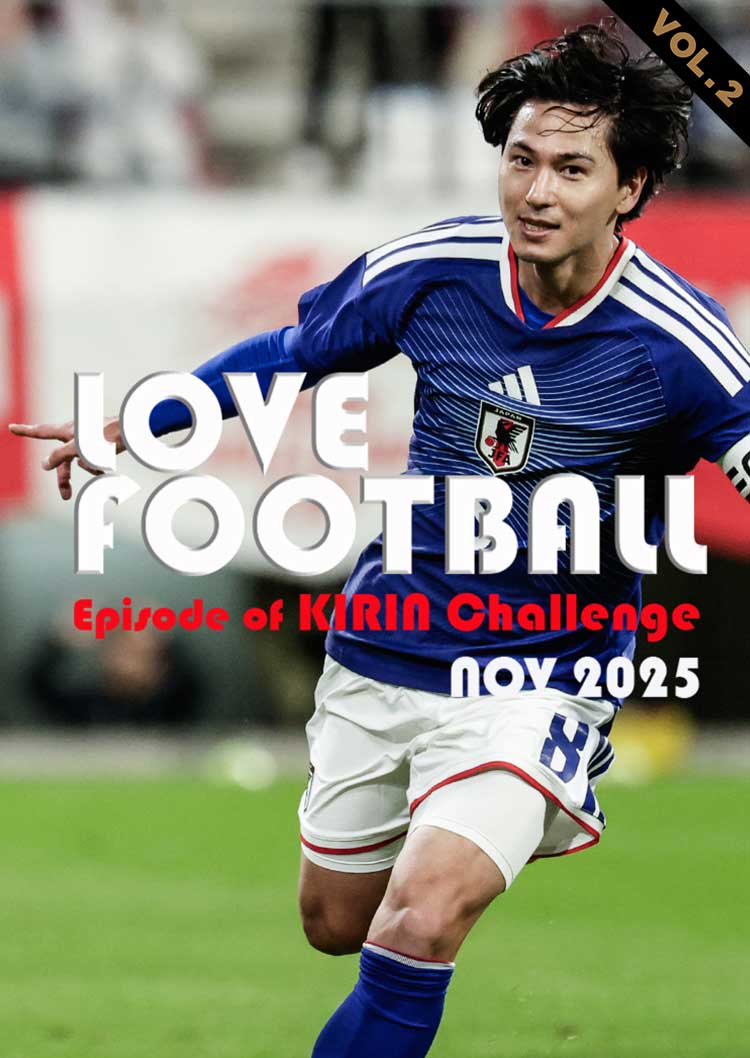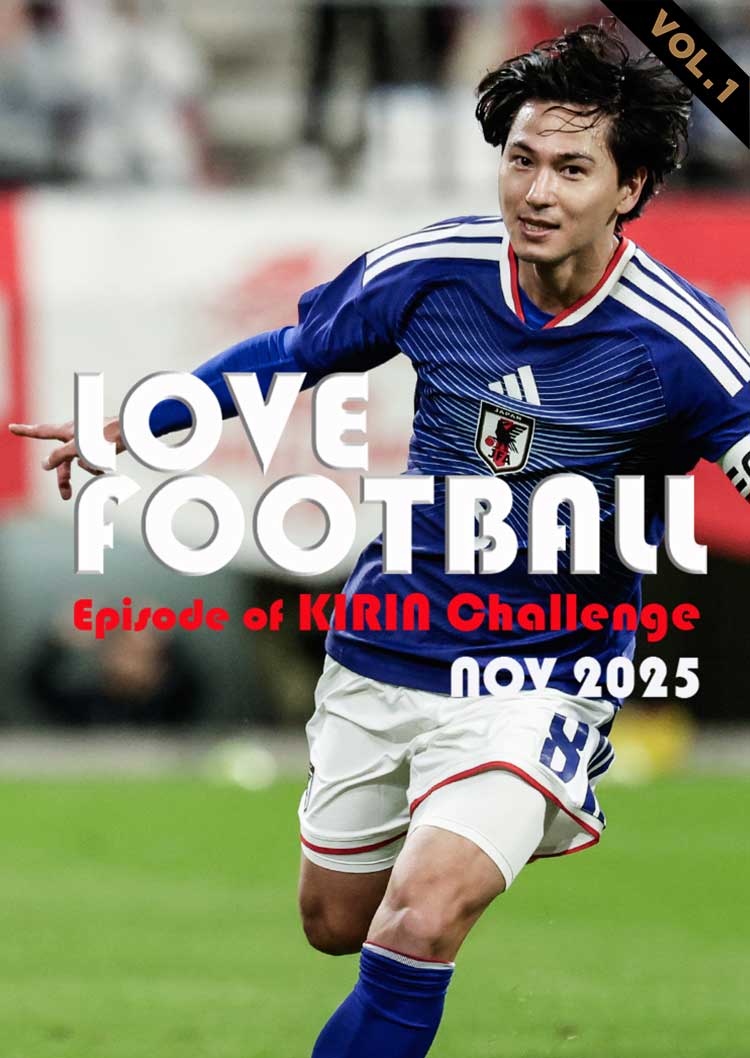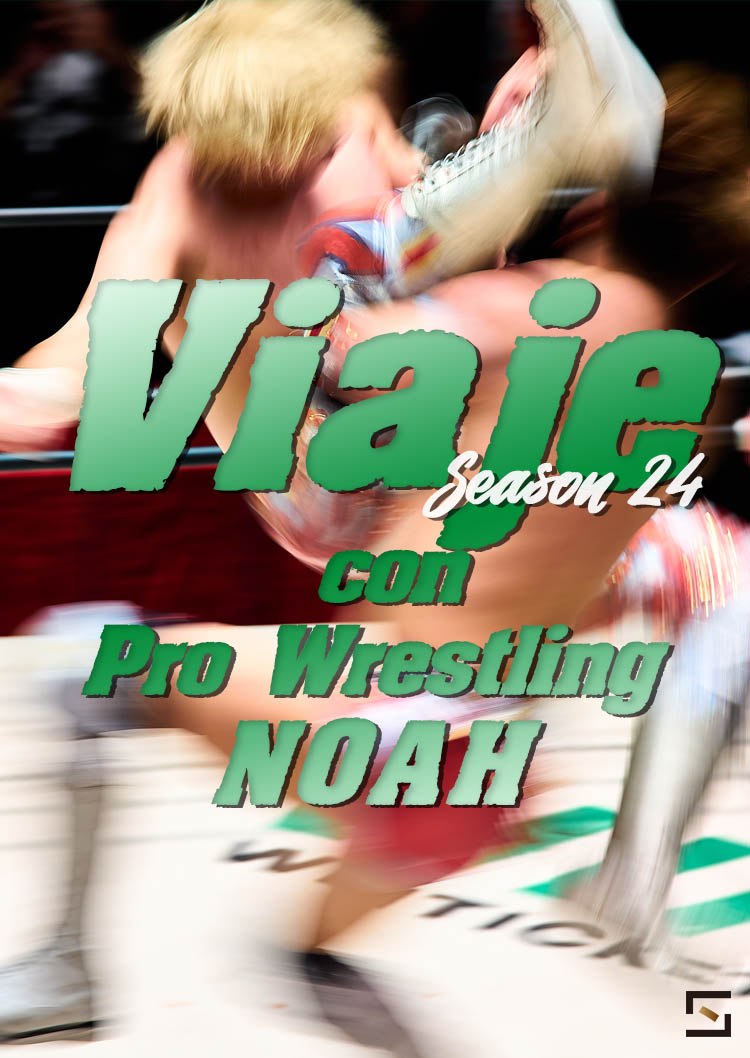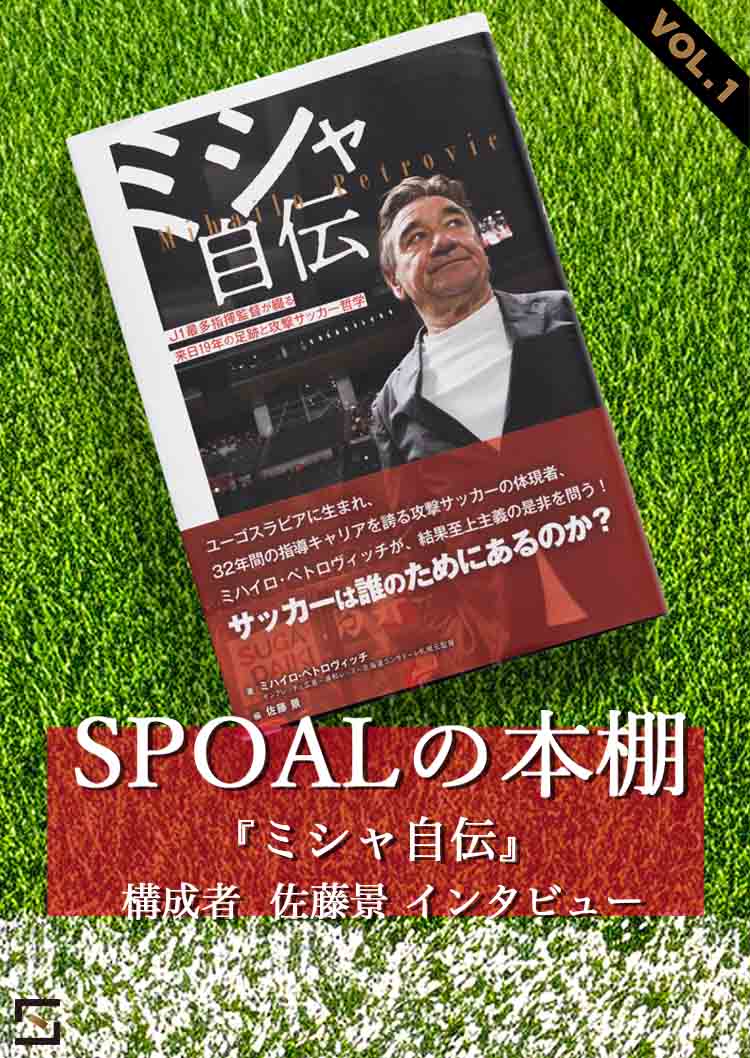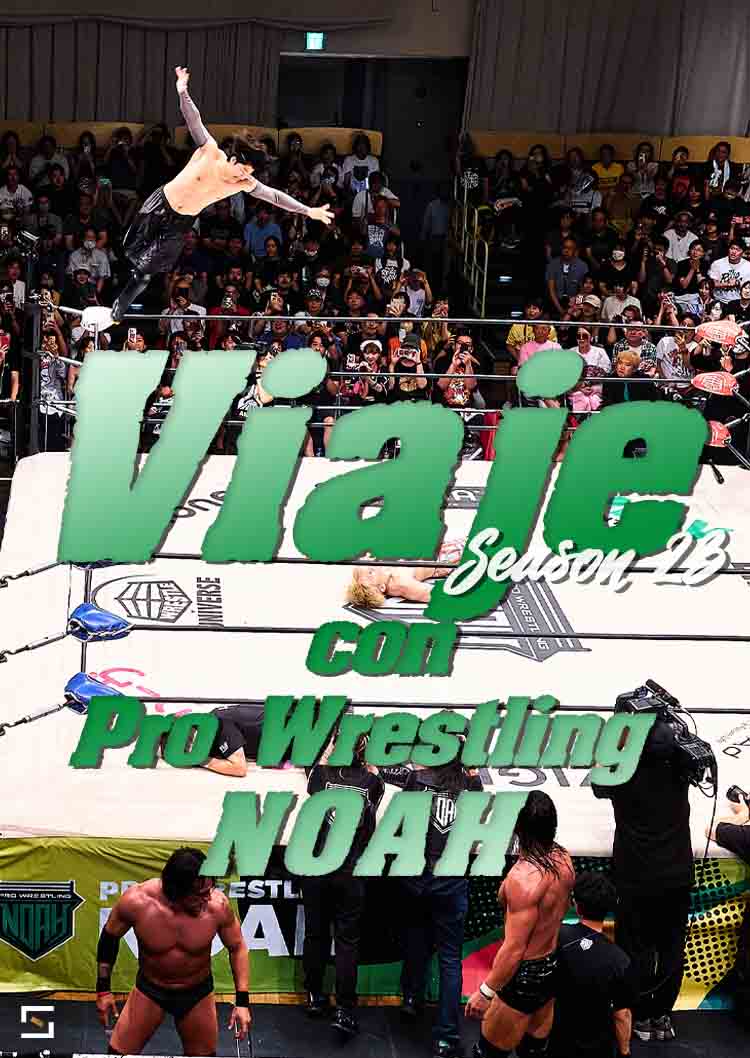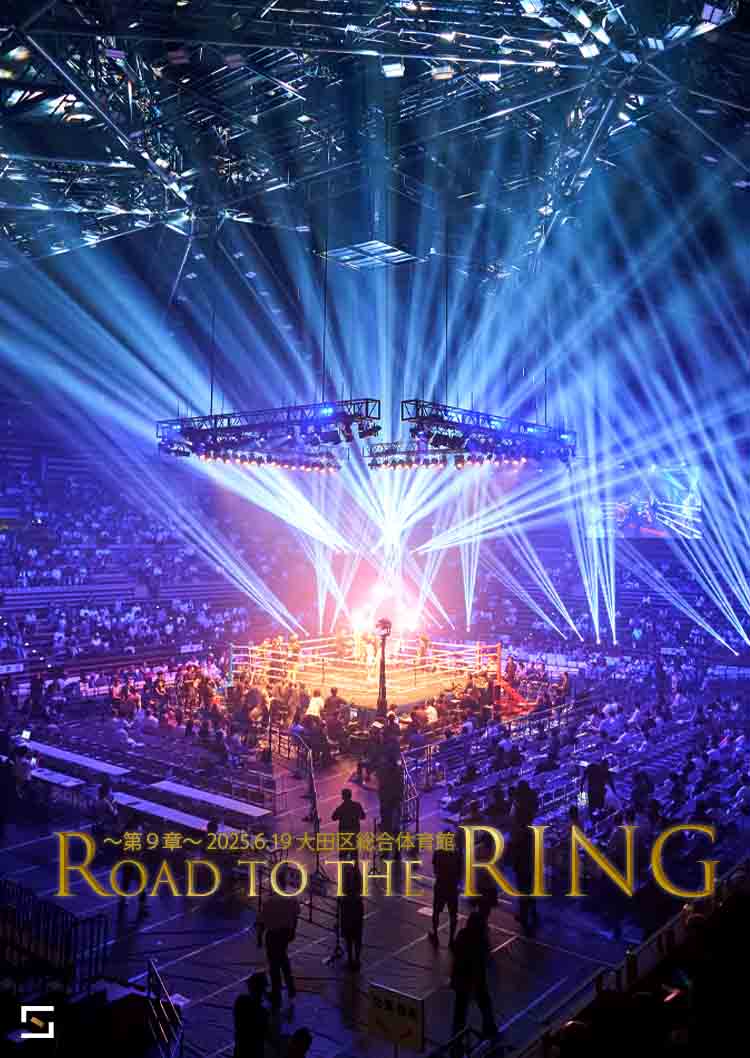目の前にショッキングな光景が広がっていた。
2018年12月22日、ラグビー大学選手権準々決勝、黒黄のタイガージャージをまとう慶応義塾は早稲田との対戦に臨んだ。その前の関東大学対抗戦での雪辱を果たすべく気迫のこもったプレーを続け、逆転に成功してラストプレーを迎えた。しかしながらペナルティーから早稲田の連続攻撃に耐えきれず、最後の最後でひっくり返された。
秩父宮に響くノーサイドの笛。目の前にあった勝利をつかみ損ね、力尽きたフィフティーンは一様にひざをついた。
スタンドから見守っていたOBの栗原徹は、表情を変えることなく後輩たちを見つめていた。
慶応大学ラグビー部(名称は慶應義塾體育會蹴球部)は日本で初めてラグビーチームを持ったルーツ校として知られる。栗原は創部100周年となった1999年度、上田昭夫監督のもとで大学日本一を果たした部のレジェンドの一人だ。精度の高いキックと抜群のスキルを武器に、卒業後もトップリーグのサントリー・サンゴリアス、NTTコミュニケーションズ・シャイニングアークス(入団当初はトップイースト、2010~11年シーズンからトップリーグ)で活躍し、日本代表でも27キャップを誇る。W杯では2003年のオーストラリア大会で40得点を叩き出し、五郎丸歩に更新されるまで日本人最多得点記録を保持していた。
引退後はシャイニングアークスでスキルコーチを務め、スポットでもキック指導を行なってきたが、金沢篤ヘッドコーチの退任に伴い、母校のOB会から次期ヘッドコーチ就任の要請が届いたのだった。
まだ迷っていた。
ショッキングな敗戦を目の当たりにしたこの日、サンゴリアス時代の恩師である清宮克幸とアポイントを取っていた。
尊敬する人は、何と言うだろうか。だが、就任については何も言ってくれなかった。その代わり、指導者の先輩としての大事なアドバイスをくれた。
「いいか、クリ。大切なのは愛だぞ。一人ひとり愛を持って接することが大事だぞ」
愛。
栗原が引き受けることになるだろうとこの人は予測していたのかもしれない。慣れ親しんだ清宮節を久々に聞いて、何だか心が落ち着いたような気がした。

シャイニングアークスとの契約も残っていたため、チームから引き留められたらヘッドコーチ就任は断ろうとも考えていた。だが部とチームの話し合いによって円満解除となり、母校に戻ることが決まった。
自分ができることを、一生懸命にやる。
栗原はそう、心に決めた。
慶応は1999年度以来、大学日本一から見離されている。初の医学部生キャプテンとなった古田京、辻雄康、丹治辰碩ら花園出場経験のある慶応高出身のタレントが卒業して一気に抜けることで、部は転換期を迎えることになった。40歳の新米ヘッドコーチには「部を変えていく」改革の好機だと考えた。前ヘッドコーチの金沢のチームづくりに敬意を表すとともに、自分にバトンを託したOBたちの期待に応えるためにも、生半可な決意ではいけないと己に言い聞かせた。
改革していくには、同志がいる。
その意味で大きかったのが、盟友である和田康二の存在だ。栗原と和田は茨城の清真学園中学、清真学園高校、そして慶応大学とずっと一緒。ラグビーで汗を流し、大学日本一も一緒に経験している。栗原と同じくサンゴリアスから誘いを受けたものの、ゴールドマンサックス証券に入社してビジネスマンとなる道を選んだ。栗原よりも先に母校の監督を務めた実績もあり、19年度からは新GMとして盟友を支える立場となった。
2人には〝上田イズム〟が流れている。
20年前、上田は慶応からの「内部生」を鍛え上げることにこだわるのではなく、有望な選手に声を掛けて受験させた。「外部生」のタレントを集めたことが、組織を強くした。
さらには林雅人という優秀なフルタイムのコーチを置き、オーストラリアの理論的なアプローチが持ち込まれた。コンディション管理を含め、様々な面で上田が改革したことによって日本一に至った。上田は2015年に病気で天国に旅立ってしまったが、彼の教えは2人に刷り込まれていると言っていい。
慶応の良さとは、一体何なのか。頭のなかで栗原はもう一度整理した。
「ラグビーを真っ先に取り入れたのも、新しいものを受け入れる度量が慶応にあるから。伝統を大切にしつつ、いいと思ったら積極的にやっていくのが慶応の本来の良さなんじゃないだろうか」
「外部生」出身だからこそ、もっと斬新なアイデアを実行に移せるんじゃないか。
栗原は強く思った。
「一生懸命にやった先にしか日本一はない。学生たちだけじゃなく、自分たちもそういう意思を持たないといけない。上田さんがいろいろと改革をして、一生懸命にやって(日本一に)たどり着いたように」

行動の人は早速動く。
和田の承諾を得て、まずは外部からコーチを招聘することにした。サンゴリアス時代のチームメイトである竹本隼太郎、元キヤノン・イーグルスの和田拓、そして元東芝ブレイブルーパスの三井大祐だ。竹本、和田は慶応OBだが、三井はライバルの早稲田OBで、かつ前年度まで早稲田大を教えていた。
早稲田のOBが慶応を教えること自体、まさに異例中の異例。
120年前、ラグビーを最初に取り入れた慶応が、早稲田をはじめ他の大学に伝え、広めていった。その慶応が、逆にラグビーを教わるなんて!と反発の声がOBから上がるかもしれない。しかしそれも「変わる」ための栗原なりの決意表明でもあった。
「慶応には学生コーチというシステムがある。しかしラグビーの専門的な知識のあるコーチに指導してもらうことが、必ずや学生にもプラスになる。そして何よりも彼らの人間形成において、社会人経験を持つコーチと色濃く接する機会を創出したい。コーチング100、人間形成ゼロでは、人間的な成長が生まれにくい。ラグビーを通じた人間形成を考えると、コーチの存在は非常に大切になってくる」
信念を通した。
環境の整備に着手すると同時に、学生たちのマインドを変えていかなければならない。
一人ひとり、彼らの心にノックする。
栗原流改革の本丸は、ここにあった。
2020年3月掲載