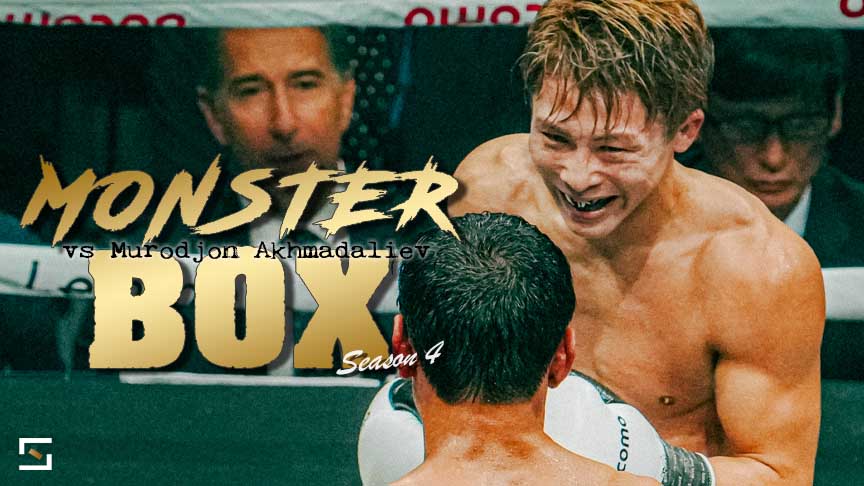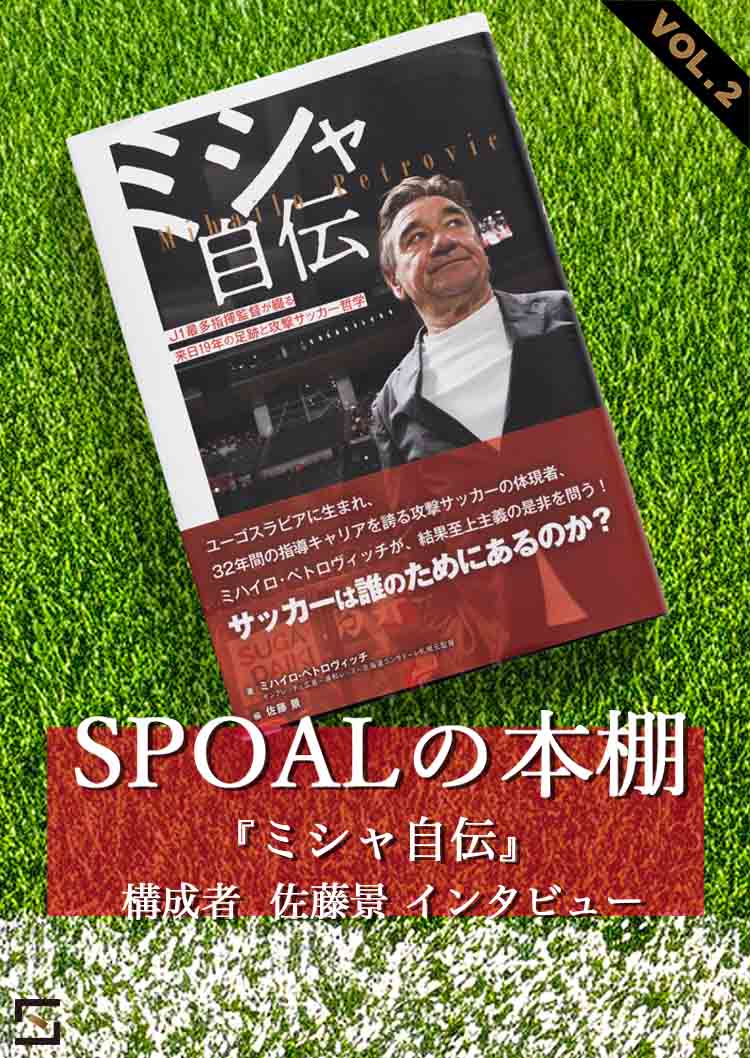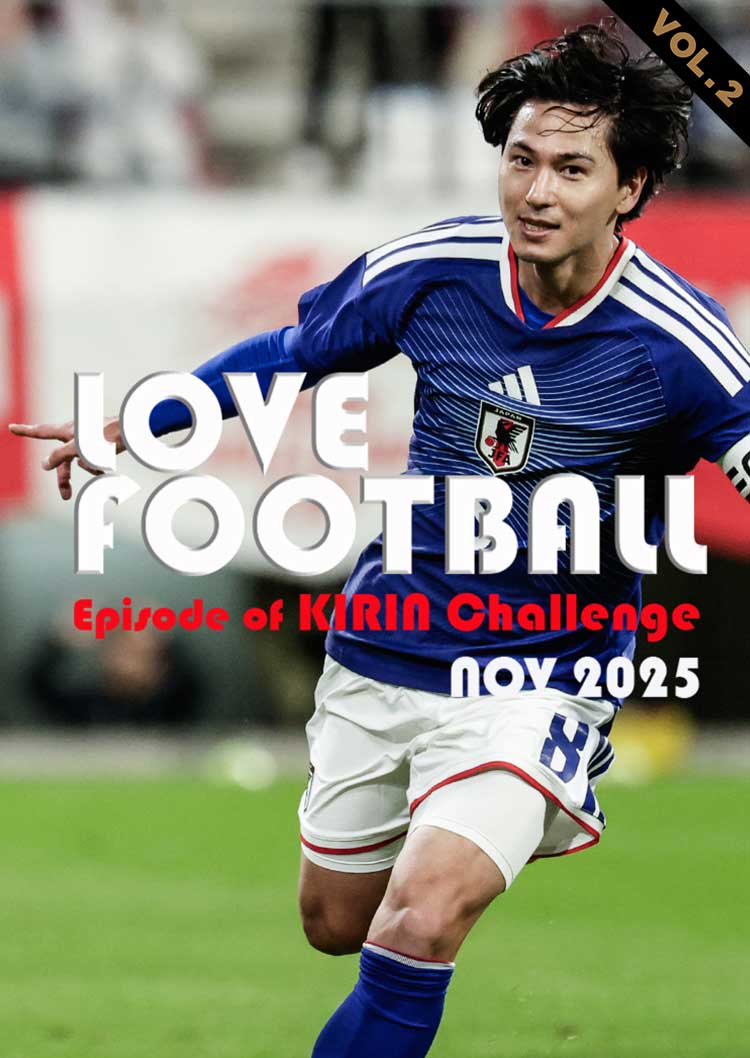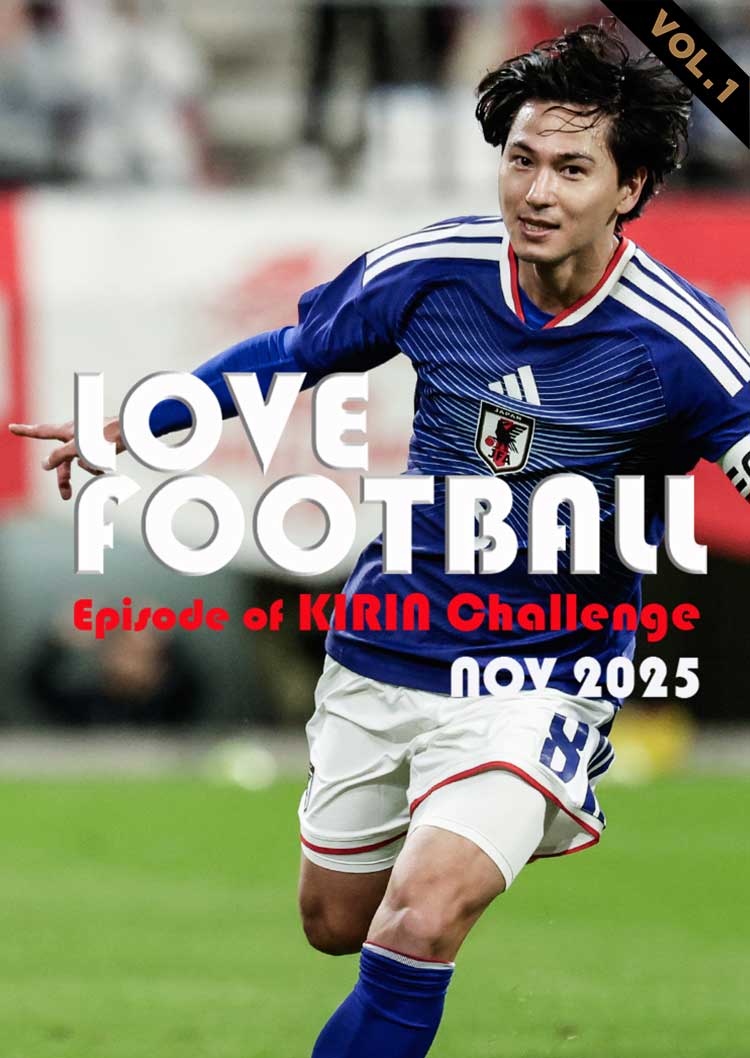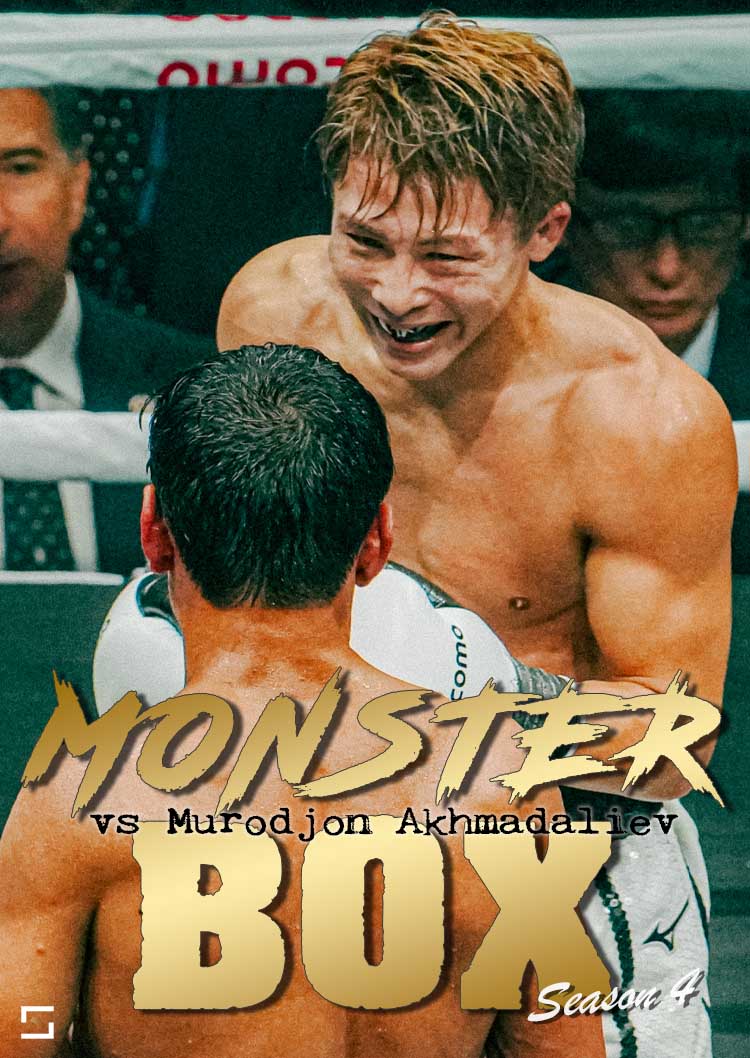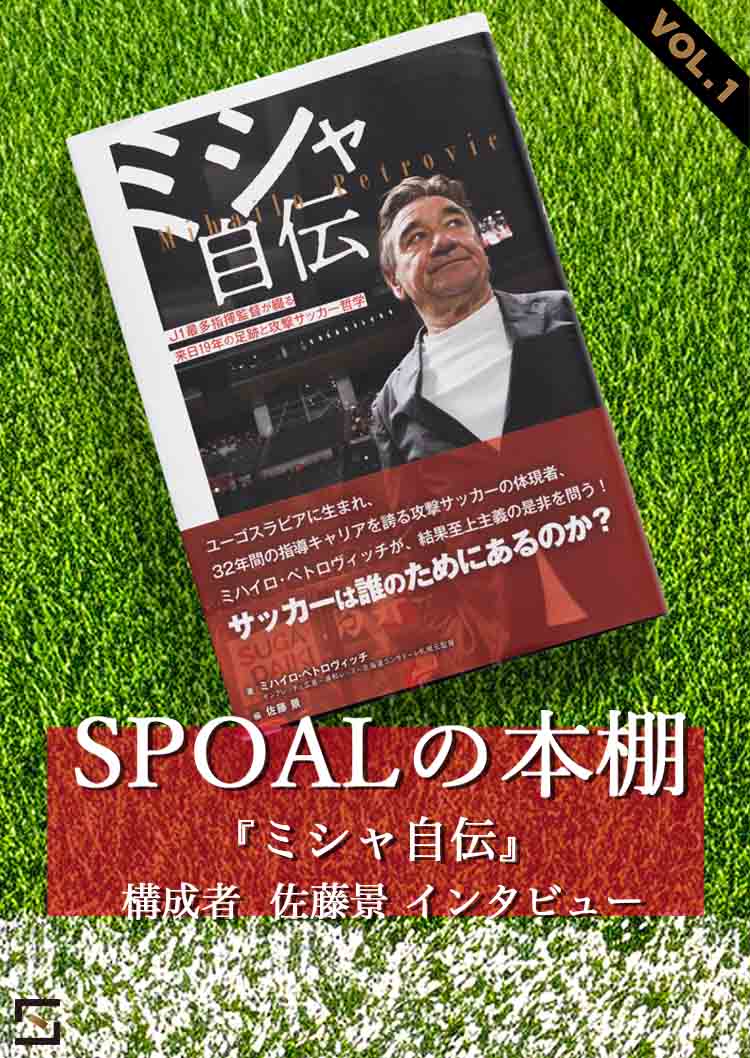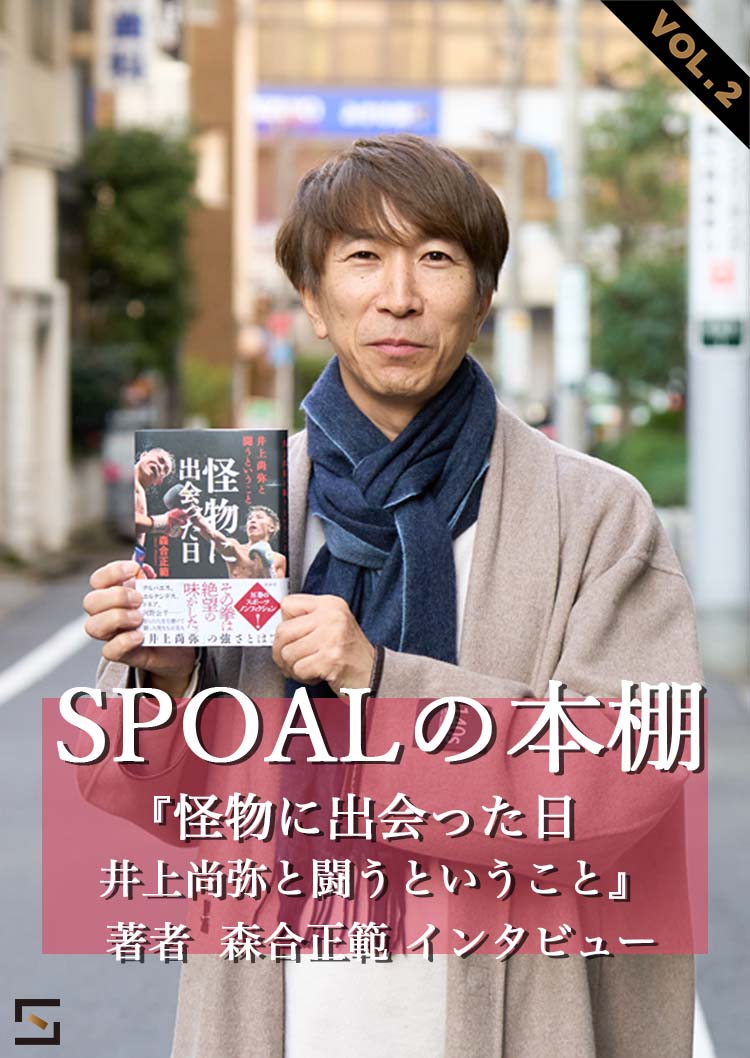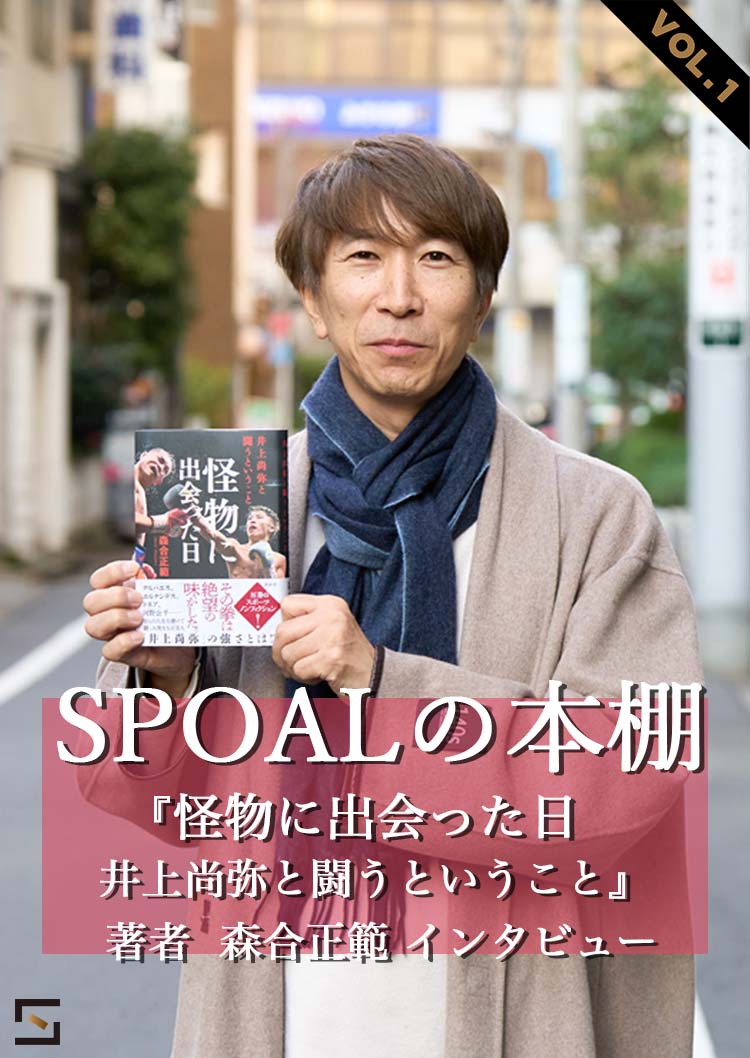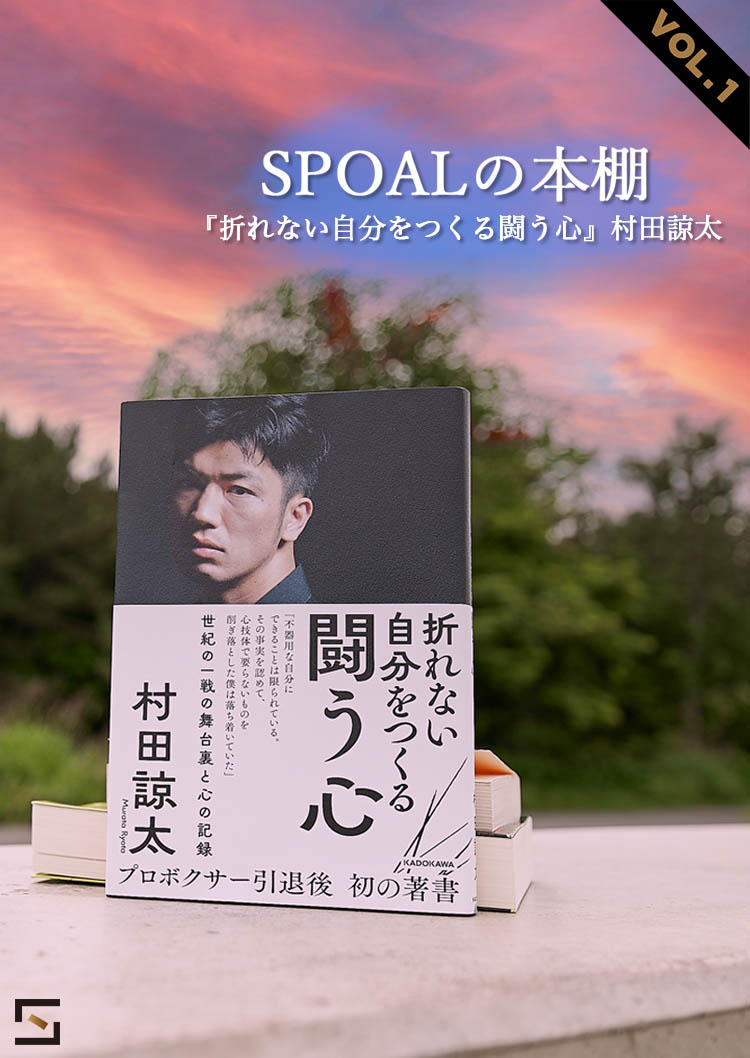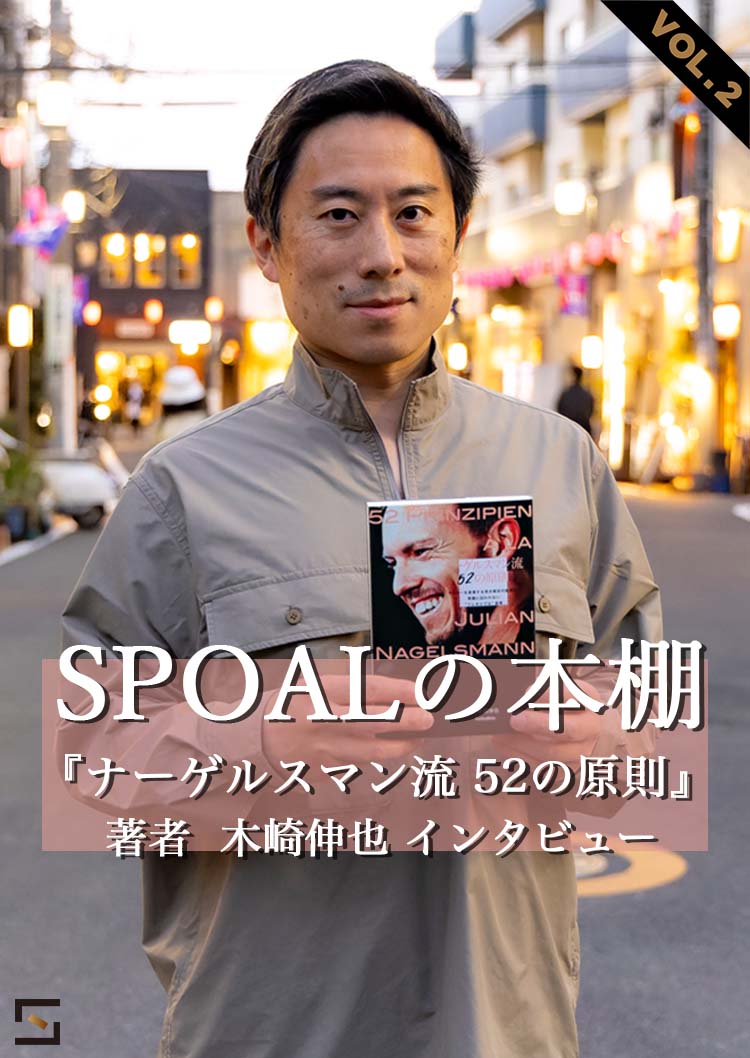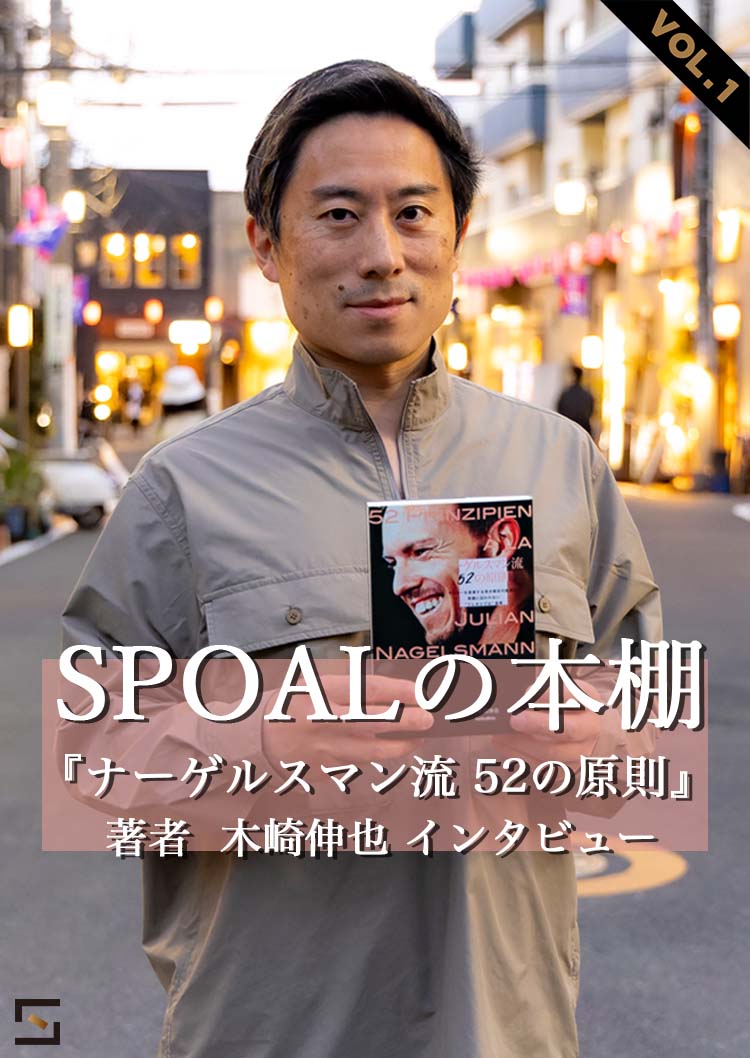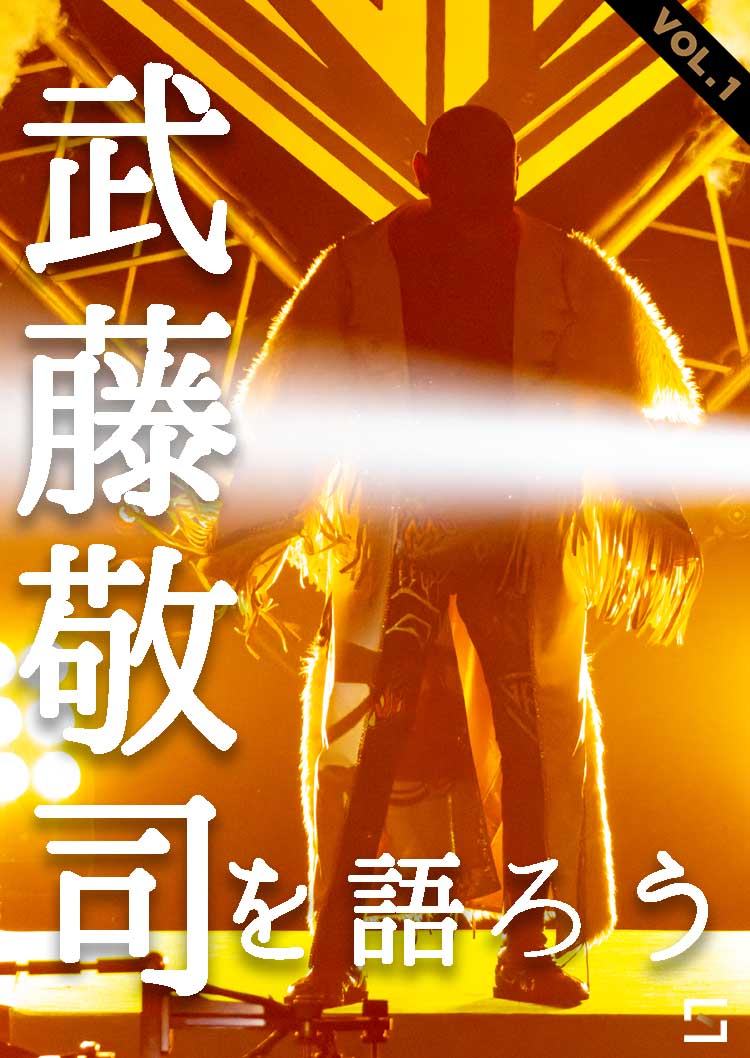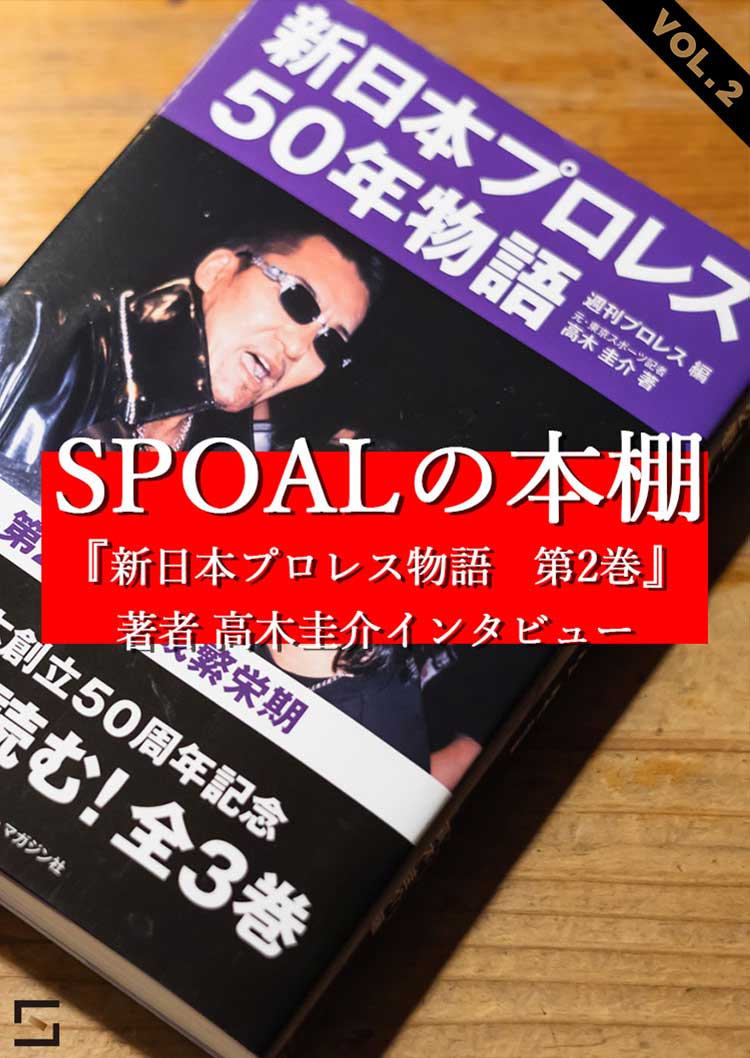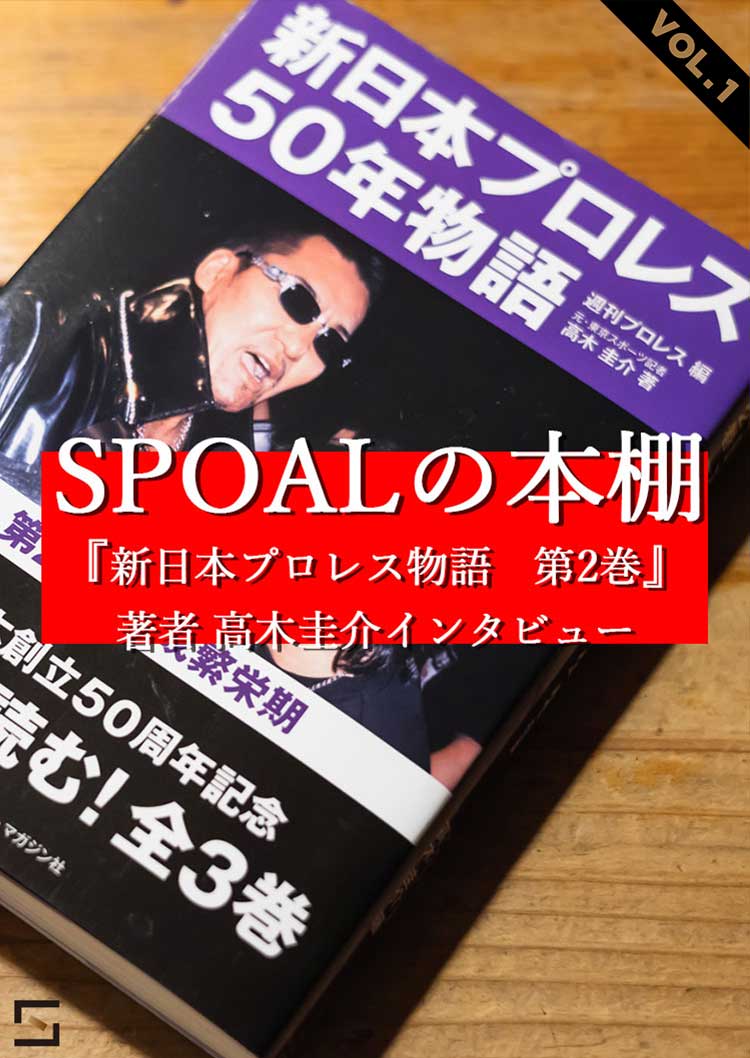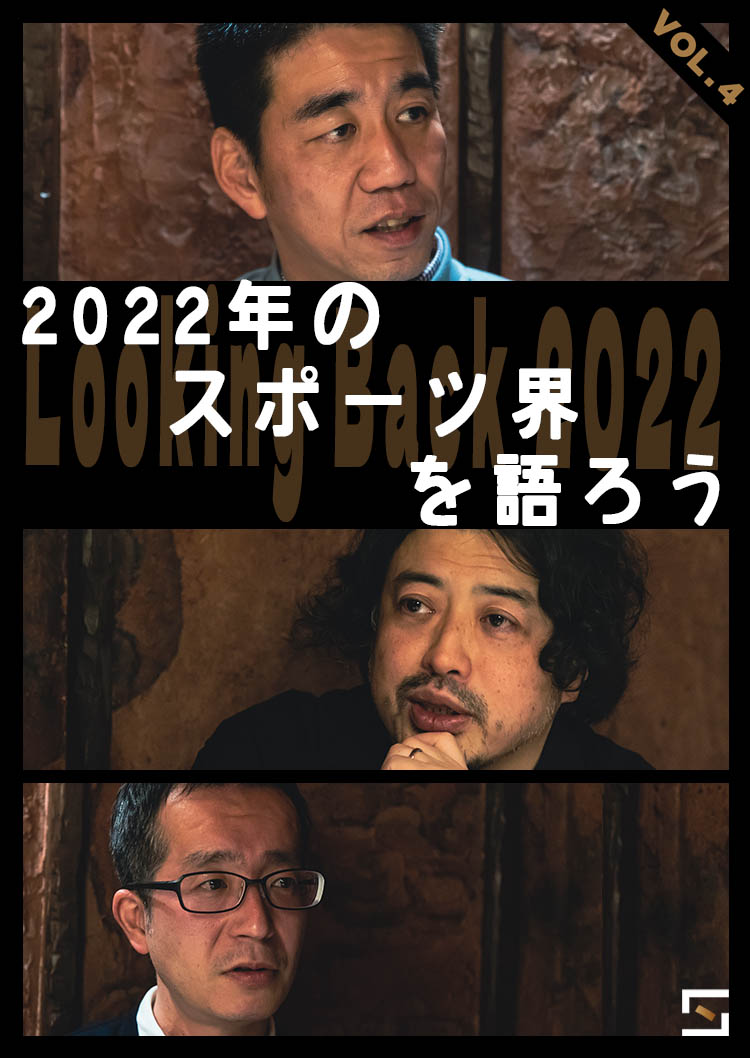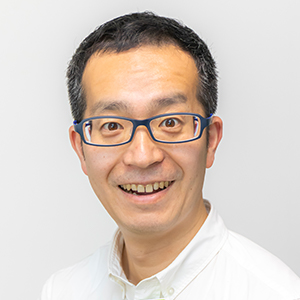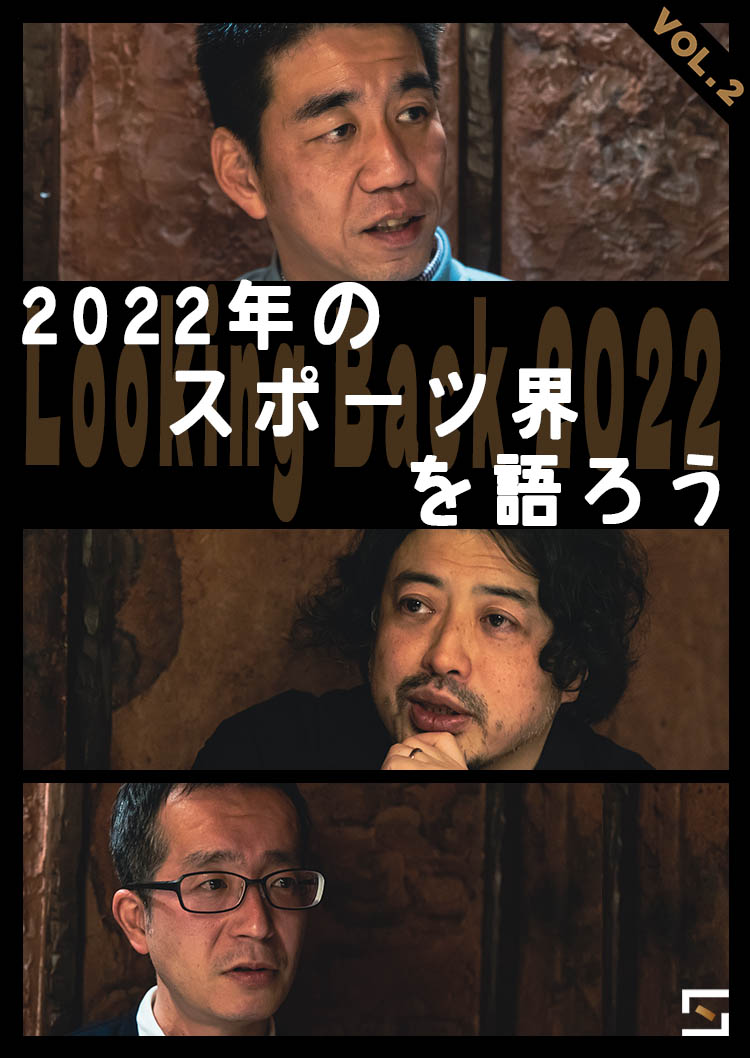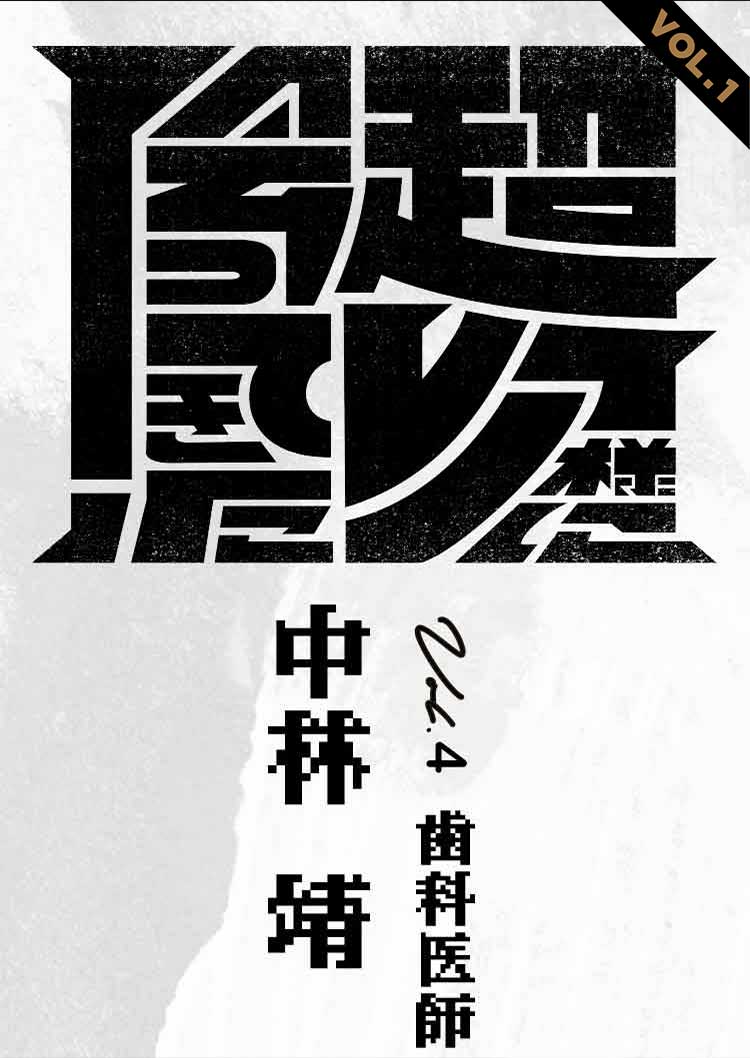二宮 ミシャさん(ミハイロ・ペトロヴィッチ)は引退して3年後に指導者として、シュトルム・グラーツに戻ってきます。そのときトップチームの監督を務めていたのが、イビチャ・オシムさんでした。あらためて説明の必要はないと思いますが、1990年のイタリアワールドカップでドラガン・ストイコビッチ、デヤン・サビチェビッチらがいたユーゴスラビア代表を率いてベスト8に進み、のちに日本代表を率いる名将。そのオシムさんとの邂逅は、本書でも章立てしているように、ミシャさんの指導者人生に大きな影響を与えることになります。
佐藤 オシムさんのことを凄くリスペクトしていることは、ミシャさんと接していても凄く伝わってきます。ただ「オシムチルドレン」かというと、本人のなかでは違うんですよね。なぜかと言ったらオシムさんのようにはなれはないから、オシムさんの頭のなかをのぞくことはできないからだ、と。
二宮 ミシャさんは当時トップチームのコーチ兼セカンドチームの監督でしたよね。本書を抜粋させていただくと「オシムさんのトレーニングは、始める前にあらゆるケースがイメージされている。どこにエラーが起こる可能性があるのか、そしてそれに対してどういう指導や対処が必要なのか。実際、オシムさんを見て私も真似したが、結局、同じようにはできなかった。誰もオシムさんにはなれない。(中略)それでも、オシムさんが見ていたもの、見定めようとしていたものの重要性だけは理解できた」とあります。
佐藤 要は、ミシャさんの説明を平たく言えば、オシムさんは数年後の、未来のサッカーを見通すことができて、ならば今何をやるべきかを狂いなくできちゃう人。常にアップデートされているってことなんでしょうね。一方のミシャさんは数年後の未来を見通せないけど、重要なものが何かとは分かっているので、自分のやり方でトライしてみようとする。そこに大きな違いがあるんだというのがミシャさんのなかにあります。
二宮 ジェフユナイテッド市原時代にオシムさんはマンツーマンを用いていて、時間を経てミシャさんも北海道コンサドーレ札幌でマンツーを採用するじゃないですか。自分のやり方でトライしつつ、オシムさんと同じところに行き着いていくというのが何ともまあ面白いですよね。
佐藤 2020年シーズン前のキャンプでオールコートのマンツーをミシャさんが持ち込むわけですけど、Jリーグでもポジショナルプレーが浸透してきたなかで予算の限られているクラブが勝つために何をしなきゃいけないかと言ったら、マンツーマンでその位置にいる相手を潰して、ポジショナルプレーを無効化しなきゃいけないということだった。それを先んじてやったのがミシャさん。それにマンツーマンと言っても、カバーの意識も忘れていない。10対10のカップリングで1人でも抜かれたら成立しないし、実際それでやられたシーンもメチャメチャありましたよ。ただミシャさんは1人外してカバーをつける意識を植えつけようとした。正直うまくいったとは言えないけど、その発想は革新的ですよ。
二宮 何が凄いかって、監督としてあれだけキャリアを重ねても自己改革ができる点ですよね。先が見えているオシムさんとアップデートの速度は違うかもしれないですけど、ちゃんと自分のやり方で答えを出していこうとする。
佐藤 選手には相当しんどいことを要求することになります。層が薄いと、なかなか難しい。ミシャさんの要求に応えられる選手を集めるにはクラブの資金力も必要になってきますからね。このやり方がどう発展していくか、もう少し見たかったというのが正直なところです。
サンフレッチェ広島監督時代のペトロヴィッチ監督。通訳を務めた杉浦大輔さんと長年タッグを組むことになる(写真・高須力)
二宮 ミシャさんの革新性で言えば、やはりサンフレッチェ広島時代にお披露目となった可変式。攻撃時は3―4―2―1のボランチの1枚が最終ラインに落ちて、両ウイングバックを前に行かせる4-1-5になる。この5トップはかなり斬新でした。
佐藤 別にこの形じゃなくても、今の時代「可変」が当たり前になっているじゃないですか。フォロワーをいっぱい生み出していることが凄いと思うんです。このミシャ式だって相手も研究してくるのでマイナーチェンジを繰り返していて、基本フォーメーションが同じでも通用させてきた。丸裸にされたら、違う手をちゃんと打ってくる。マンツーマンだって、そうじゃないですか。ミシャさんがやったら、結局フォロワーが増えてきて、対策されたらまたマイナーチェンジをやろうとする。これをJリーグで19シーズンも続けてきた功績はもっと称えられて然るべきなんじゃないかということも、この本を企画したテーマの一つだと言えます。
二宮 J1のリーグタイトルは獲れなかったとはいえ、ミシャさんの攻撃サッカーは見ていてやっぱり面白かったです。
佐藤 もちろんサポーターからすれば優勝してほしいし、そこが一番の評価基準だということは分かっています。ただ、どんなサッカーをやっているかという部分も、評価軸としてもっとしっかりあってほしいというのが僕のなかにはありますね。
二宮 自分の半生を振り返るだけではなく、最後の章「ラストシーズン」では日本サッカーの提言もありました。ピッチ内の発展に比べてピッチ外の発展が乏しいというのは、耳を傾けなければなりませんよね。トレーニングを基本的に非公開にするクラブが増えていますが、オープンにこだわる理由についてもあらためて記されています。個人的には、後継者にずっと通訳を務めてきた杉浦大輔さんの名前を挙げているところが、ちょっとグッときましたね。
佐藤 「杉浦さんを後継者に」というのは退任会見でも語っていて、凄く期待しているんですよね。彼は今、中国に渡って3部チームの監督をしているんですけど、就任する際僕のほうにも連絡をくれて「夢としてはいつかミシャさんとお互いにチームを率いて戦ってみたい」と言っていました。実現してほしいなって思います。
二宮 それはいいですね。ミシャさんも退任会見で監督引退の可能性を95%と言っていますが、100%じゃないんですよね。
佐藤 退任後にクロアチアで手術を受けて、ますます元気になったという情報も聞いています。まだ67歳ですしね、Jリーグ復帰もないとは言い切れないと思いますよ。
二宮 「ミシャ自伝」にはまだ続きがありそうですね。楽しみです。
(終わり)