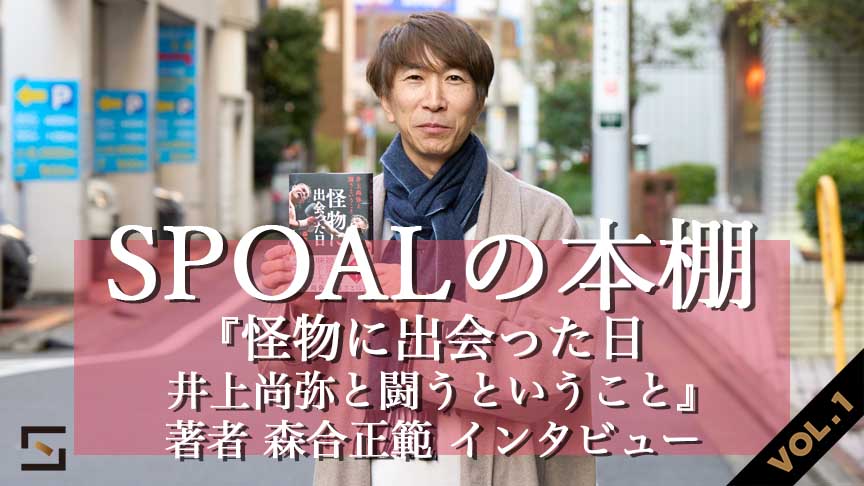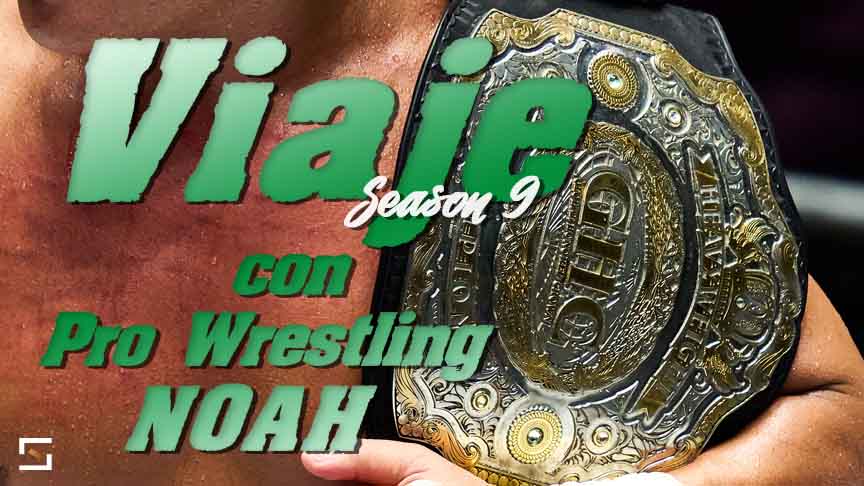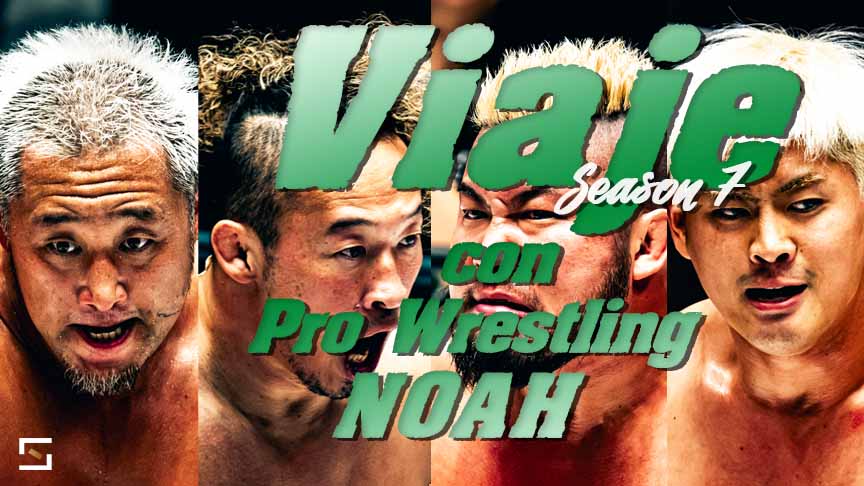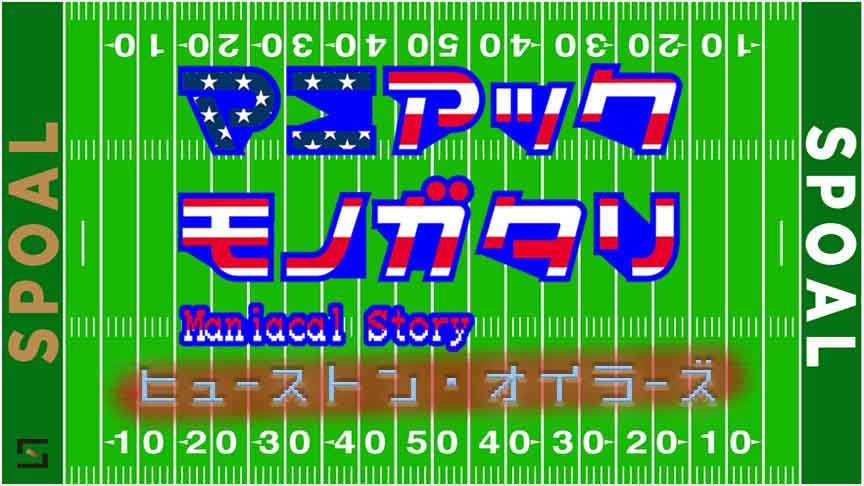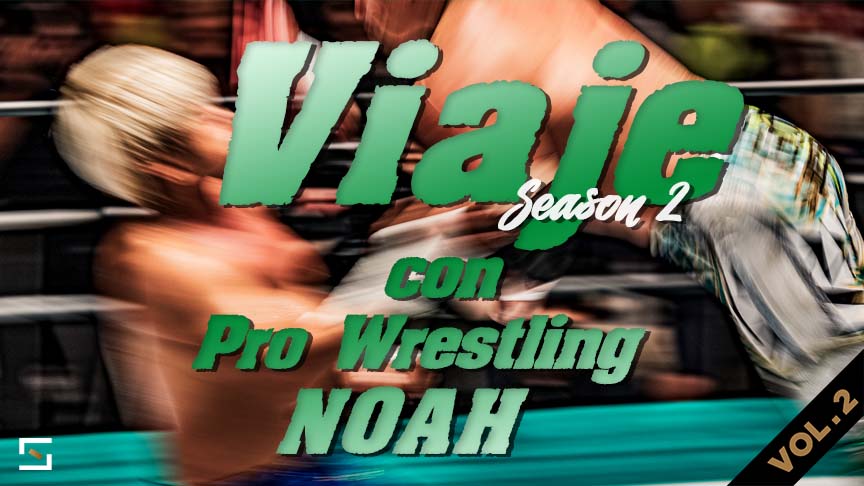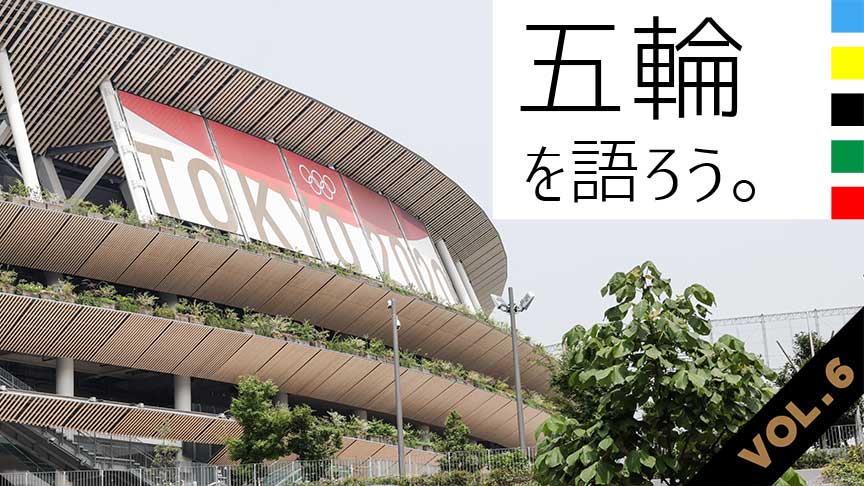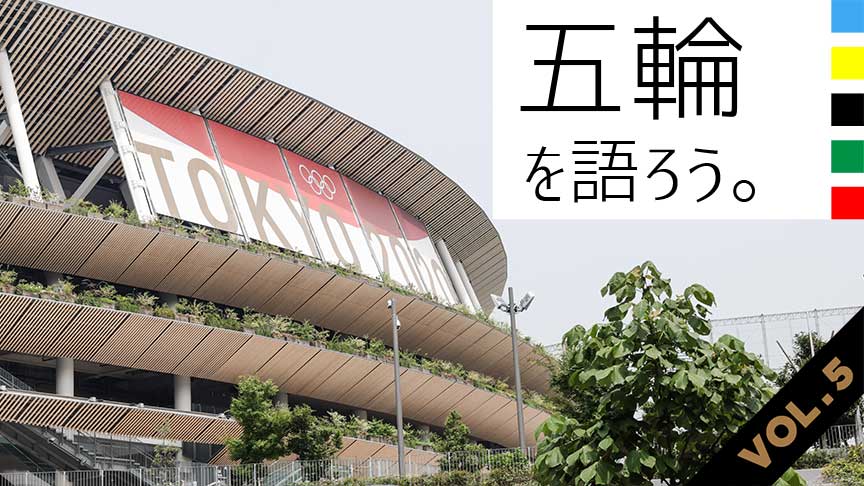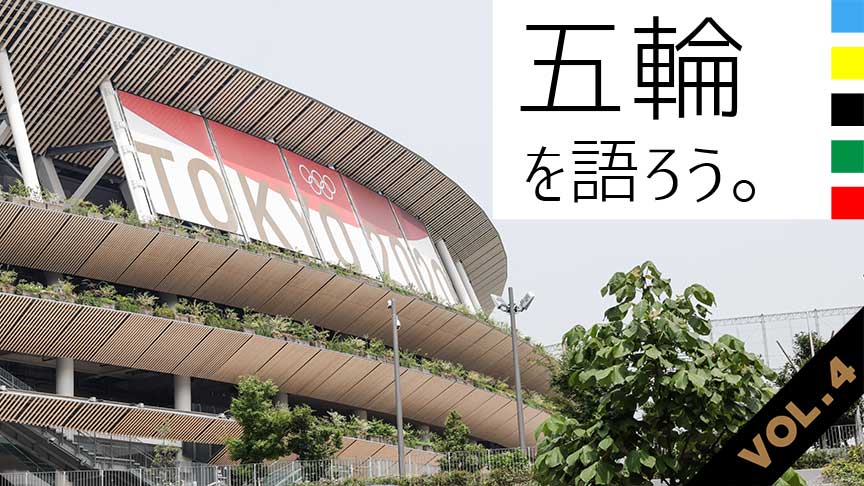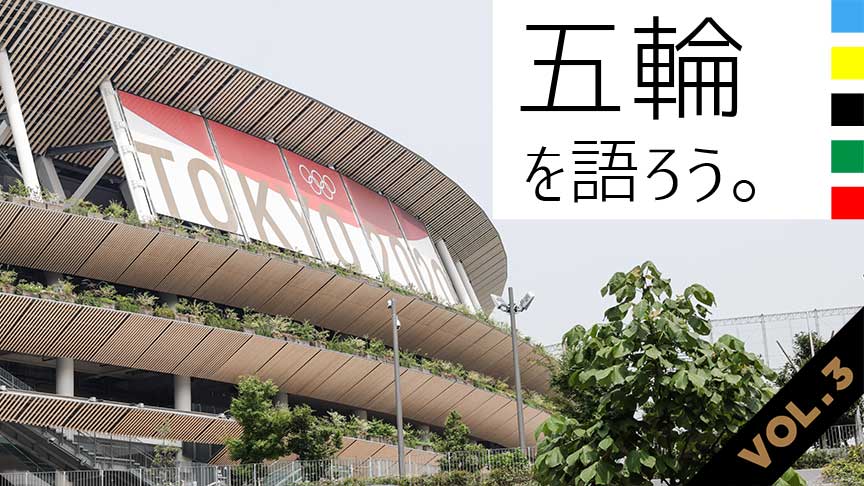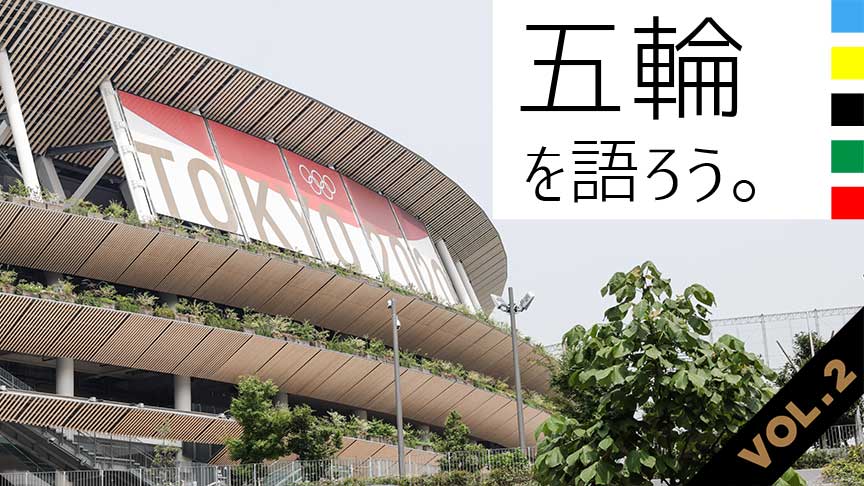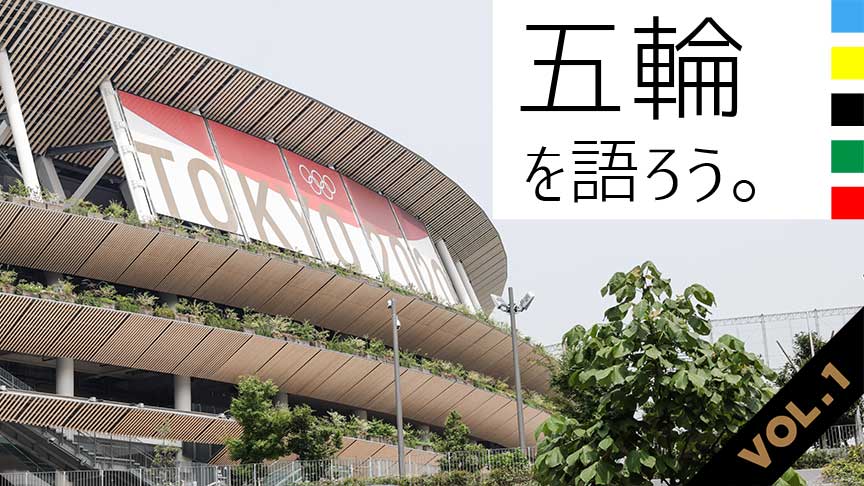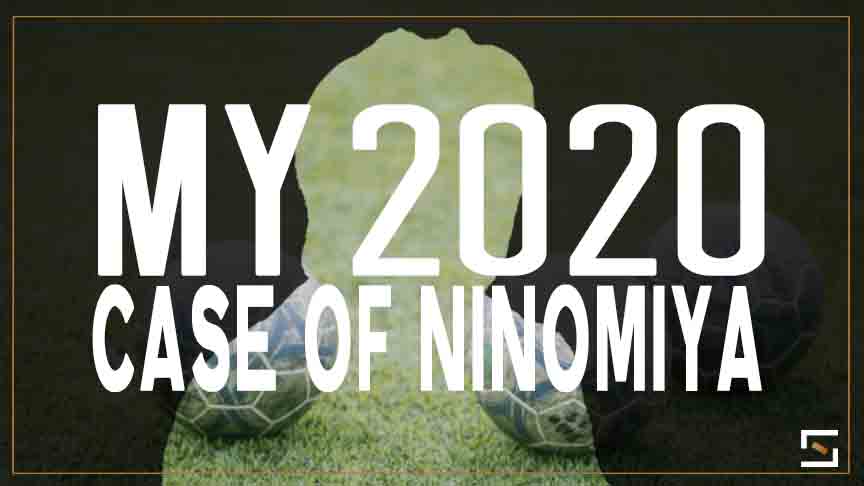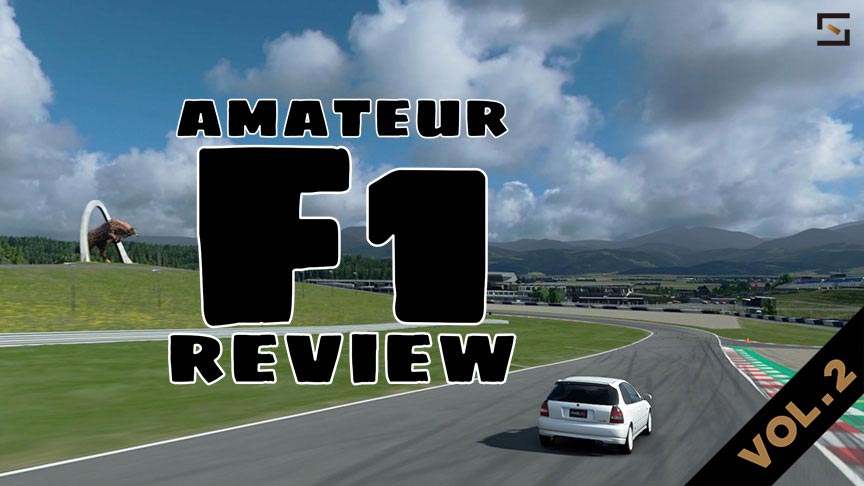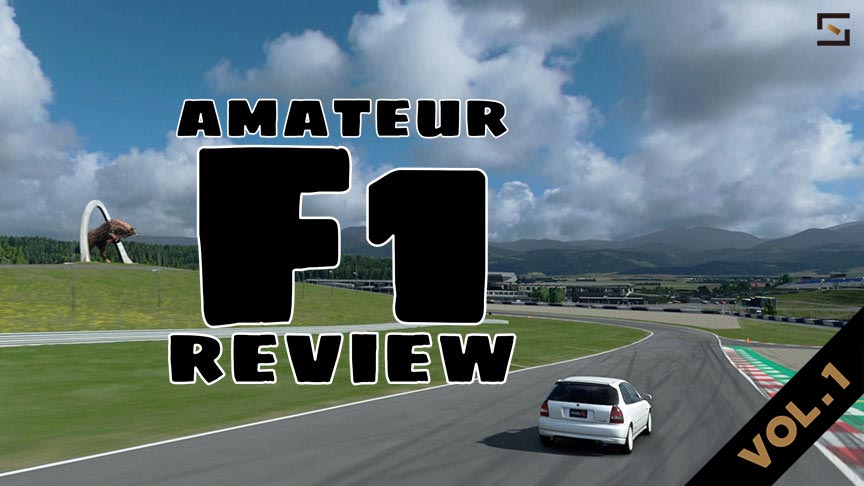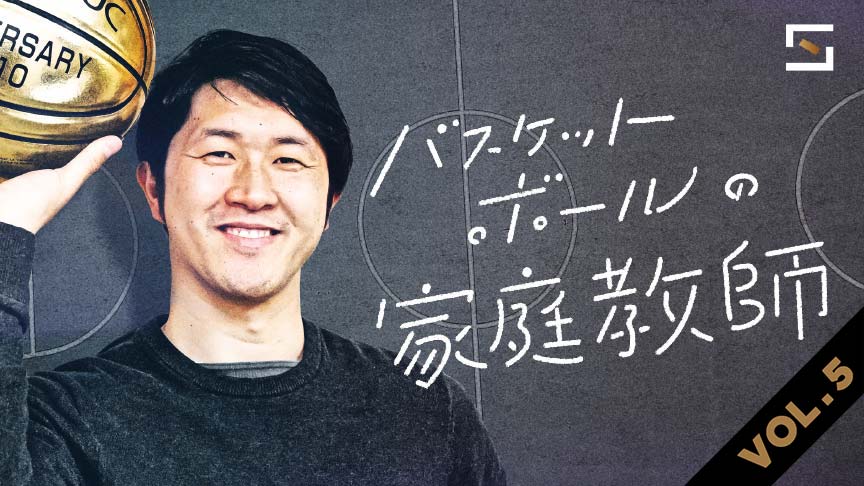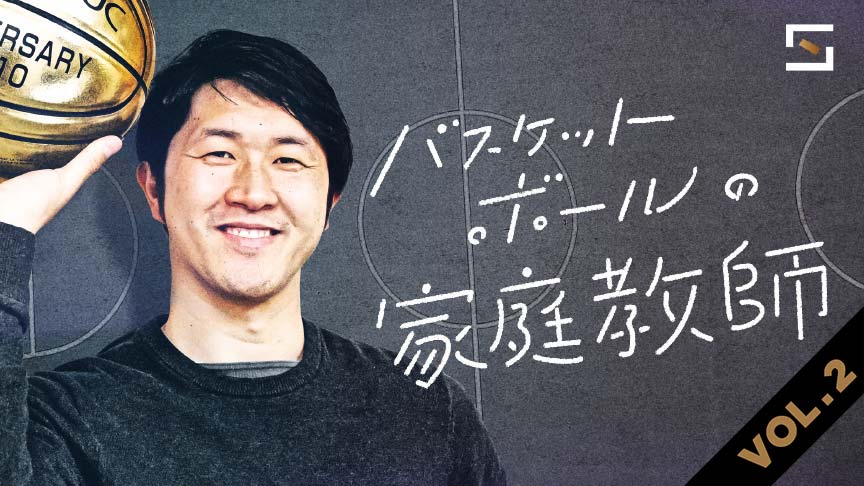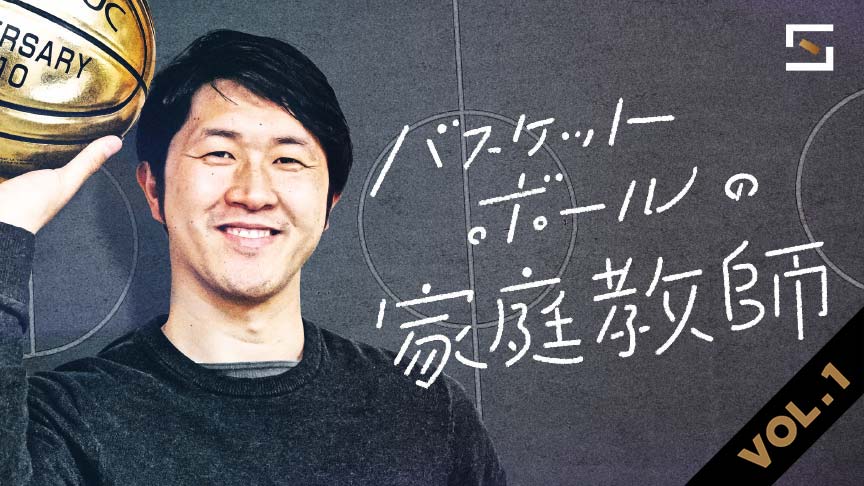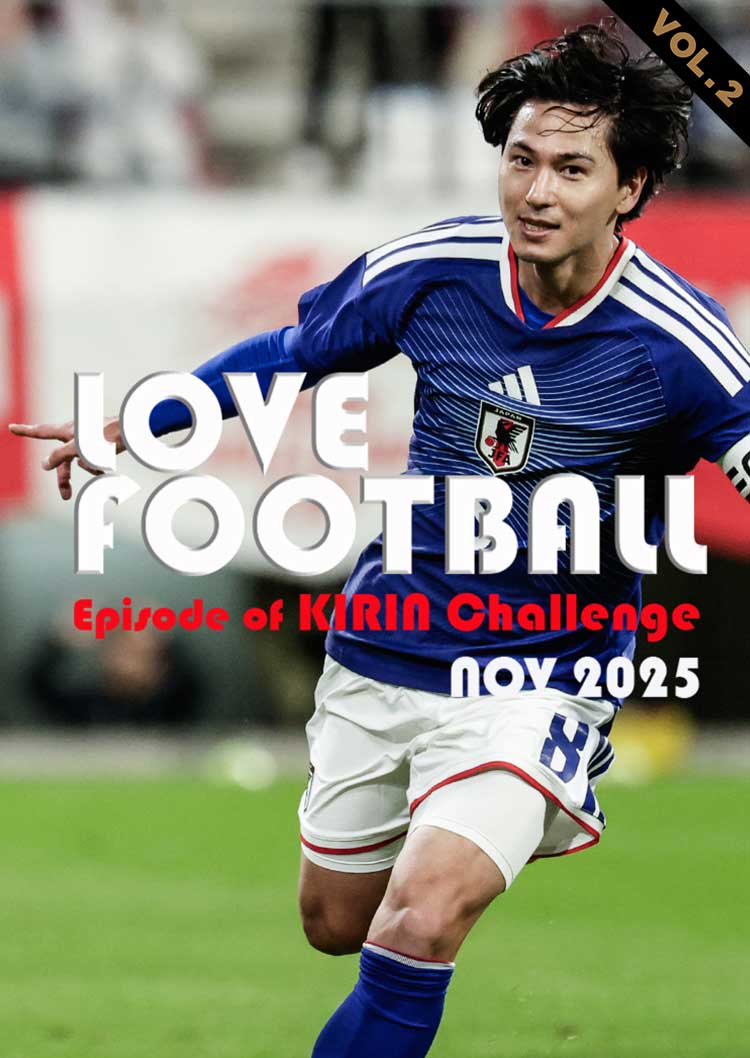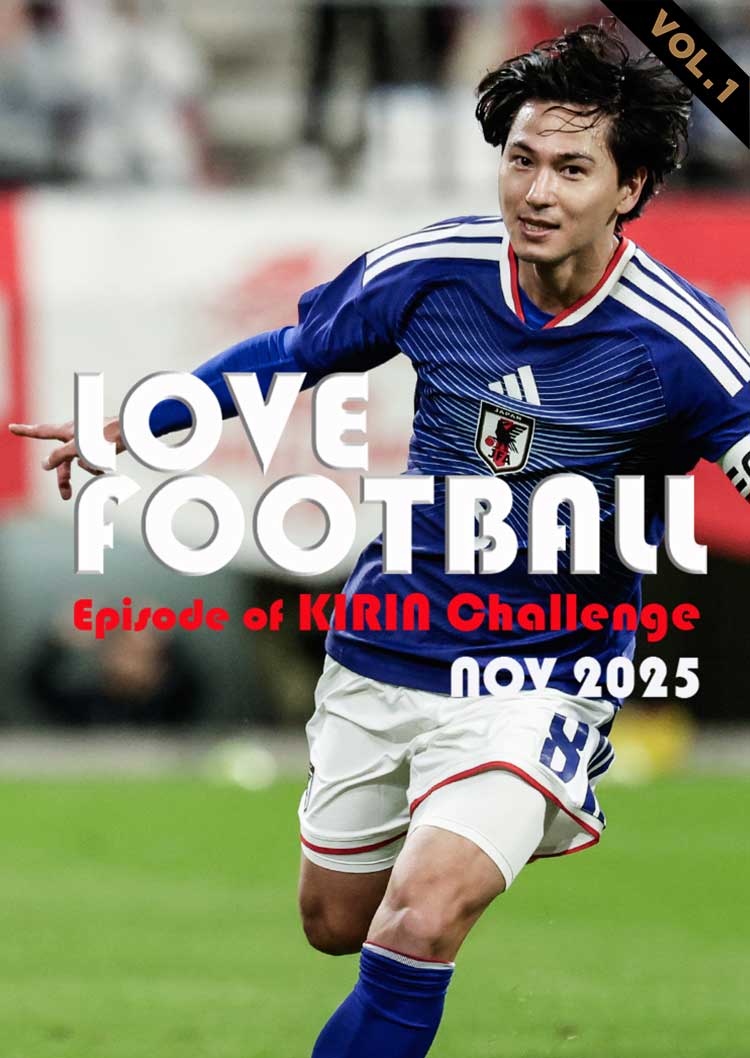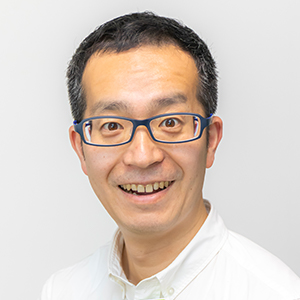アクロバティックかつスピーディーかつデンジャラス。
現代のマット界においてトップレスラーの一人となった英国出身のウィル・オスプレイが少年時代に憧れていたのが、ほかならぬ丸藤正道であった。
脂が乗り切っている現代の天才がインスパイアされた方舟の天才。邂逅は運命であったのかもしれない。
「真・飛翔~丸藤正道デビュー25周年記念大会」での対戦相手にオスプレイ自ら名乗りを挙げ、シングルマッチでの初対戦が決まった。

オスプレイに負けず劣らずのテンションで胸を高鳴らせる丸藤がいた。
「自分が求めているものと、SNS含めて周りが求めているもの、その意味で(対戦相手は)オスプレイ一択でしたね。(ヒデオ・イタミ=KENTAとシングルで戦った)20周年記念大会とはまた違うものを見せなきゃいけないと思うと、彼しかいなかった。
(憧れと言われて)素直に嬉しかったですよ。僕も子供のころにプロレスを観て、憧れて、プロレスラーになった人間なので」
2023年9月17日、東京・後楽園ホールは超満員に膨れ上がった。入場したオスプレイのリングシューズには「NOAH」の文字が刻まれていた。この試合への意気込みが伝わってくるようでもあった。
試合は丸藤の逆水平チョップから始まった。
「あのとき、オスプレイに話しかけているんですよ。〝チョップが食らいたいのか〟と。〝そうか、分かった。じゃあ行くぞ〟と。普通、レスラーって言い合うことはよくあると思うんだけど、こういうような会話ってない。というか、それこそ試合中にそんな会話ができるレスラーがあまりいない。ただ技のやり合いをするだけじゃなく、そんなやり取りもあったから余計に楽しかった」

チョップの痛みを噛みしめた後、深く一礼するオスプレイ。そこから一気に動き出す。バックの取り合いからグラウンドでの攻防……体を合わせての会話が始まる。タックルを受けてひょいと起き上がるオスプレイのムーブは、まさに丸藤のもの。丸藤がフックキックを見せれば、同じようにオスプレイも。憧れがどれほど強いものか、観ていればそれはよく理解できた。
天才同士の掛け合いはまさにジャズのセッションのよう。丸藤十八番のフロムコーナートゥーコーナー(トップロープの反動を使った遠距離からのドロップキック)を先に繰り出されてしまえば、フックキック、エプロンサイドでの不知火からフロムコーナートゥーコーナーをやり返していく。

ひと回り年下のオスプレイに対して、昔のようにスピーディーに、ノンストップに畳みかけていくことはできない。それでも間を使い、呼吸を整えながら、現代の天才とも噛み合わせていくのだからさすがである。思わぬタイミングで技を繰り出す感覚は、経験を積んできた今だからこその味がある。
「最初から分かっている状態でやろうとしたって面白くないじゃないですか。見えないところから分からないタイミングでやるようにすればお客さんも驚いてくれる。単純な技に、一つひとつスパイスを加えるだけでお客さんが感情を出せるシチュエーションをつくっていけますから。

20代、30代でやっていたプロレスとはどんどん形を変えてやってきている。昔の貯金もありつつ、今できることを試行錯誤しながら今の自分のプロレス像をつくってきた。オスプレイとの試合も昔ならもっと人々の心に残るようなプロレスができたかもしれないけど、逆に言えば今のようなプロレスを昔はできなかったと思うんです」
スピードに乗る展開になれば加速していく。一方で重みを出す展開になればエルボー合戦、逆水平合戦とそちらに重心を傾けていく。パートごとに見せ場をつくり上げていく様はジャズでもあるが、どこか映画のようでもある。


「それはあるかもしれません。映画、舞台、テレビドラマはよく観るようにしています。恋愛ものなら、お客さんにどう感情移入してもらえるか、ホラーものなら、お客さんをどう驚かせるか。技は自分で淘汰されて今の状態で落ち着いていますけど、(展開など)技以外のところでは、映画、舞台、テレビドラマから得られるものって案外、多いんです」
2人の濃密なストーリーも終盤に入っていく。
切り返しの連続、大技の連続。息をのむ技の応酬から、丸藤はしばらく封印していたタイガー・フロウジョンまで繰り出す。流れが丸藤に傾くやと思いきや、ここでオスプレイもギアを上げていく。最後はヒドゥンブレイド、ストームブレーカーと仕留めに掛かり、23分の激闘に決着をつけた。
大の字になって動けない丸藤に対し、オスプレイは手を握って起こし、労うように肩をポンポンと叩いた。

ファンの拍手と歓声が、試合の満足度を物語っていた。
天才同士の邂逅は、期待を裏切らなかった。マイクを握った丸藤は、花道を引きあげるオスプレイに「大きな拍手をお願いします」と送り出して呼吸を整えた後、集まったファンに向けて決意を口にした――。