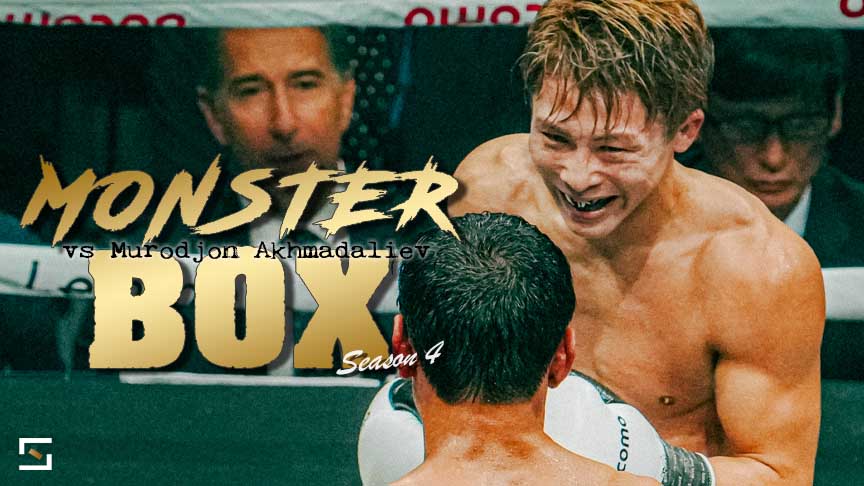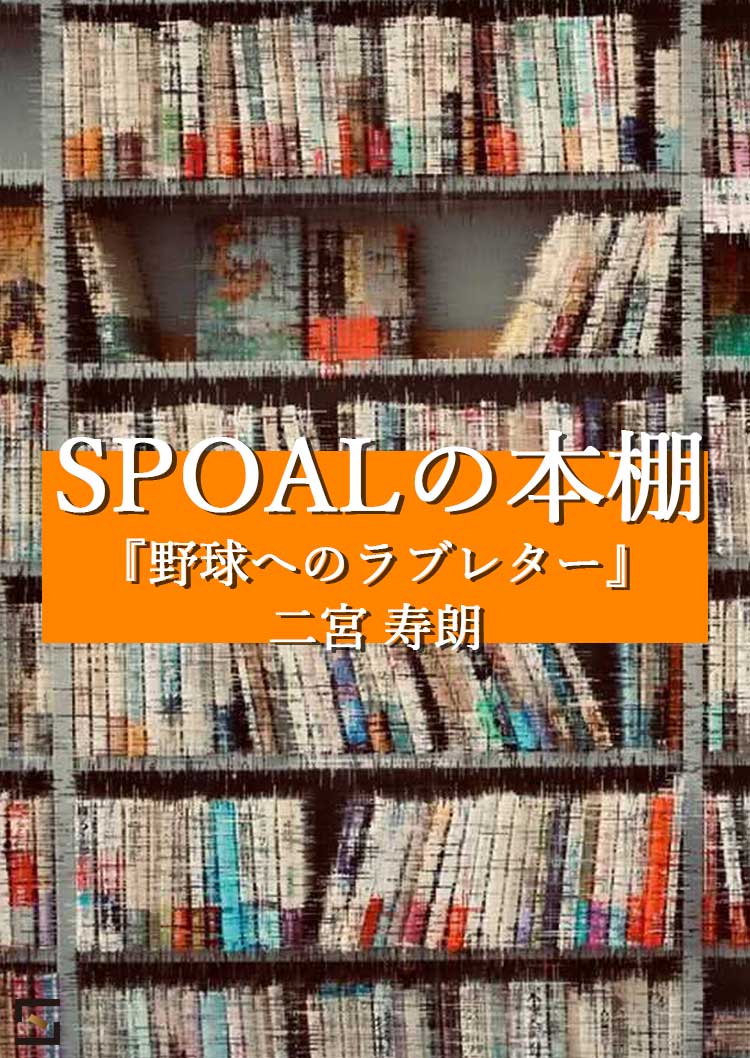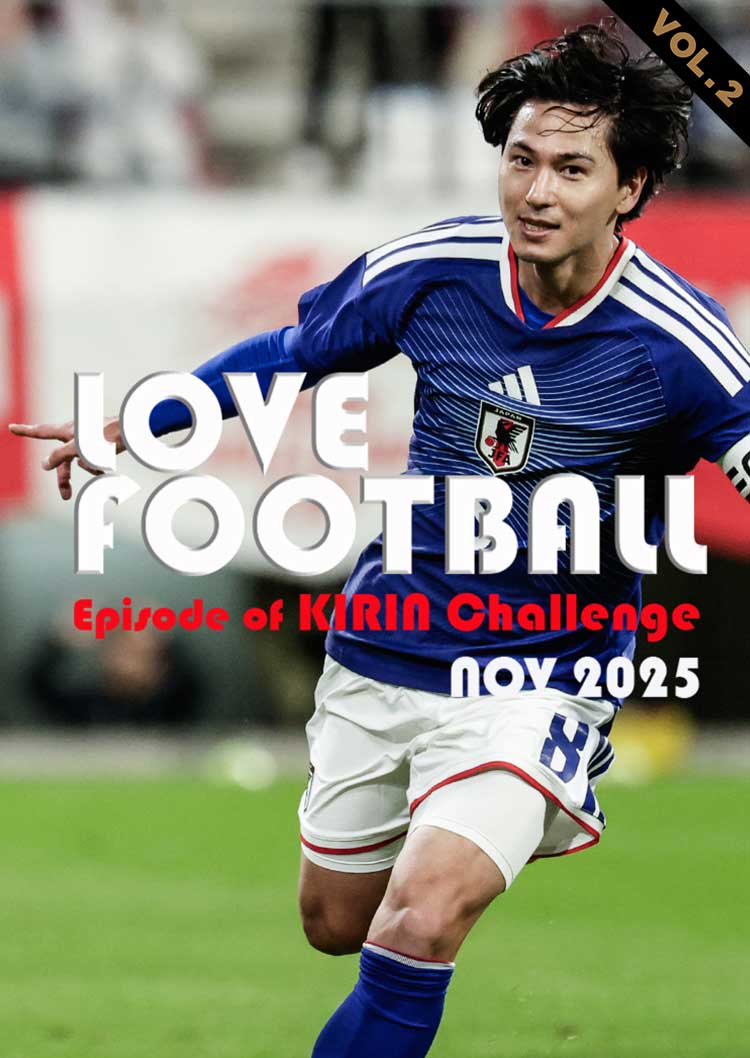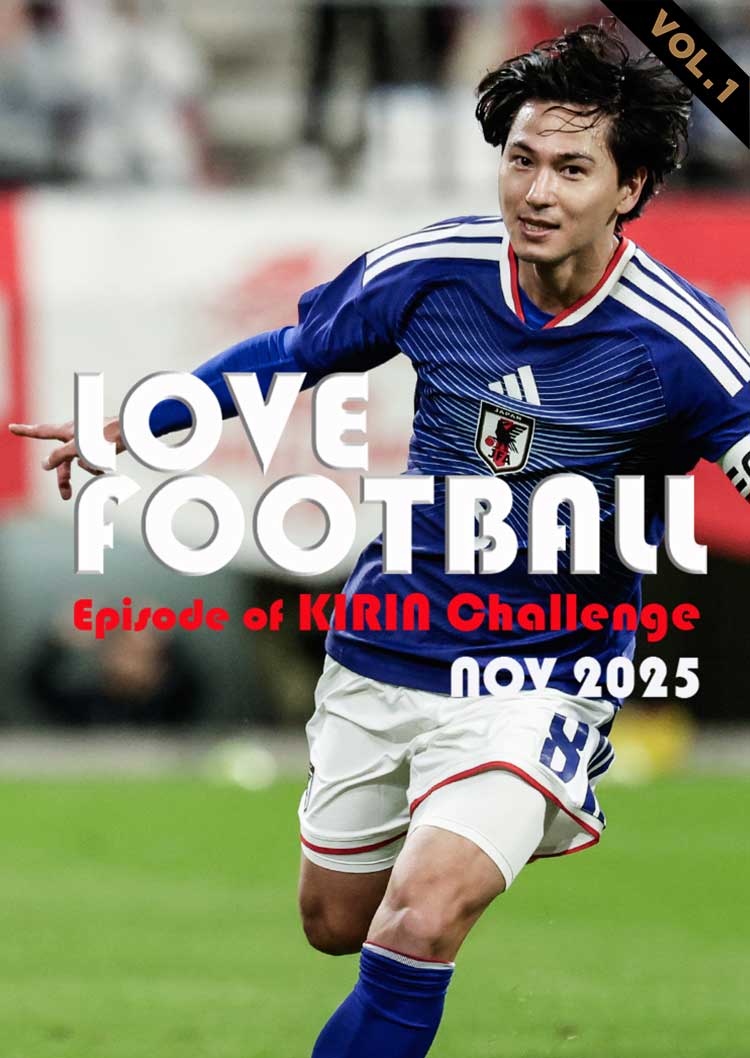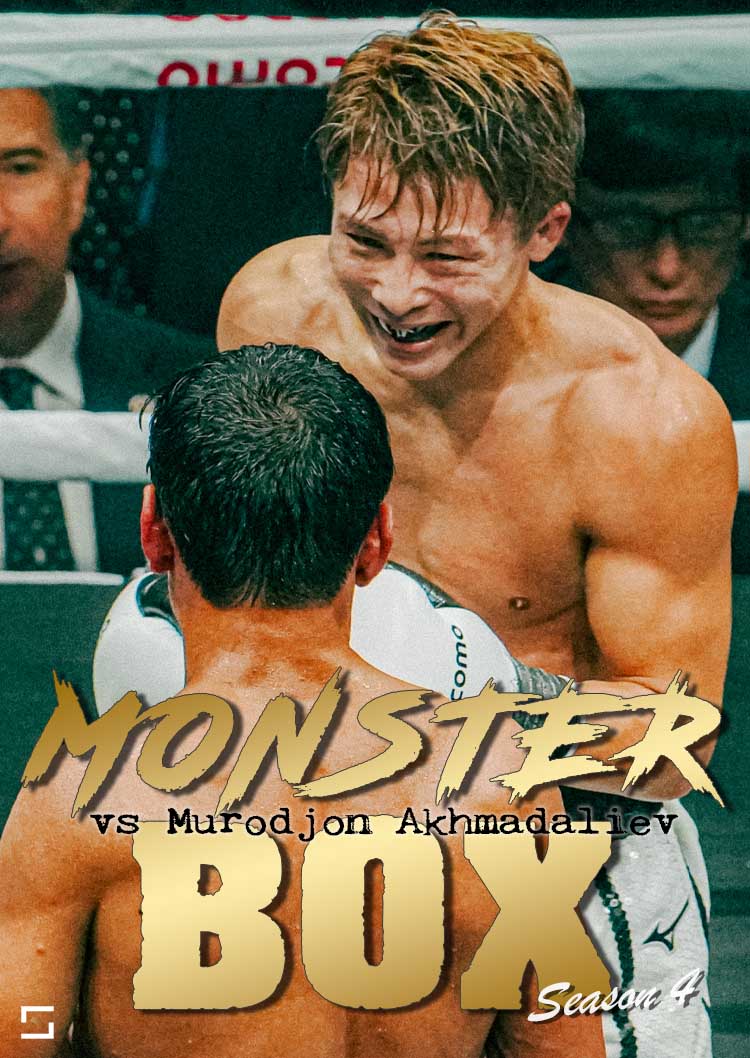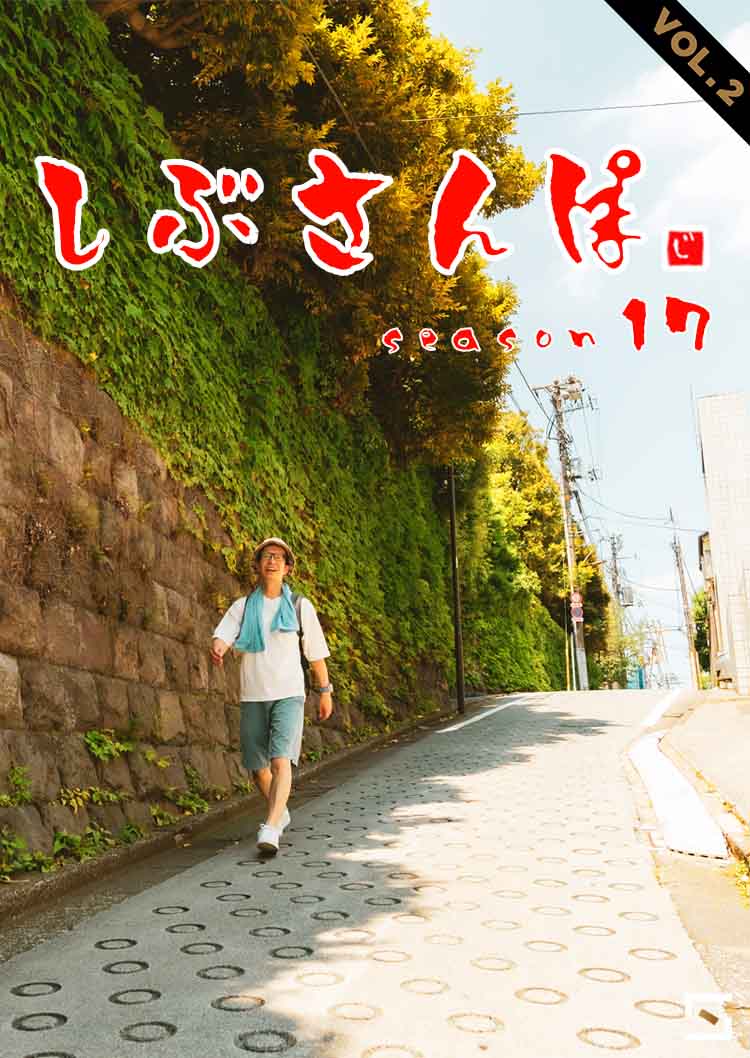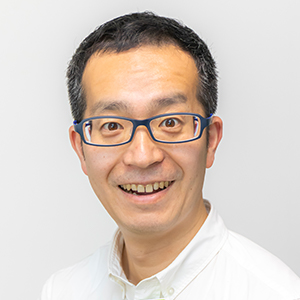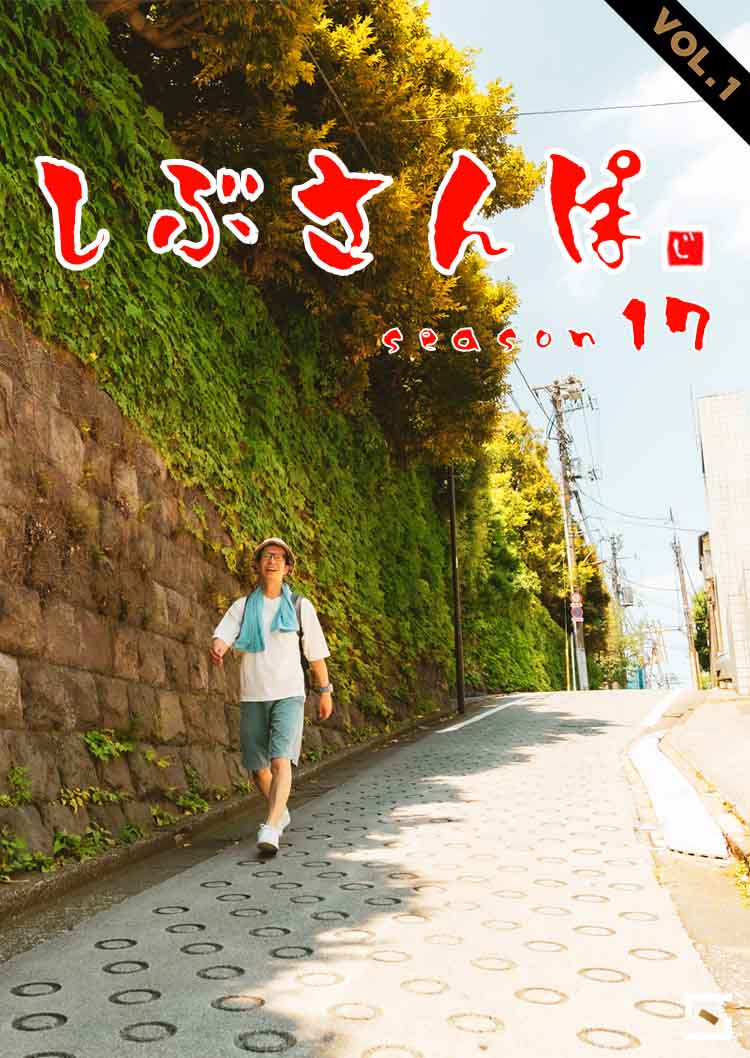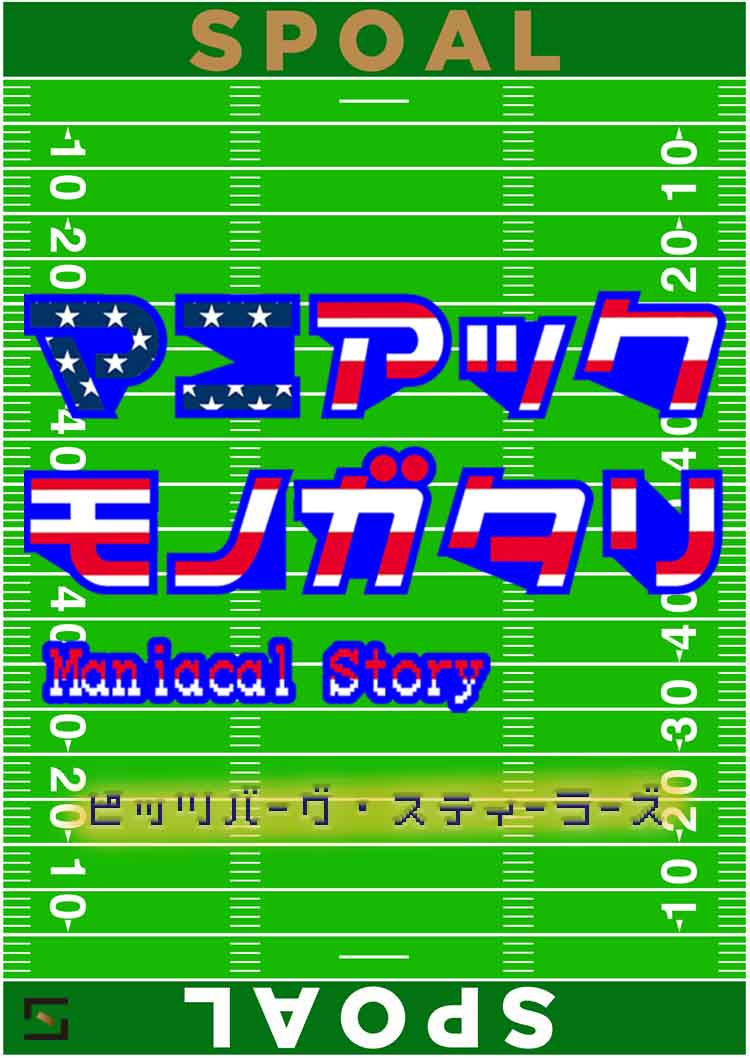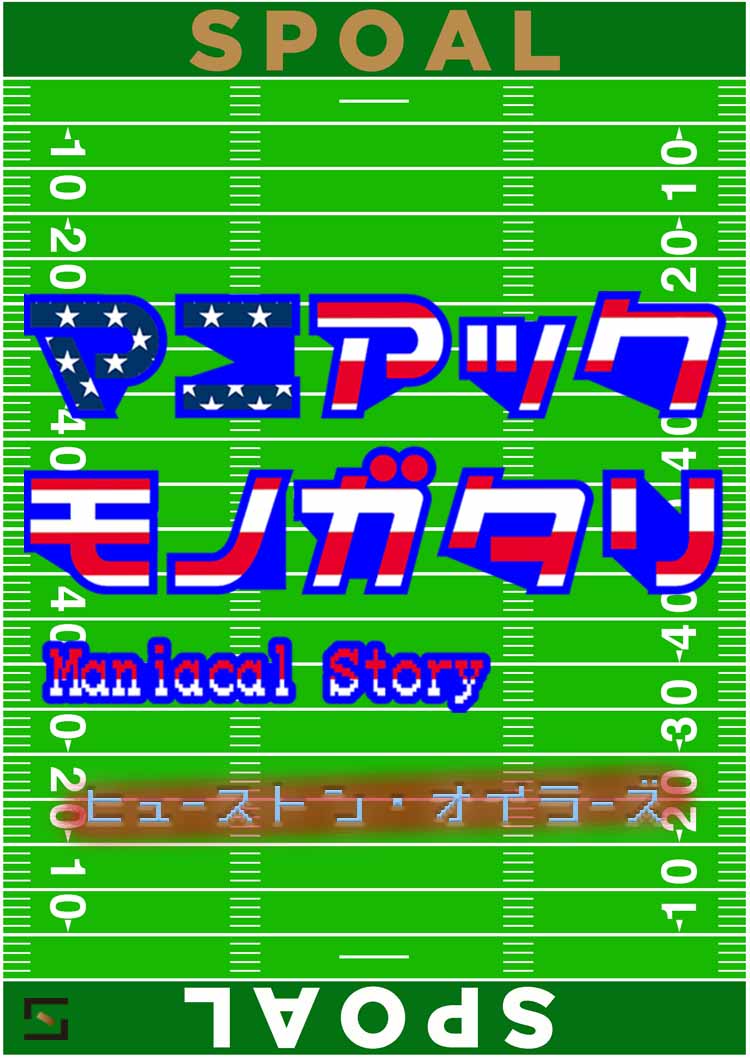スポーツファンの一人として毎回、欠かさずチェックしているテレビ番組がいくつかある。その一つが、NHK BS1の「レジェンドの目撃者」だ。プロ野球のレジェンドたちにスポットライトを当てて、選手、関係者からのいくつもの証言によって実像やプレーのこだわりを浮かび上がらせていくという内容。レジェンドをゲストに招き、それらの証言をもとにしたトークも最高である。確かSPOALの立ち上げ時に近い2019年12月ごろにスタートした番組だと記憶している。「盗塁王 福本豊」「ケンカ投法 東尾修」編は知らないエピソードや本人たちの軽妙洒脱なトークもあって録画したものを再度見た。どの回も素晴らしのだが、特にこの2つは僕にとっての「神回」だった。
そしてまた「神回」に出会ってしまった。
10月に放送された「攻守のスペシャリスト 篠塚和典」編は、翌日にまた観てしまったほど。もちろん少年時代、大好きな選手であった。小学生のころは愛媛で希少な横浜大洋ホエールズファン。とはいえ野球中継は巨人しかやっていないのだから選択肢はない。地元出身のショート河埜和正を応援していたが、次第にセカンドの選手に関心が移っていった。
それが篠塚である。名前が「トシオ(利夫)」で同じということもあって(のちに和典に改名)勝手に親近感を覚えたものだ。好きだったのは守備。柔らかい身のこなしとグラブさばきは、子供ながらに美しく感じた。
私は小4で地元の少年団でソフトボールを始め、ほぼ守備にしか興味がなかった。打つ練習よりノックを受ける練習のほうが断然テンションは上がった。からっきり打てなかったが、時折試合に出させてもらう場合は大体セカンドかショート。ゴロを捕るのがとにかく好きで、逆シングルもいけるようになった。篠塚先生を真似たグラブトスに失敗して、怒られたこともある。少年時代の記憶がふとよみがえってくる。
この番組を観て、篠塚のグラブが人よりも小さいものを使っていたことを知った。人差し指の付け根部分だけが黒ずんていたそうで、その一点で捕るようにしていたという。捕球の際に「ボールの軌道を邪魔しない」という表現もカッコよかった。
近藤俊哉さんの作品より。こうやってキャッチボールを眺めるだけで、何だか心が落ち着くのは私だけでしょうか?
篠塚のドラフト1位指名にこだわったのが当時監督の長嶋茂雄であった。〝ミスター〟の期待に応えるために努力し、結果を残し、そしてレジェンドとなっていくという物語。1994年、日本シリーズを制して初めて「日本一」となった長嶋監督を胴上げして、現役引退したことからもミスターへの思いがヒシヒシと伝わってくる。
アラフィフの私にとって「長嶋茂雄」はあくまで監督のイメージで、選手時代は知らない。ただ、天覧試合のサヨナラホームランや、サードの華麗な守備の映像を見て、もの凄いスーパースターだということは理解できた。大人たちが言う「長嶋には華がある」という言葉にも納得できた。
華=魅せる。
「月刊ジャイアンツ」の連載をまとめ、加筆・修正・再構成されて2010年に出版されたのが「野球へのラブレター」(文春新書)である。野球のあらゆるテーマに目を向けた長嶋茂雄の野球談議で、ミスターの野球愛が伝わってくる一冊になっている。
私のお気に入りは守備に関する一節だ。ミスターは「打、走、守では守備が一番好きだった」と本書で語っている。以下、抜粋させていただく。
「長嶋と言うと先ず打撃をファンは思い浮かべるのだろうが、打撃は瞬間の運動で〝遊び〟ができにくい。守備は、考え工夫した事を動きとして表現しやすい。これを〝遊び〟というのだが、だから楽しかった」
ただ単に派手なプレーだけが「魅せる」の定義ではない。
篠塚は攻守において確実性をプレーのベースに置いたが、難しいことを簡単にやってのける技量はその範疇に入る。一点でさばくグラブさばきは、篠塚にとって考え、工夫した〝遊び〟の要素もあったに違いない。長嶋の教えを、彼なりに解釈しつつ表現していた。
北海道日本ハムファイターズの新監督に就任したビッグボスこと新庄剛志はまさに〝魅せる〟を体現してきた野球人。もう一度、「魅せる」とは何かをプロ野球界全体として考えていくときなのかもしれない。「野球へのラブレター」には、そのヒントが散りばめられている。
(終わり)
2021年11月公開