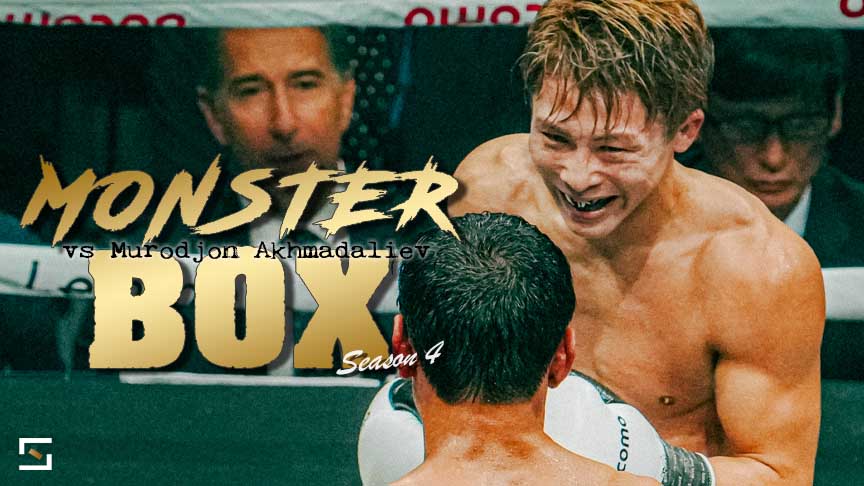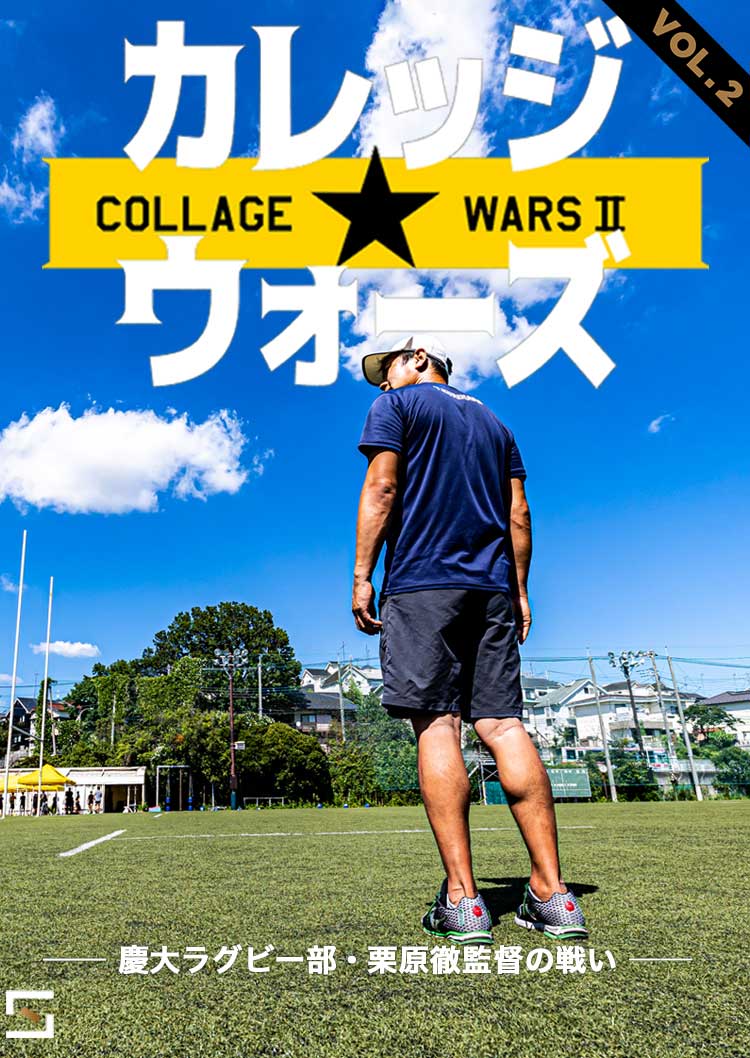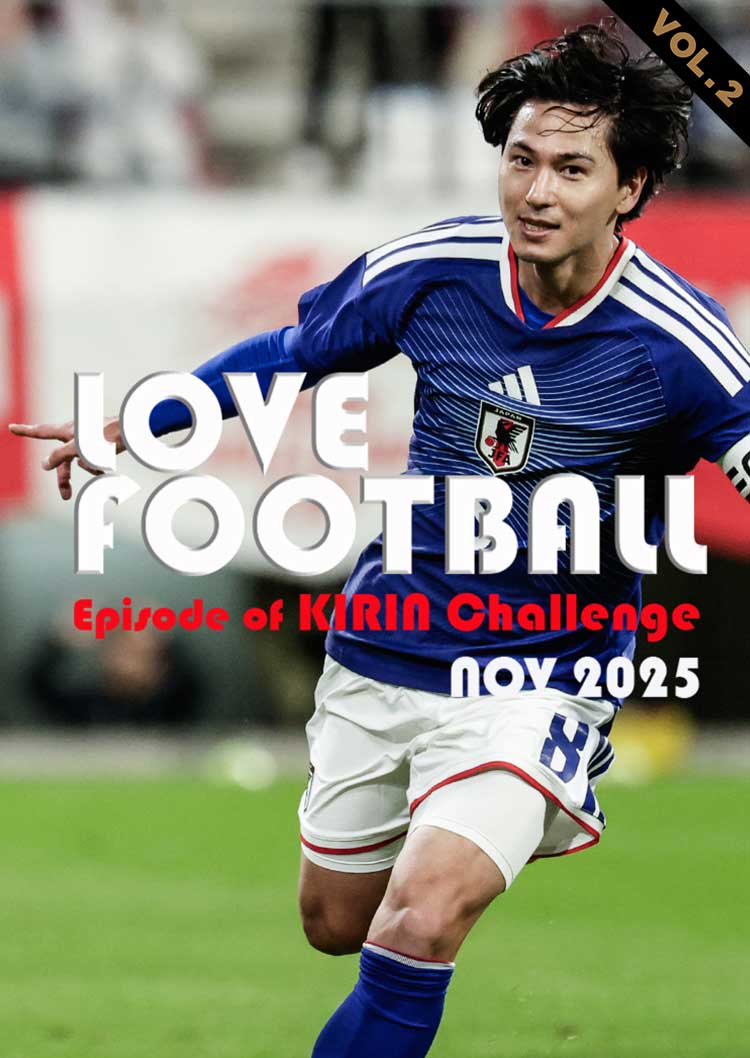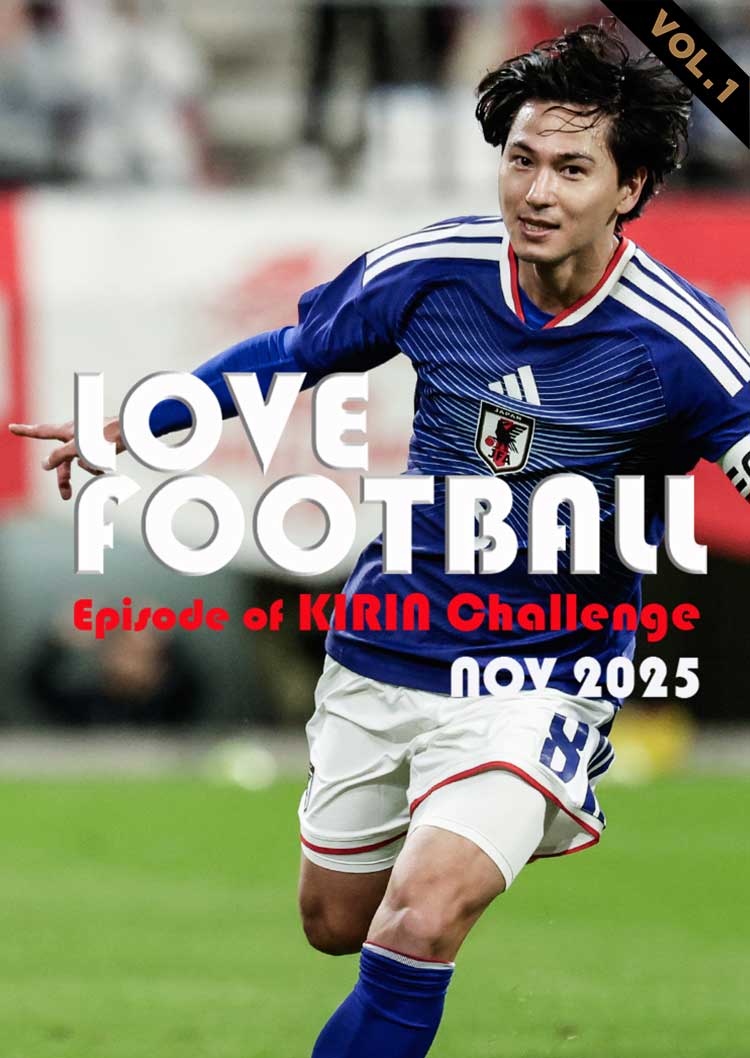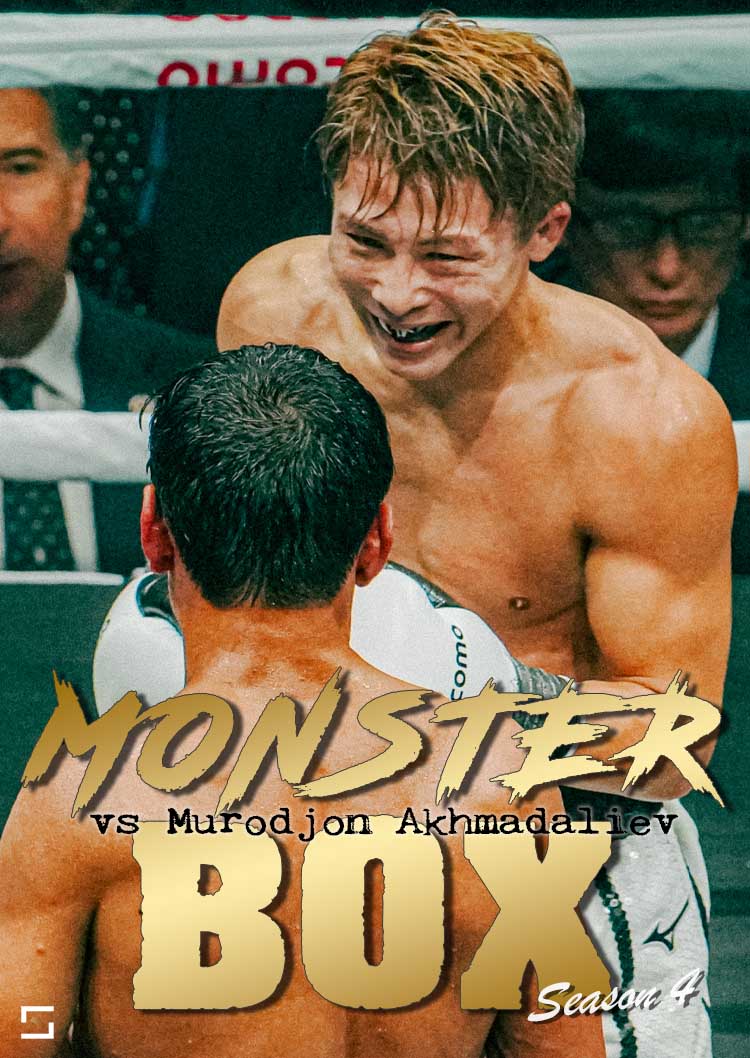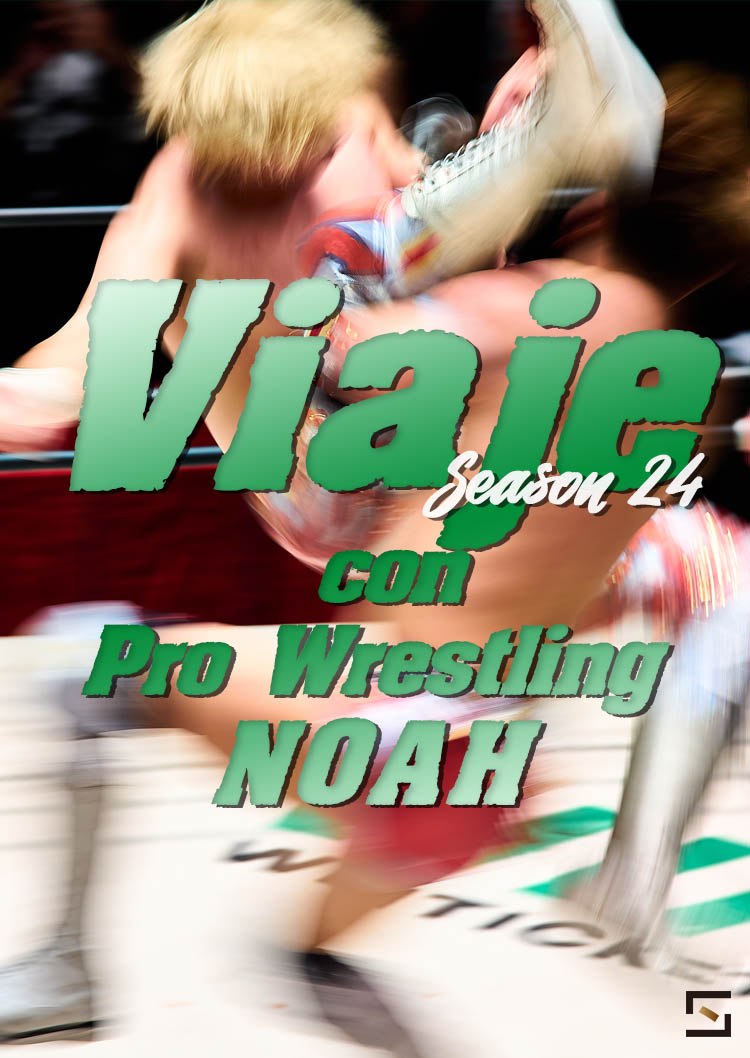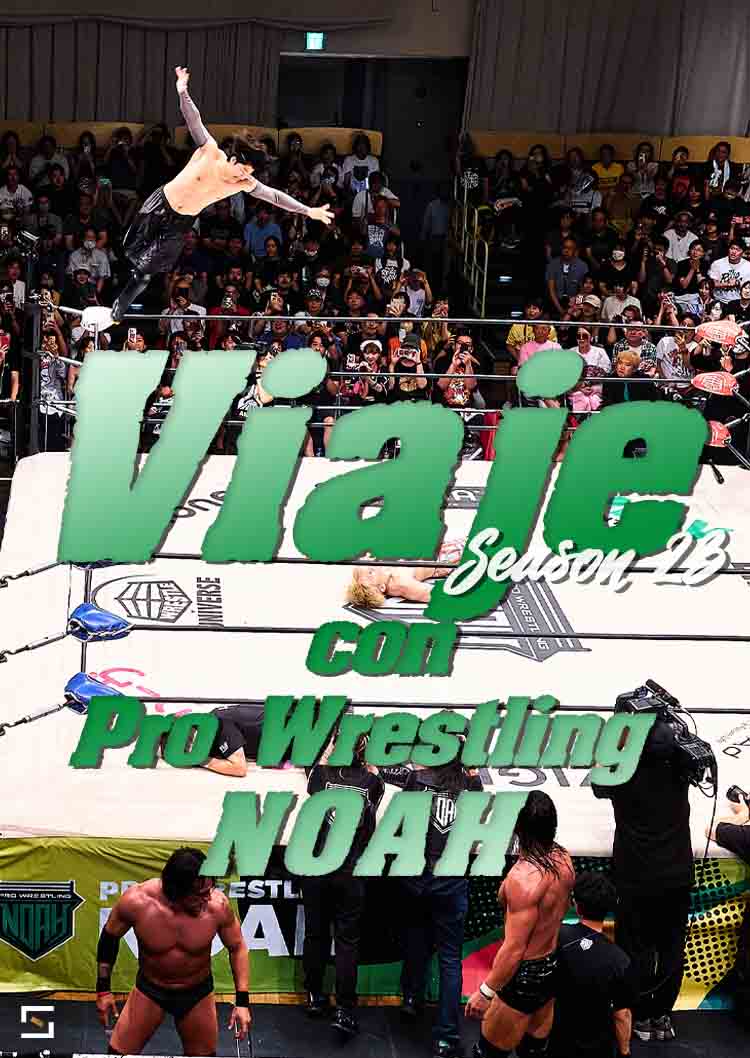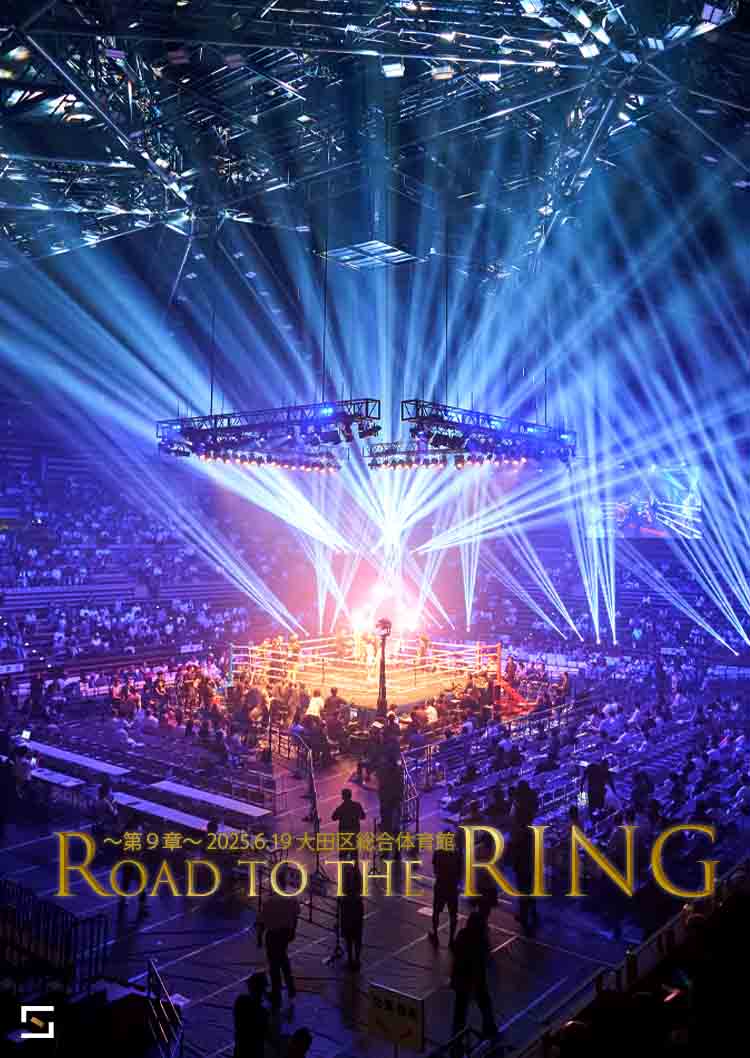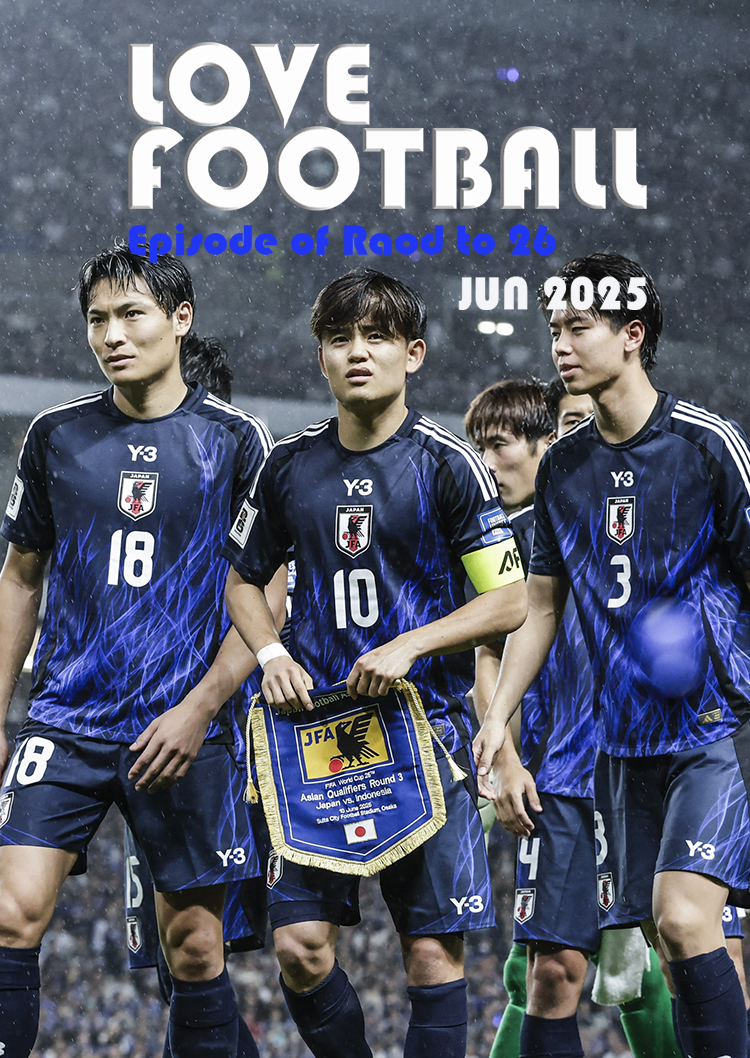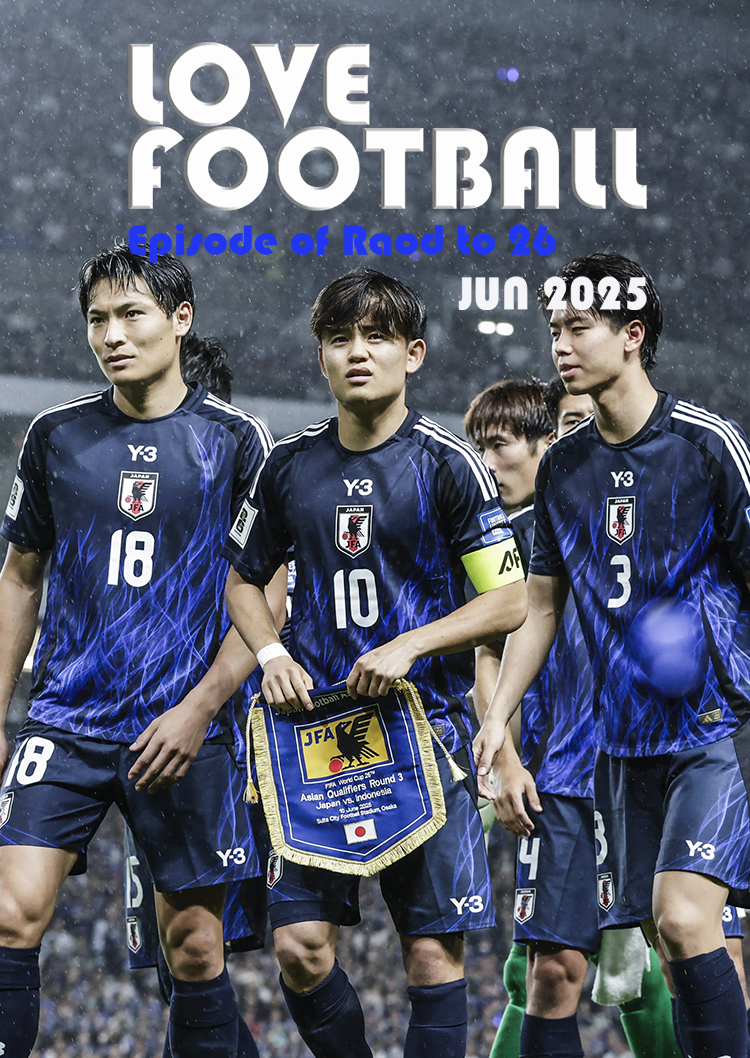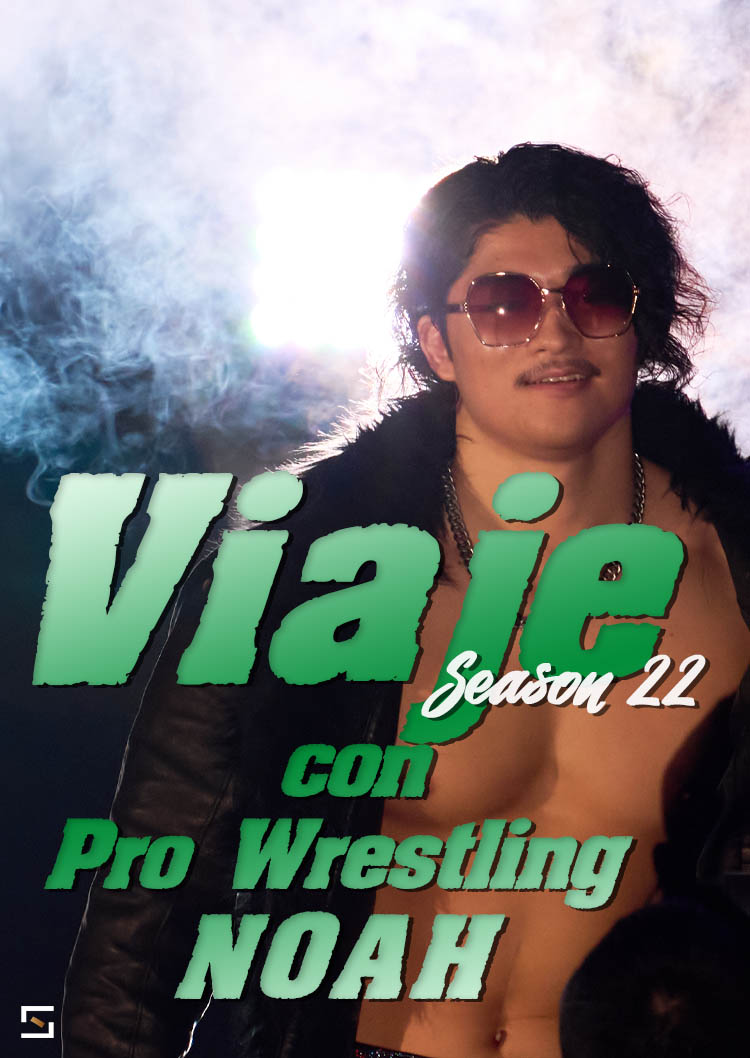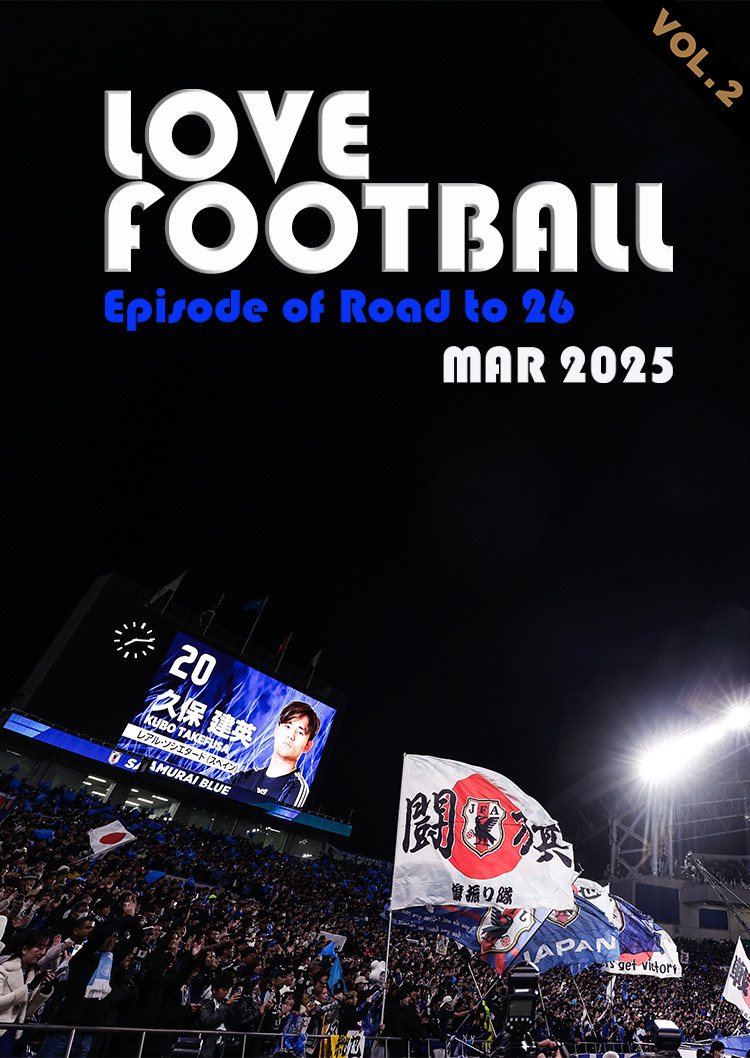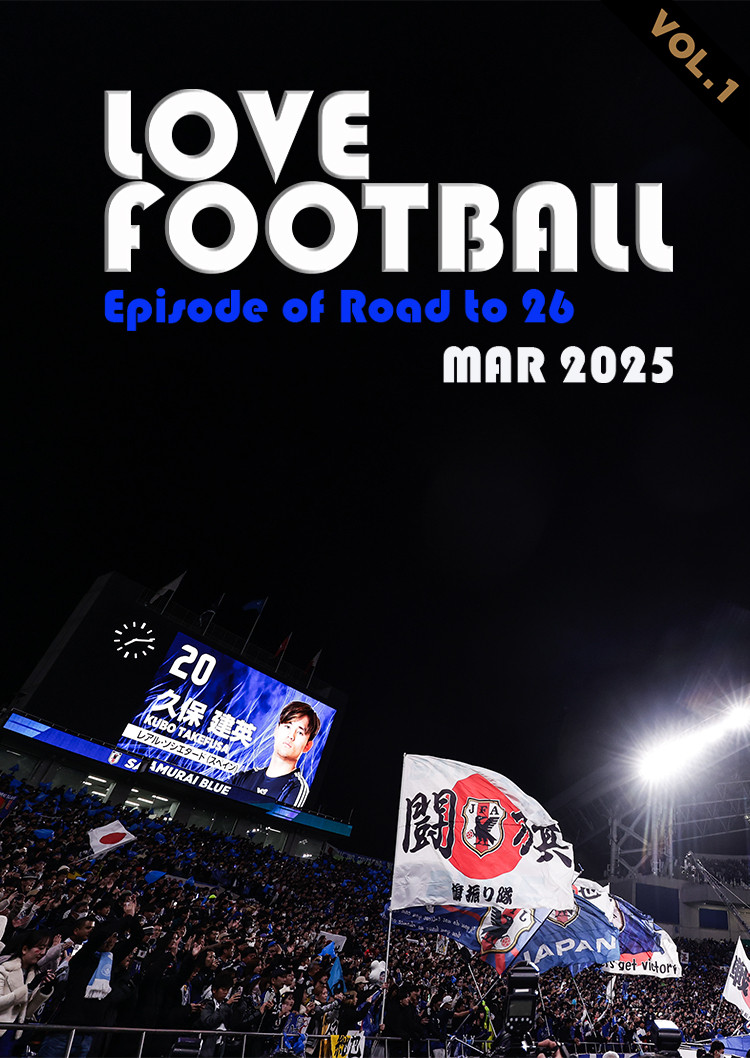試合の結果によって、チームにどうアプローチしていくか。
2020年シーズン、慶応大学ラグビー部で指揮を執って2年目となる栗原徹監督が参考にしたのは、2014年にNTTコミュニケーションズ・シャイニングアークスのスキルコーチに就任して出会ったロブ・ペニーHC(ヘッドコーチ)であった。
「シャイニングアークスを甦らせて開幕戦(宗像サニックス戦)に勝って、次に東芝(ブレイブルーパス)に接戦の末に敗れて。そういうときにロブはどうするのかなと思って見ていたら、観客と同じように拍手をして迎え入れたんです。〝グレートボーイズ、東芝相手に良く頑張った。誇りに思う〟と。その一言で、チームは勇気をもらったし、来週勝てるって思えたんです。そういう意味では負けた後の言葉が大切なんだなって感じました。選手から離れたロブの顔を見たら、メッチャ怒っていましたけど(笑)」
勝とうが負けようが、試合は続いていく。
取り組んでいることを継続させてこそ、それが成果となっていく。名将と称されるロブ・ペニーのマネジメントを間近で見ることができたのは栗原にとって幸運だった。

大学選手権に出場できなかった2019年シーズンを終えると、すぐに新チームを始動させた。意図的にきついトレーニングを課していく。
栗原は語る。
「どのスポーツでもそうですけど、最後の最後、心身ともにきつい状況になるなかで、それでも体を動かしていかなくちゃいけない。トレーニングではここに目を向けて、厳しく、細かく声を掛けていきました。〝今あきらめていないか〟〝ここで頑張れるかどうかで変わるんだぞ〟とか。学生がついてきてくれて、かなりタフになりました。前年(大学選手権に)行けなかった悔しさもあったとは思うんです。明治にしても、帝京にしても、実力からしたら格上の相手。10回戦って、1、2回の勝ちを拾えるかどうかというのが僕の認識でした。だから明治に勝とうとか一言も口にしていない。とにかくチャレンジしよう、目の前のことをしっかりやろう、とだけ言ってきました」
いずれも後半ロスタイムに勝利を決めた劇的な勝利。粘り強く勝利を引き寄せたのは、突き刺すようなタイガー軍団伝統の「魂のタックル」であった。
苦しいときの〝もうひと踏ん張り〟を課してきたことが大きかった。ただここは伝統の力だと栗原は解釈している。
「タックルというのはDNAとして染み込んでいますから。そこは何も言わなくても、タックル、ディフェンスにプライドを持っている部員が多い。求心力が(タックルに)あるから、コーチングしやすいところがあるんです。普通みんなアタックが好きなはずなんですけど、ディフェンスをやらせてくれっていう声がここでは多いので。ただこれは僕が就任する前から。歴代の指導者が植えつけてくれたこと。自分としてもここは大事にしてきたいと思っていました」
選手の自主性を引き出していくために、教えすぎないことを意識している。
シャイニングアークスで5年にわたってスキルコーチを担ってきた経験を活かして、応用重視で教え込むこともできる。だが、敢えて広げようとはしない。「学生にやらせる」が主になってしまうからだ。学生が能動的かつ自主的に取り組んでいかなければ、一人の人間としても育っていかない。

ベーシックなことを、とことん追求する。
栗原は言う。
「シンプルでいいと思っています。たとえばアタックはボールキャリーとサポート。オプションには、ずらす、もぐる、飛ばすがあって、ボールキャリーで勝ったらKBA(キープボールアライブ)だぞ、と。部員もここはすぐに答えられるだろうし、頭のなかがクリアになっていると思います。そこからのオプションをどう選択していくかは、彼らの自由。野球のピッチャーに置き換えるとストレート、カーブ、シュートといくつか球種を教えておいて、初球はカーブから入って相手の打ち気をそらしてから次に内角をストレートでえぐって、最後は外で落とすみたいなセオリーを教えはしますけど、決めるのはあなたたちだよ、と。最初にストレートで入ったって全然構わない。ベーシックなことがクリアになっていれば、あとはどう使っていくかだけなので」
サインプレーも選手たちに決めさせている。指導者側がいくらいいサインプレーを提案しようとも、「受け身」では意味がないと考えるからだ。
「コーチたちは本当によく勉強してくれていて、海外のラグビーを参考にして〝このサインプレーを試してもいいんじゃないか〟って学生側に提案してくれたことがあるんです。でも学生の半分くらいは、(コーチに)任せっきりみたいなところがあってうまく身につかなかった。だったら、あまりいいサインプレーじゃなくても学生主導で〝これやってみたい〟と思ったものをやるほうがいいかなと感じたんです」
チームにアタックリーダー、ディフェンスリーダーなど学生のなかに「リーダー」を置いて、話し合いをさせている。そのうえで「スーパーラグビーでこういうサインプレーをやっていて、採用してみてはどうかという話になりました」と報告が上がってくれば、基本的にはOKを出すようにしている。リーダーは4年生ばかりではない。下の学年も積極的に話し合いに参加させるためである。

学生主導で能動的にやるからこそ、チームがタフになる。大事な局面で粘りが出る、泥臭さが生まれる。明治戦、帝京戦でもそれは証明された。
栗原は言葉を続ける。
「スクラムやラインアウトモールで押し切るために大事なのは、結局、強いかどうかじゃない。しんどいことをずっとやっていくと、低い姿勢が保てなくなって、ああでもない、こうでもないっていう声が出てくる。でもリーダーが一言、〝ケツ落とせ〟と言えば、それでいい。トレーニングのなかできつい状況でもケツを落として押し切れていたら、試合でもできるようになる」
みんなで決めたことなら、言い訳もできない。
みんなでやっているなら、自分もやんなきゃいけない。
キャプテンを務めるLO相部開哉が、その先導役となった。
「相部があきらめることを僕は見たことがない。ダメになる前にあきらめる学生も少なくないなかで、彼は絶対にあきらめないんです」
キャプテン発信で、あきらめないチームになった。監督発信なら、それは不十分だったかもしれない。
2年ぶりの大学選手権では京産大に47―14と快勝して準々決勝に進出。しかし前年度王者の早稲田大学に14―19で敗れて、準決勝には進めなかった。
とはいえ、前年度から積み上げてきたものを成果として感じ取ることはできた。
継続は力なり--。
12月19日でシーズンは終わった。
やった分だけ、血となり肉となる。
1日だけのオフを経て、次の2021年シーズンに向けてトレーニングが始まった。
2021年8月公開