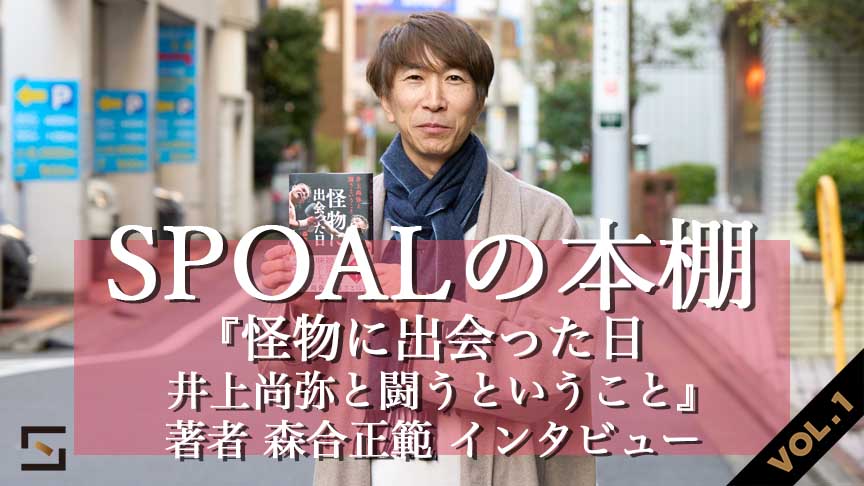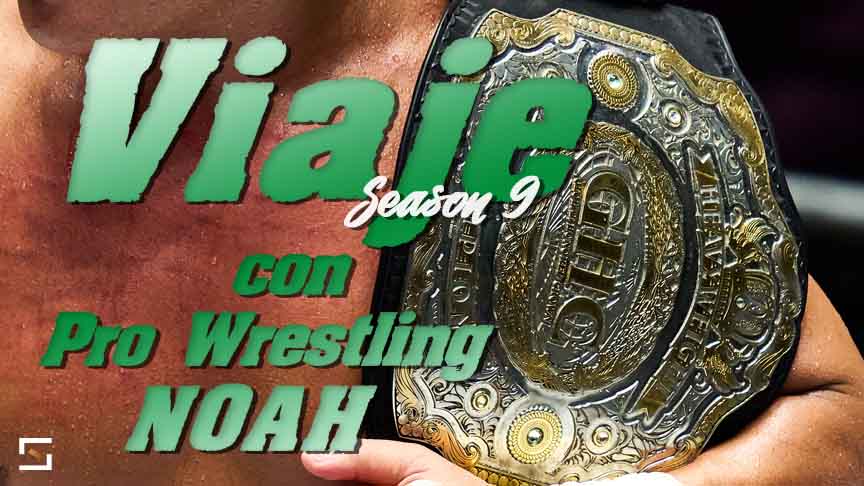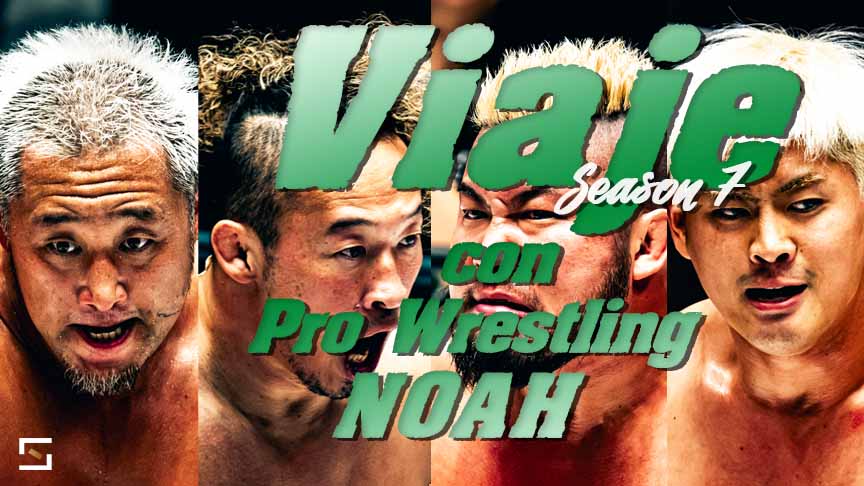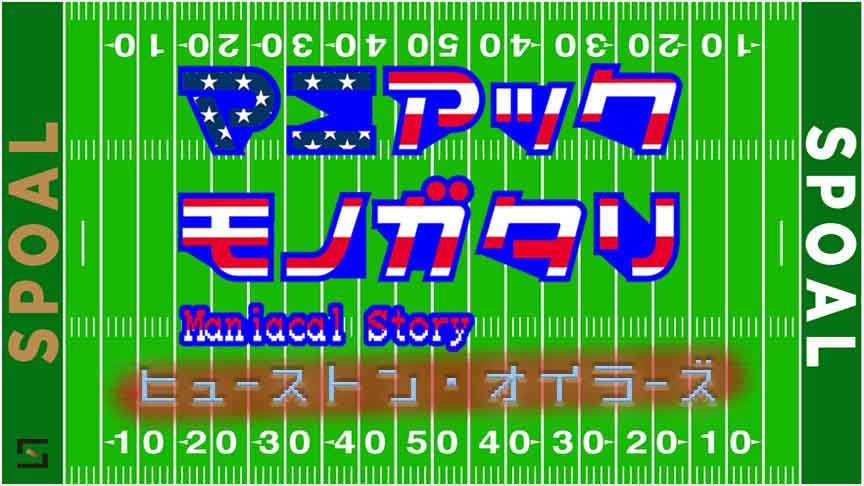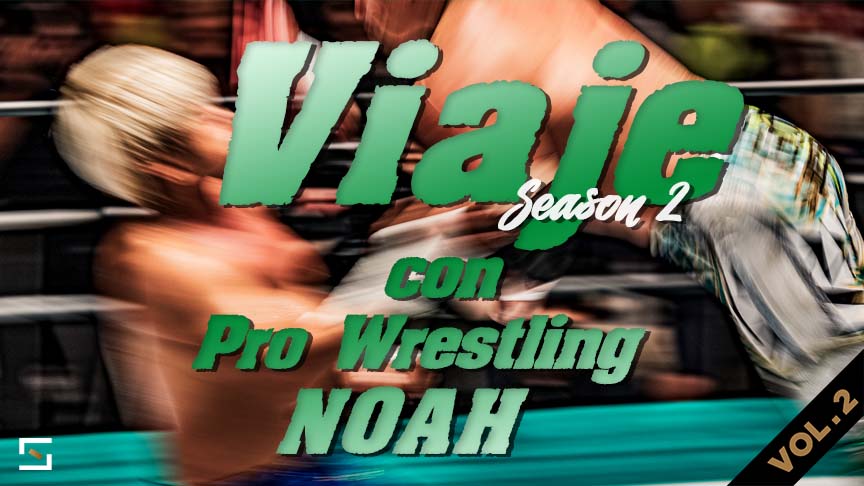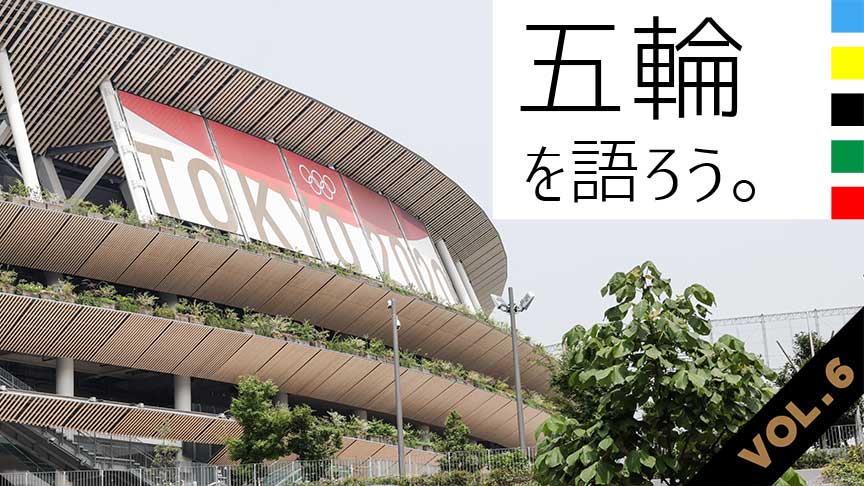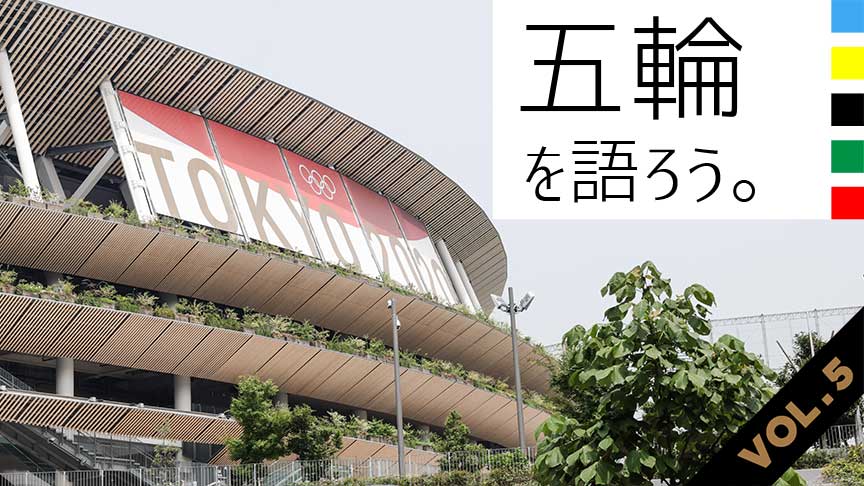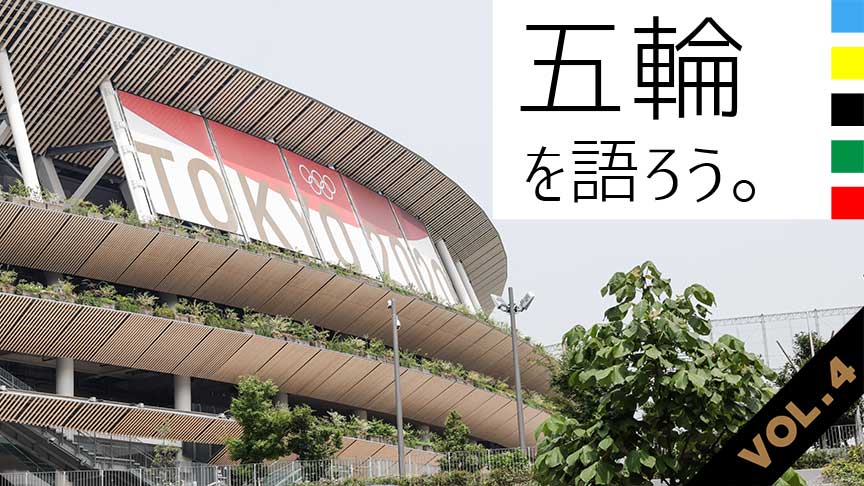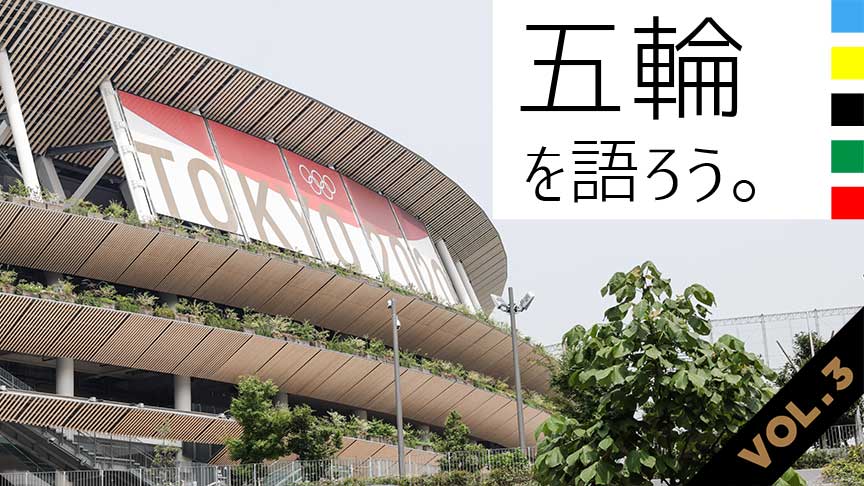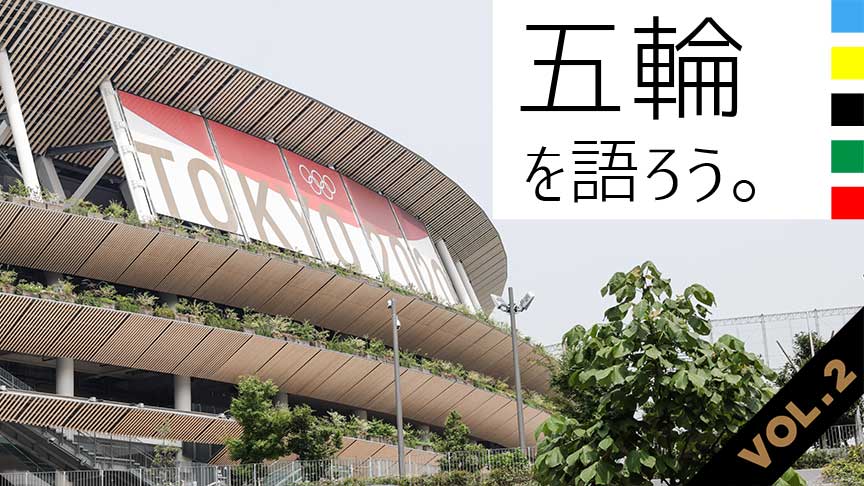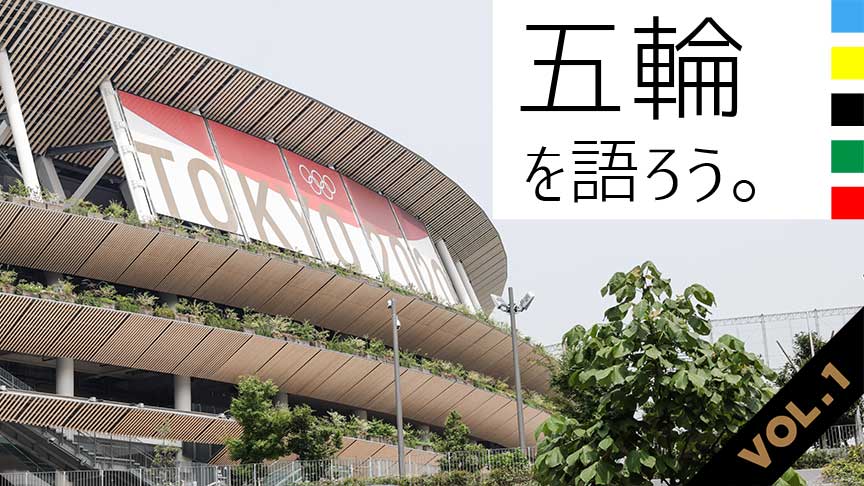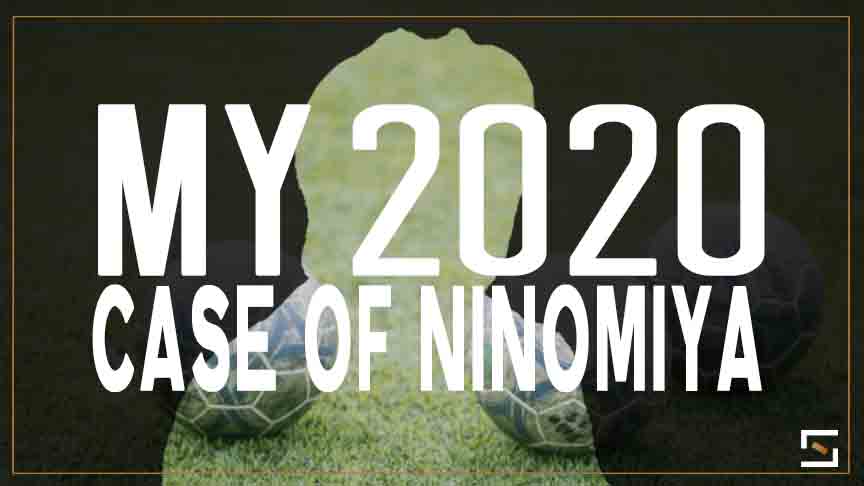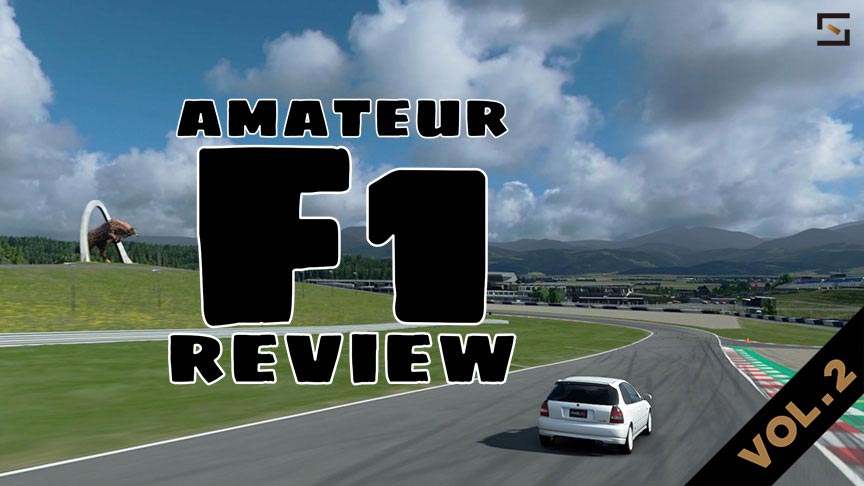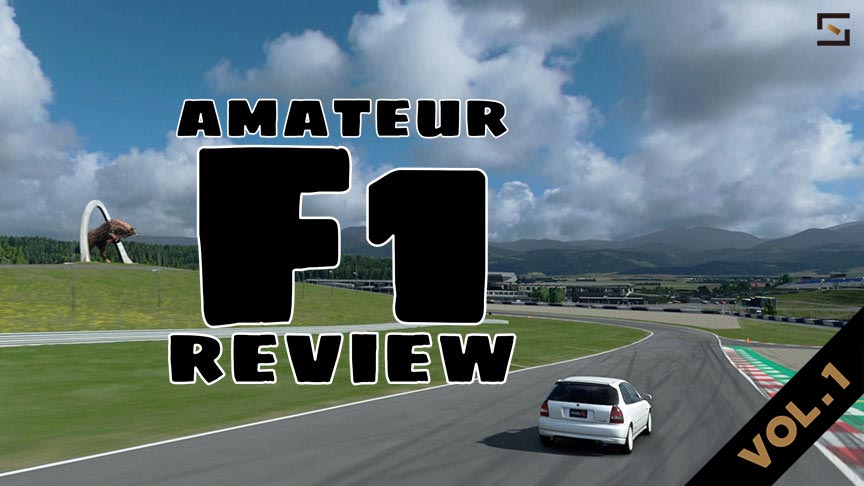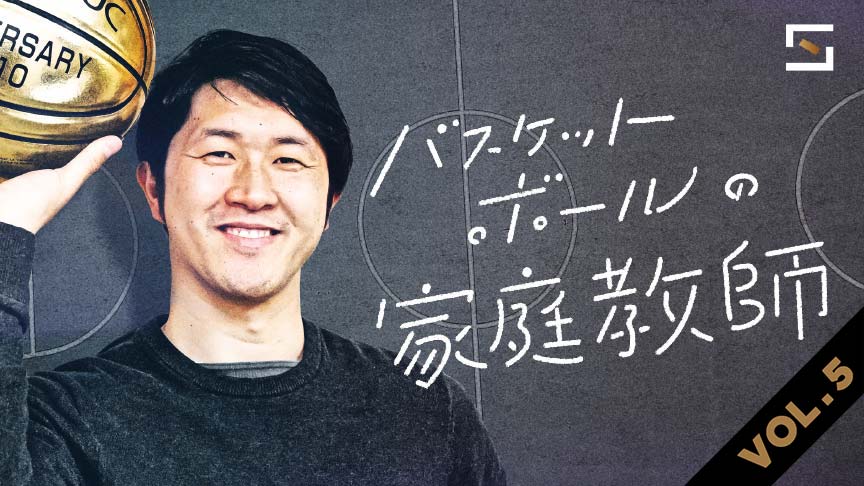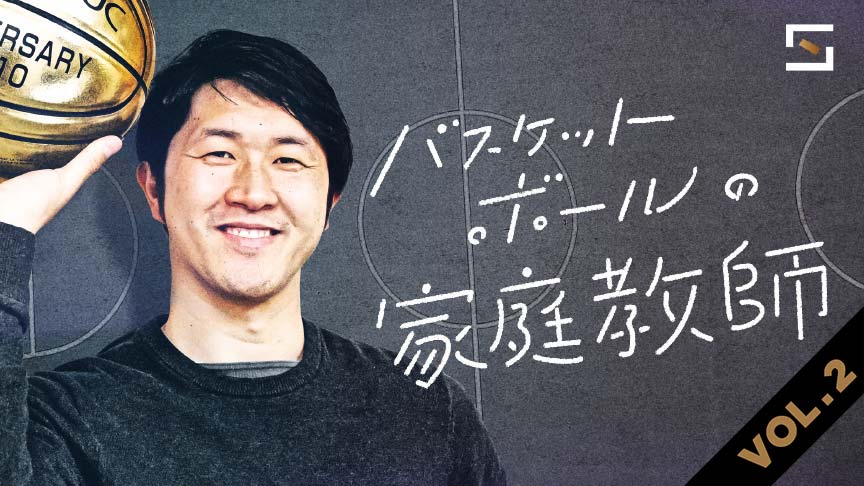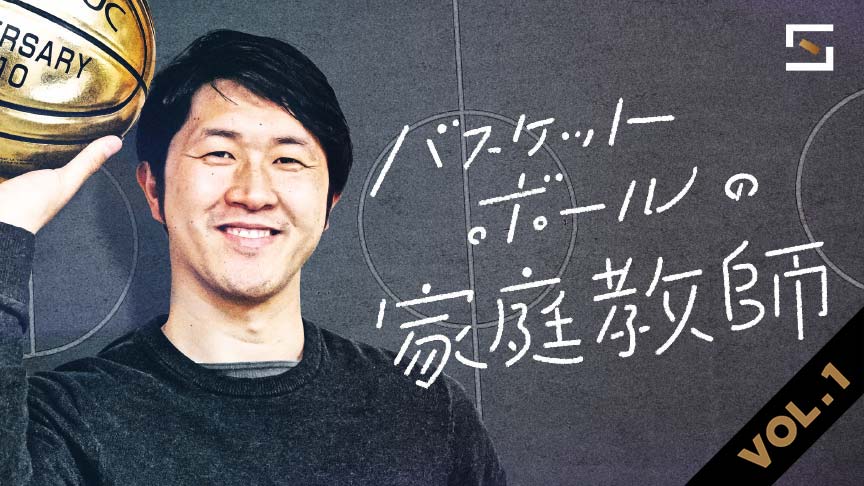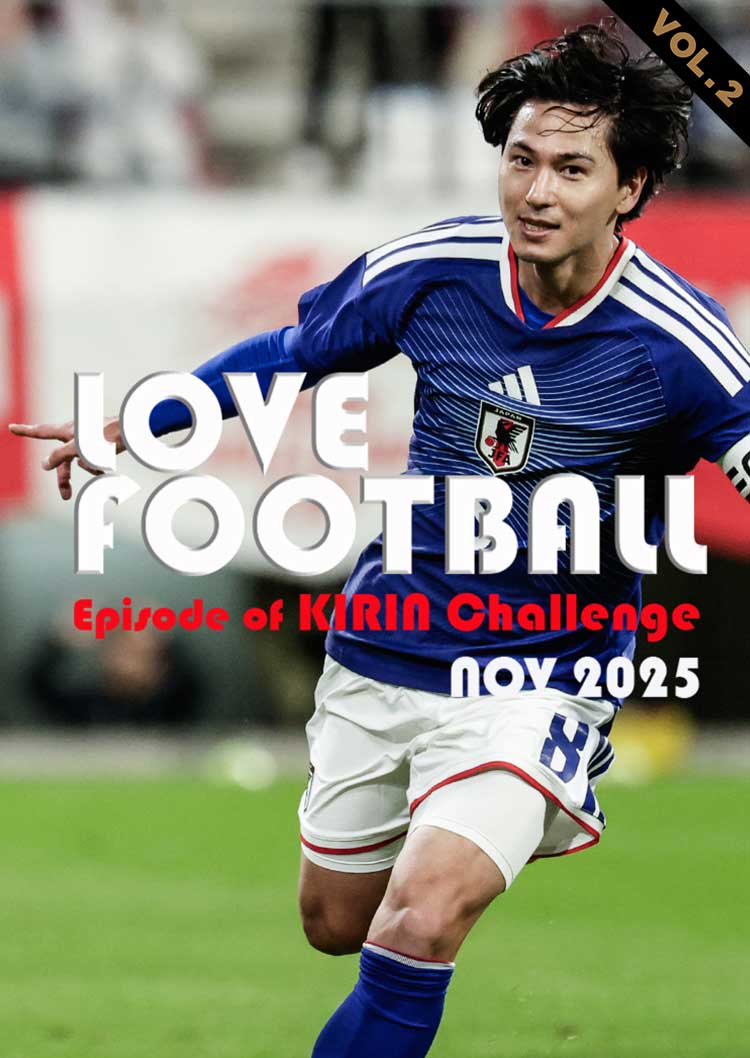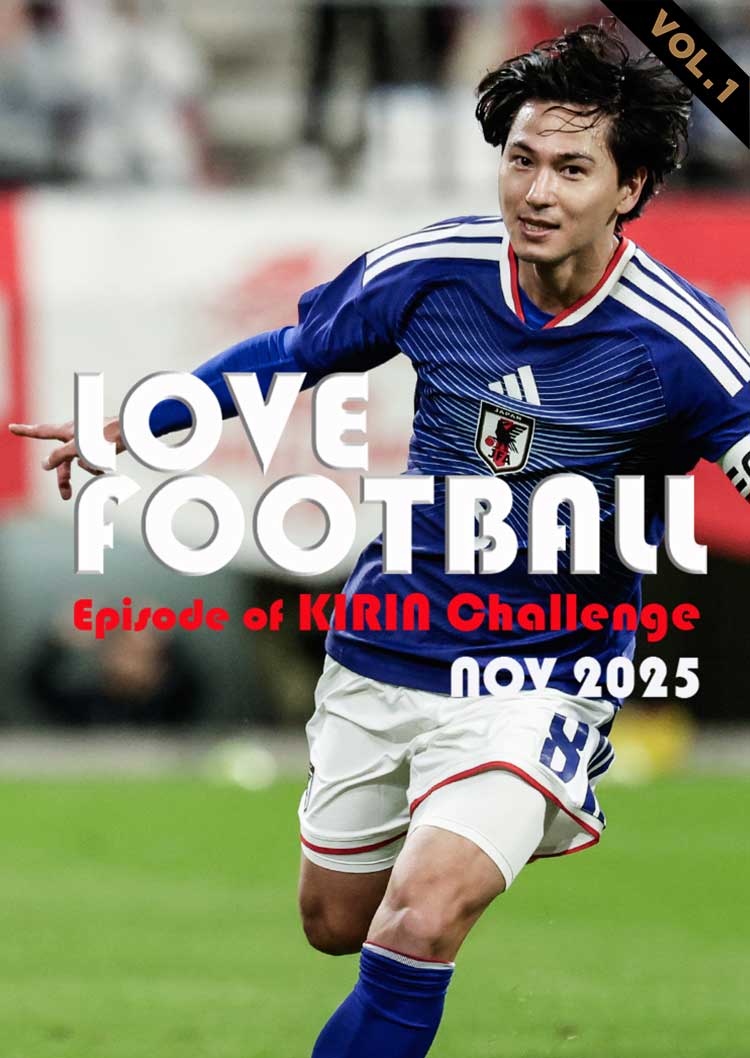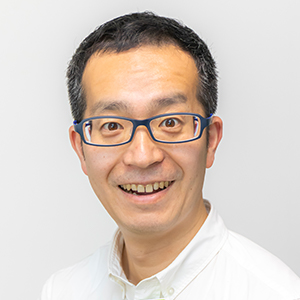1972年3月4日、東京・日大講堂は熱気に包まれていた。
WBA世界フライ級タイトルマッチ、王者・大場政夫(帝拳)―挑戦者・花形進(横浜協栄※カワイから名称変更)のライバル対決は挑発合戦もあってボルテージは最高潮に達していた。
花形が風邪をこじらせてしまった事実は限られた人しか知られていない。スタミナ面に不安を残しており、序盤を勝負のキーポイントに置いた、
ジャブの差し合いからの静かな立ち上がり。1ラウンド残り1分手前で左フックをヒットさせた。2ラウンド1分過ぎには、左フックで大場に尻もちをつかせて場内を沸かせたものの、これはスリップと判定された。

花形は振り返る。
「大場くんの足がそろったところ、あごをかすって肩に当たった感触だった。ダウンを取ったと思ったんだけどなあ。あそこでダウンになってりゃ、逃げきろうとうまくやったかもしれない」
2ラウンドまでは花形ペース。いつもは終盤追い上げタイプなのだが、意識してギアを上げたことで流れをつかんだかに思えた。しかし打ち合いの誘いに大場が乗ってこない。スピードのあるコンビネーションを叩きこまれ、ペースを逆に握られてしまう。
だが体調不良を乗り越えてここまでたどり着いたのだ。3度目の正直、負けるわけにはいかない。大場には一度勝っている。絶対に勝機はあると己を鼓舞した。
8ラウンドには大場の右を浴びて一瞬止まったが、それでも反撃しようとする。逆に9ラウンドはロングレンジの右を見舞って下がらせたが、終盤には大場が盛り返してくる。意地と意地、プライドとプライドのぶつかり。ラウンドを追うごとに激しさが増していく好勝負は判定に持ち込まれた。
結果は5ポイント差、4ポイント差、1人はドローという0―2判定で敗れた。花形は大場と抱き合い、静かにリングを降りた。
この一戦の記憶は50年近く経っても、花形の脳裏に深くこびりついている。
「もう意地だよ、意地。相手が大場くんじゃなかったら途中で(試合を)投げていたかもね。無理だってとぼけて倒れていたかもしれない(笑)。大場くんはなにせ気が強い。それは(戦いながら)感じていたね」
ある新聞も「壮烈な決闘」という大きな見出しで、この試合を表現している。まさにお互いに持てる力を出し切った名勝負だった。
花形の挑戦を振り切った大場はそれ以降、オルランド・モラレス(パナマ)、チャチャイ・チオノイ(タイ)をいずれもKOで下して名チャンピオンへの階段を上がっていく。だが、1973年1月25日、交通事故により、23歳という若さで天国に旅立ってしまう。花形戦から8カ月後のことだった。
自宅で一報を知った花形は絶句するしかなかった。
「信じられない。もうその一言しかないよ……」
拳を交え合った者しか分からない友情がある。ライバルの突然の死を現実として受け止めるには時間が掛かった。
花形は再び世界王者を目指して、歩みを進めていく。
WBA新王者となったチャチャイのホーム、タイに乗り込んで挑戦したが判定負けに終わる(1973年10月)。その1年後、またしてもチャチャイに挑むことになる。今度は日本で、それも地元の横浜で戦えることになった。
5度目の挑戦、もう27歳になっていた。
「死んでもいいから勝ちたいって、心の底からそう思ったよ。横浜で試合がやれるわけだし、もうここでやるしかないだろって」
死ぬ気で取り組んだ。真面目な人はこれまでも練習で手を抜いたことはない。それでもその上を行こうとした。大場戦の反省もあって、生活面でも最大限に注意を払ってコンディションを落とさないようにした。気持ちも体もこれ以上やることがないと言い切れるだけの状態に仕上げた。
1974年10月18日、横浜文化体育館。
花形は怒っていた。
チャチャイは前日計量でオーバーとなり、タイトルを剥奪された。花形が勝利すれば新王者に認定されるとはいえ、心も体も乗っていただけに水を差された形になった。
怒りは試合で示せばいい。
スタートから足を使いながらパンチを浴びせ続けていく一方的な展開。チャレンジャーは一切、気を緩めることなくチャチャイを攻め立てた。
フィナーレは突然にやってくる。
6回途中だった。レフェリーはパンチが出ないチャチャイの戦意喪失と判断して試合をストップする。レフェリーにしがみつくようにうずくまるチャチャイに目を向ける花形に笑顔はなかった。
「チャチャイが泣いているんだよ。何やってんだって思ったね。5度目の挑戦で勝って、泣きたいのは俺のほうなんだから。河合(哲朗)会長と抱き合って喜びたいのに、俺も会長も呆気にとられちゃって。ただ、チャイチャイがベストの状態だったとしても、絶対に勝てるという確信はあった。中盤から勝負に出ていって倒し切れると思っていた。だからもう拍子抜けもいいところ。次の日の新聞には『あんな相手なら誰でも勝てる』みたいなことを書かれていて悔しかったよね」
それでものどから手が出るほど欲しかった世界チャンピオンの称号を手に入れた。
会場には母親や妻がいた。河合会長、後援者、友人、知人……支えてもらった人々にやっと喜んでもらえる。そう思うと、少し肩の荷が下りる気がした。
ボクシングを始めたときから応援してくれていた父の姿はない。6回戦ボクサーのときに他界していたが、〝人より一つでいいから上に立つものをつくれ〟という父の教えをようやく実現できたという感慨もなかったわけではない。

「親父には世界チャンピオンになった姿を見せたかったというのはあるよ。俺がチャンピオンになるのを誰よりも楽しみにしてくれていたし、会社でも俺がボクサーだっていうのを自慢していたらしいからね」
きっと父親は天国で世界チャンピオンになったことを自慢してくれていることだろう。
負けても失敗しても、それを何度も繰り返しても、花形進はあきらなかった。世界一になる目標を決して降ろさなかった。
62試合目の栄光。
長い、長い道のりが、花形進を強者にした――。
2020年12月公開