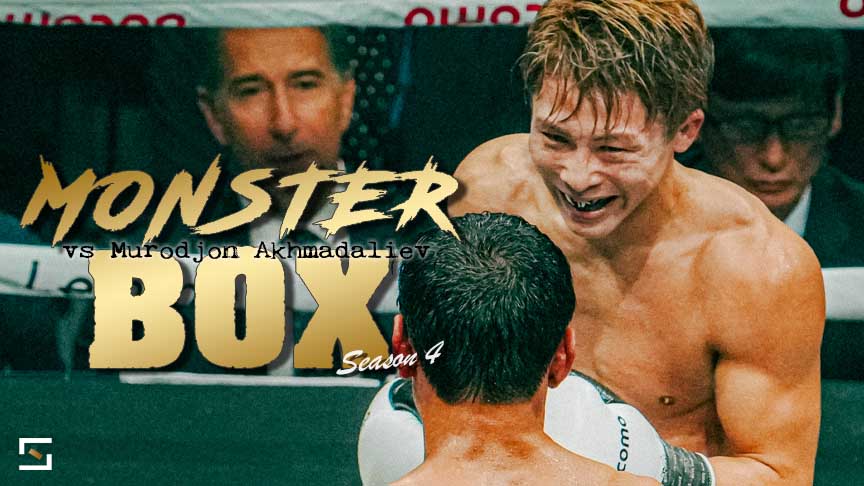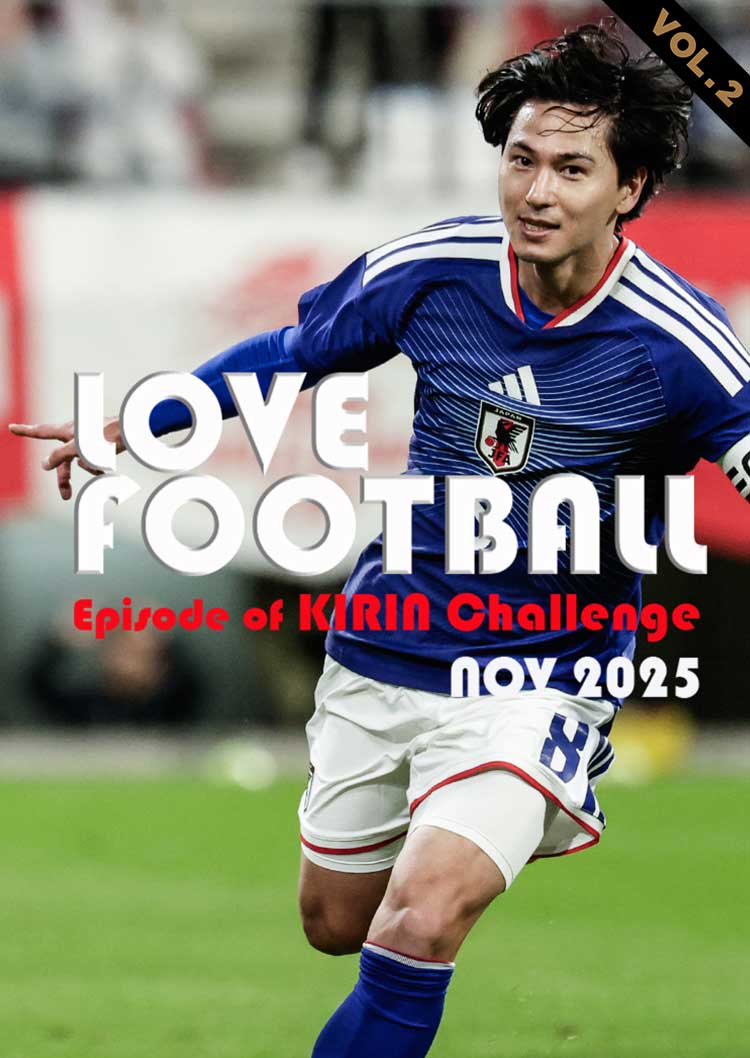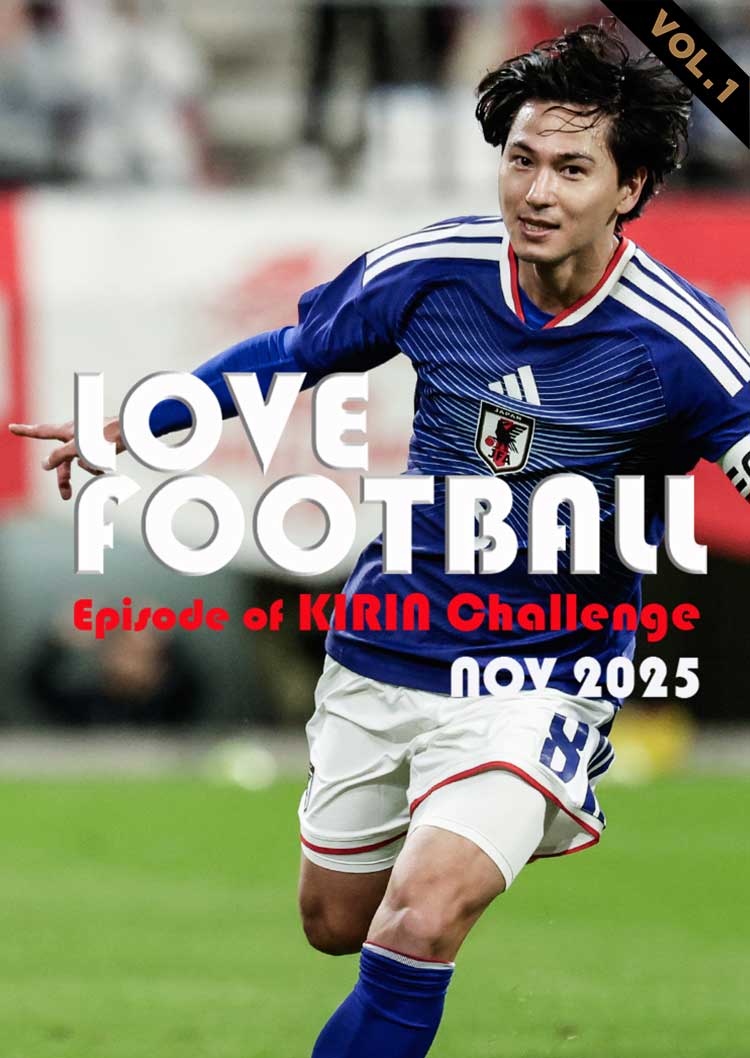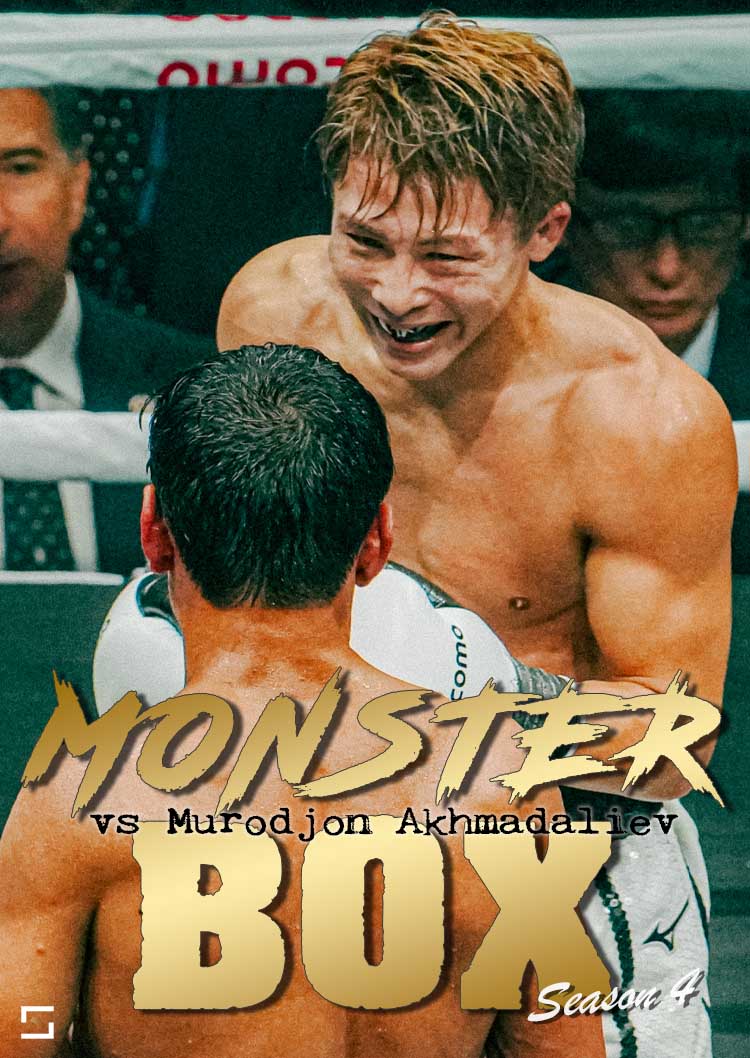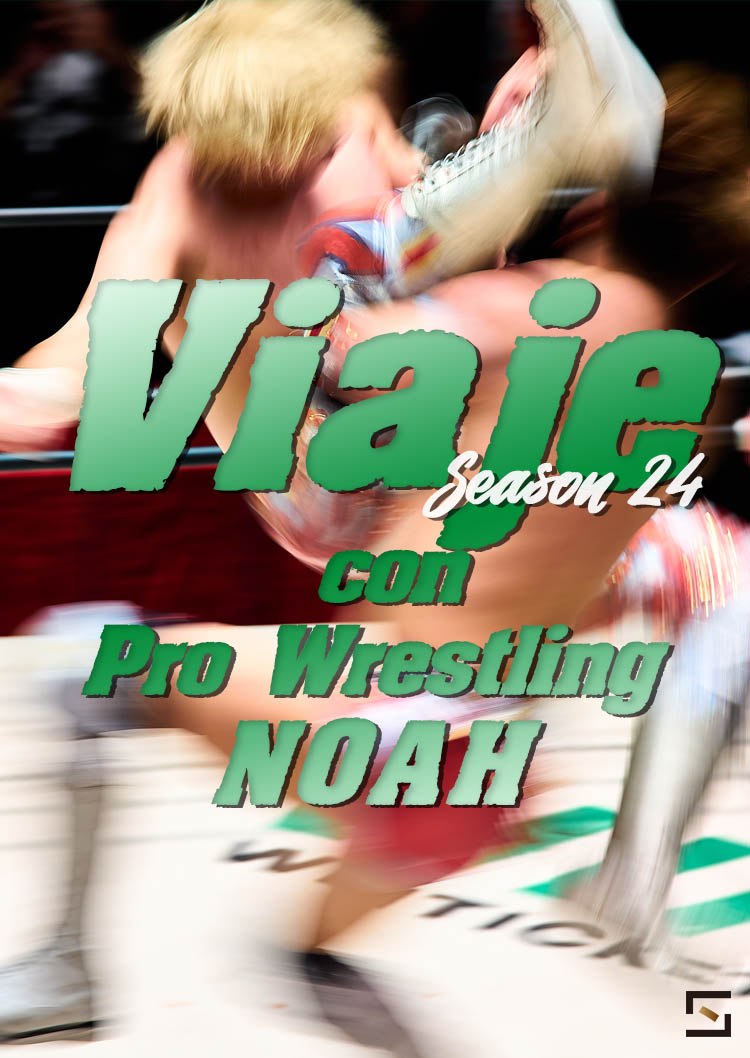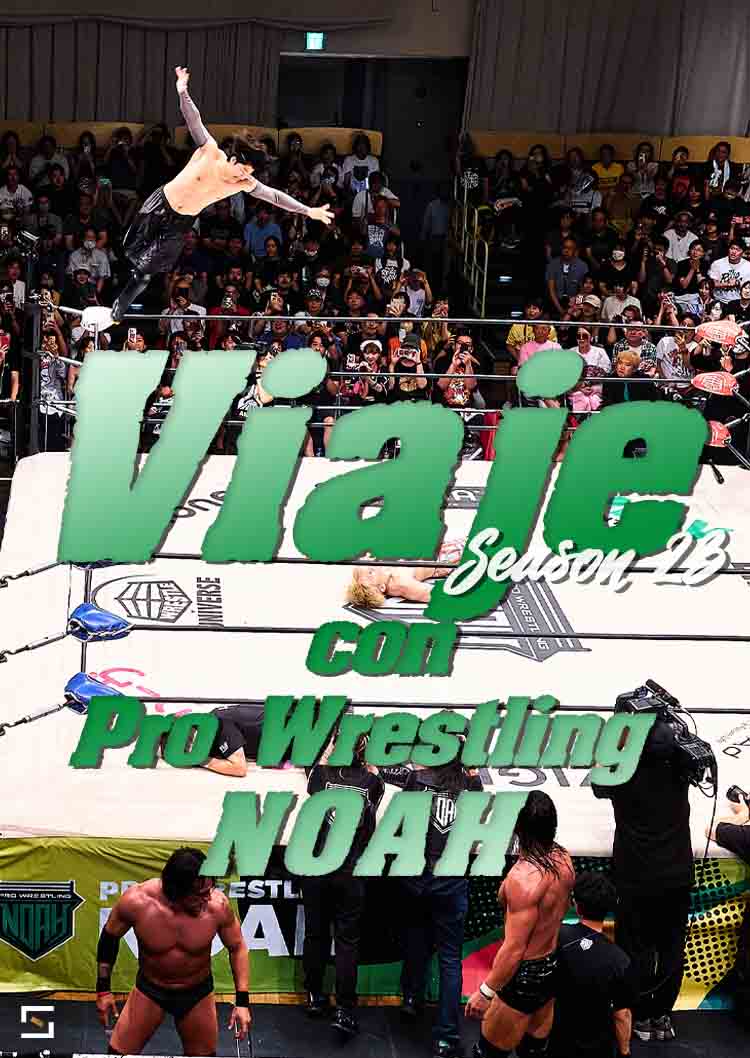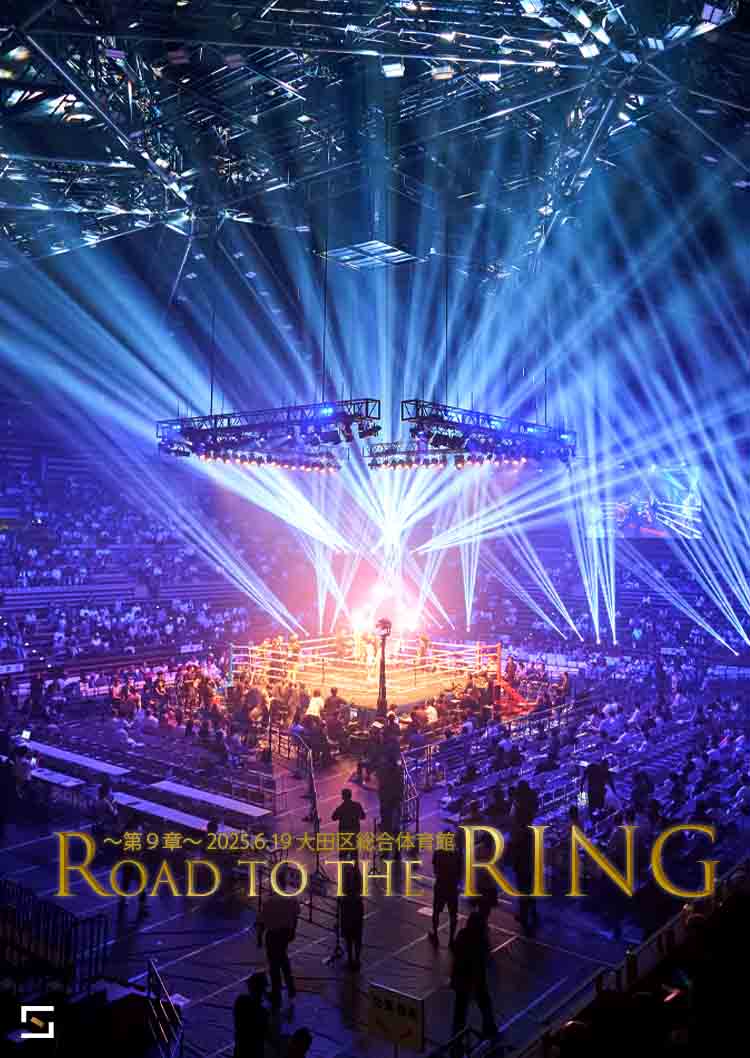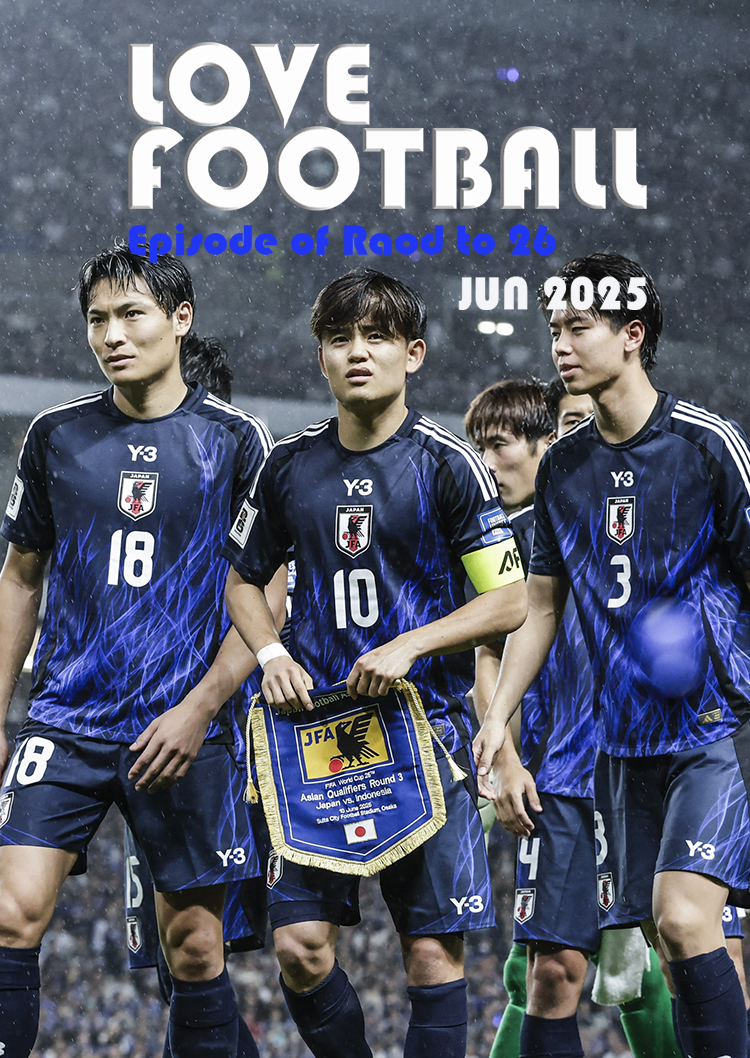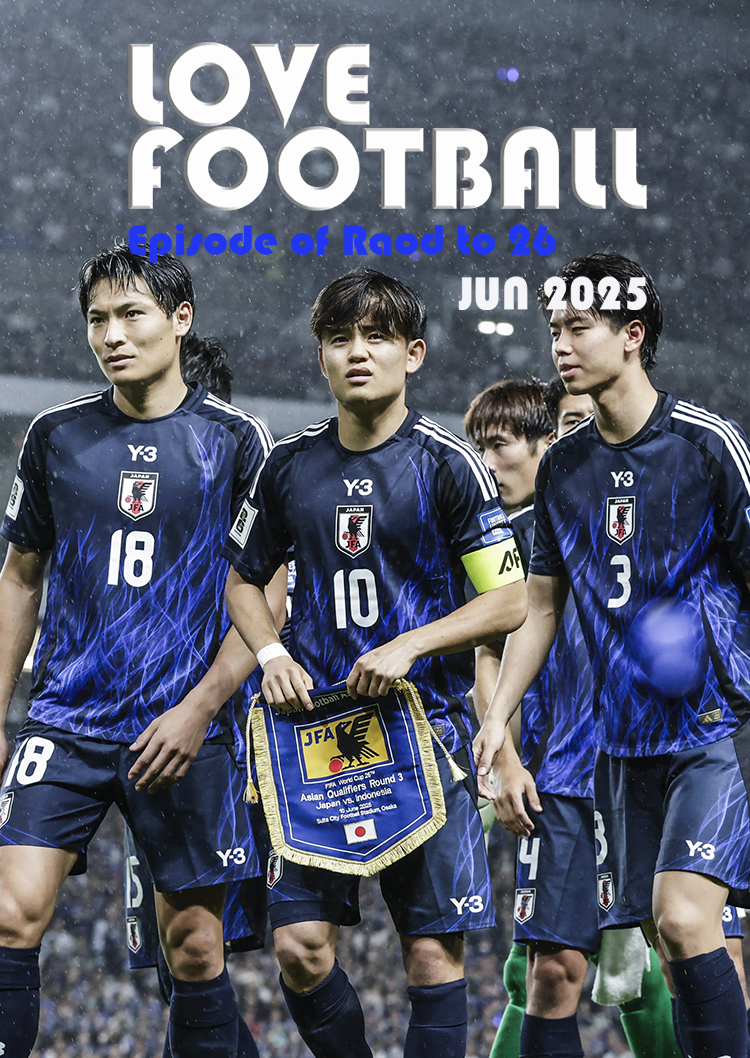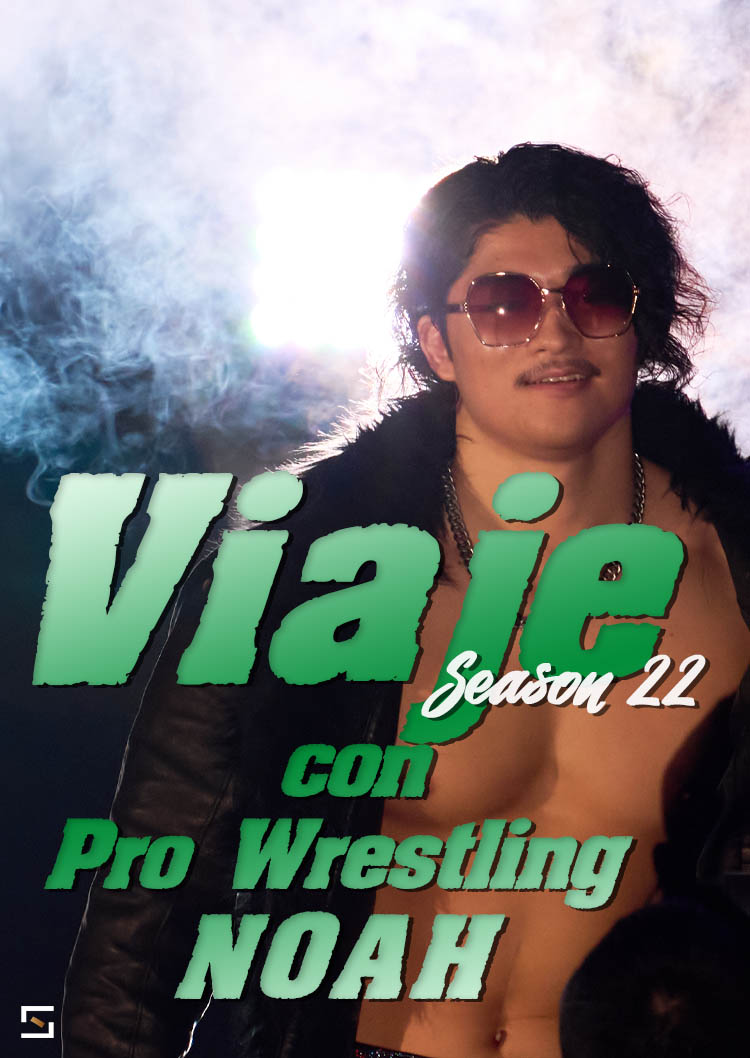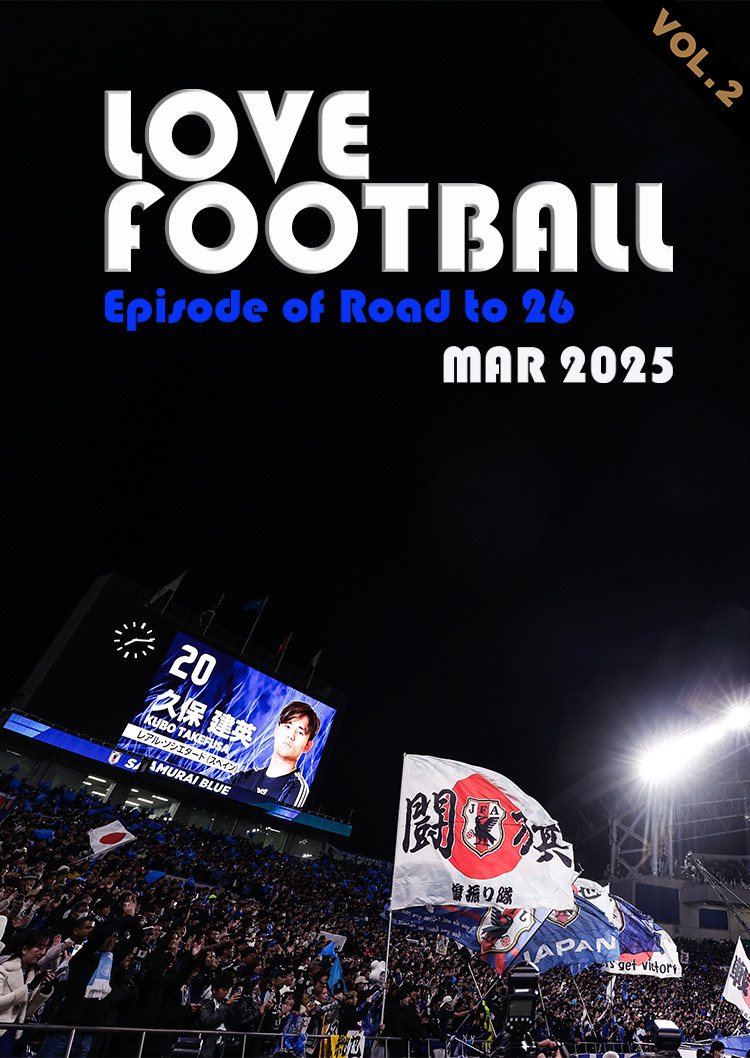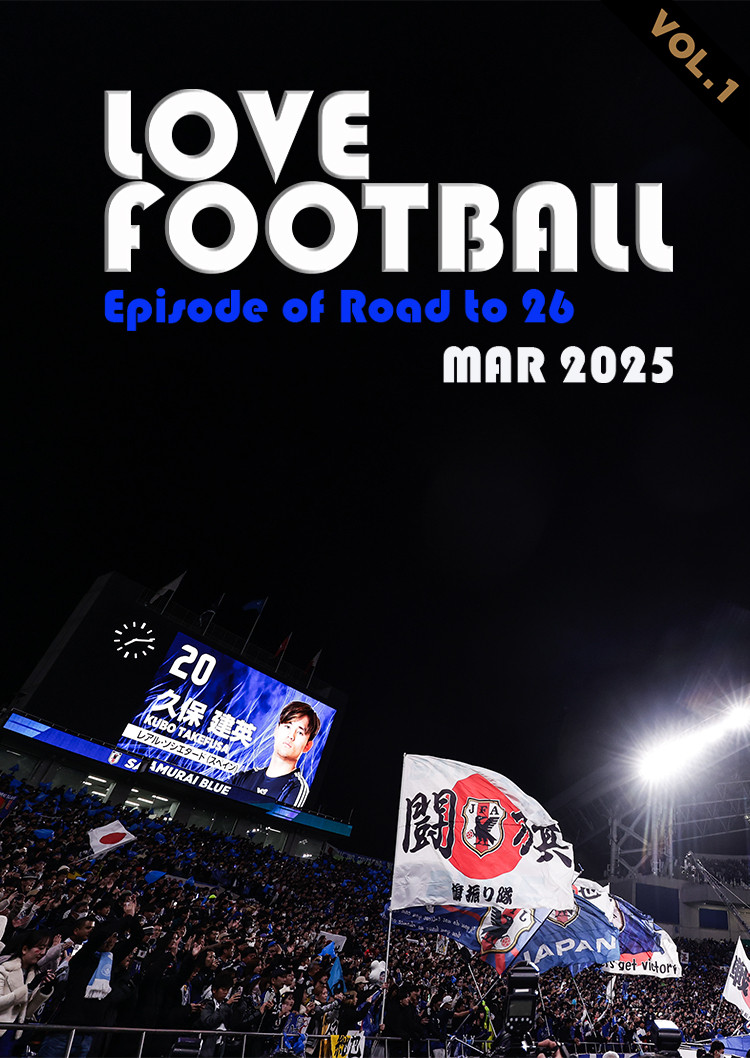当初は仁川アジア大会を区切りに考えていたセパタクロー取材だったけれど、一から見直すことになった。まずは取材方式を変えることにした。選手全員を対象にすることを断念したのだ。選手たちには良くしてもらっていたから、難しい決断だったけれど、取材対象を絞ってテーマをハッキリさせる必要があった。被写体に選んだのは当時、日本人で唯一タイのプロリーグに挑戦していた寺島武志だった。
国内で唯一の実業団チーム阪神酒販で正社員として働きながらプレーしている彼は、毎年、タイのプロリーグに挑戦していた。僕が初めて現地で彼を取材したのは、彼がタイに渡るようになって4年目のシーズンだった。この年はバンコクから車で2時間、ビーチで有名なパタヤのチームだった。初めてタイに挑戦したときは言葉も喋れず、チームに溶け込むこともできなかったと言う。それから3年。流暢なタイ語を喋り、チームにもすっかり馴染んでいた。
寺島を中心に追いかけるようになって2年が経ったころ、写真について新たな指摘を受けることになった。ひとつは被写体と距離がある点だった。
「なんで正面からの写真がないの?」
普段のスポーツ撮影では400ミリの望遠レンズを使用することがほとんどだ。競技中は安全面も考えて5メートルは離れている。これは10年以上かけて培った感覚だし、僕自身にとっても心地いい距離感だった。ドキュメンタリーとして、寺島を狙うときは50ミリの標準レンズを選び、なるべく近くに寄るように心がけてはいたけれど、実際には3メートルより近づくことができなかった。表情を大きく切り撮りたいときは望遠レンズを使い、正面に回り込むことは躊躇われた。この頃にはプライベートな話もできる間柄にもなっていたけれど、どうしても踏み込めなかった。
望遠レンズで表情を狙うときも横顔が多かった
そこである日、覚悟を決めて寺島に話したことがある。このままではドキュメンタリーとして成立せず、これまで撮ってきた写真も発表できずに終わる可能性が高いこと。その理由は僕が勇気をもって踏み込むことができないこと。そもそも極度の人見知りだから、こうして向き合って話していることも実は苦手なこと。でも僕はどうしてもセパタクローで個展をしたいこと。そうすることがこれまで取材に協力してくれた選手たちへの恩返しになると信じていること。だから、これからは厳しい状況、苦しいときでも突っ込んでいきたいと思っていること。撮られて嫌なときもあると思うけど、それは許してほしいこと。だいたい、そんなことを話した。
「何でも撮ってください。実は俺も人見知りですよ」
寺島はそう言って笑ってくれた。この日を境に僕はより突っ込んだ撮影ができるようになった。少しだけ光が見えてきた気がした。

上段は初めてタイで撮った練習後、下段は3年目の写真。どちらも同じレンズでの撮影
もうひとつは僕のドキュメンタリーに対する解釈の問題だった。タイ在住のカメラマンの友人からされた指摘だった。
「高須くんの写真はカッコいいいんだけど、これ(セパタクローの写真を)見てると胸が苦しくなるんだよね。たとえば紛争地のドキュメンタリーあるじゃない? その中には必ず笑顔の写真あるでしょ。何でだと思う? 見る人は悲惨な状況でも笑顔があるんだって思いたいのよ。犬猫や動物写真が人気なのも同じ理由だよ。みんな癒やされたいの。見て苦しくなるだけの写真なんて誰がみたいと思う?」

ストイックな部分に焦点をあてた写真
いつだったか寺島が言っていた。
「昔は本当に大変でしたけど、今は環境もだいぶ整ってきました。理解して協力してくれる企業も増えたから、仕事だってバイトじゃなくて社員待遇が増えました。もう貧乏ネタで取り上げられるのは違うと思います。若い子たちが『どうせ俺たちなんて』って思ってるのも好きじゃない。俺はセパタクローをやって幸せですし、若い子たちにもそう思ってもらいたい。そのためにも生涯かけてセパタクローに関わって生きていきたいです」
ハッとさせられた。「恵まれていない環境で人生を削りながら競技に取り組んでいる」というステレオタイプに侵されて、ストイックなシーンにばかり気をとられていたのは、他ならぬ僕だったからだ。
それからは今まで見逃していたシーンを意識するようになった。それは彼らの笑顔だ。なぜ笑顔なのか、どういう状況で笑っているのか。僕は誰よりも近くでそれを見てきた。面白くて笑い、楽しくて笑い、嬉しくて笑う。そこには様々な笑顔があるのだ。彼らの周りには笑顔が溢れている。だって、セパタクローは幸せになるためにやっているのだから。
スタンド・バイ・ミーのイメージで!
2022年9月公開