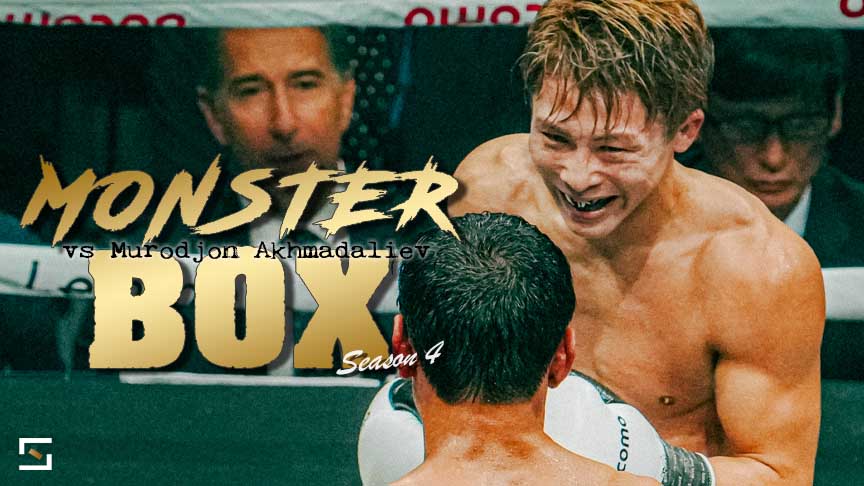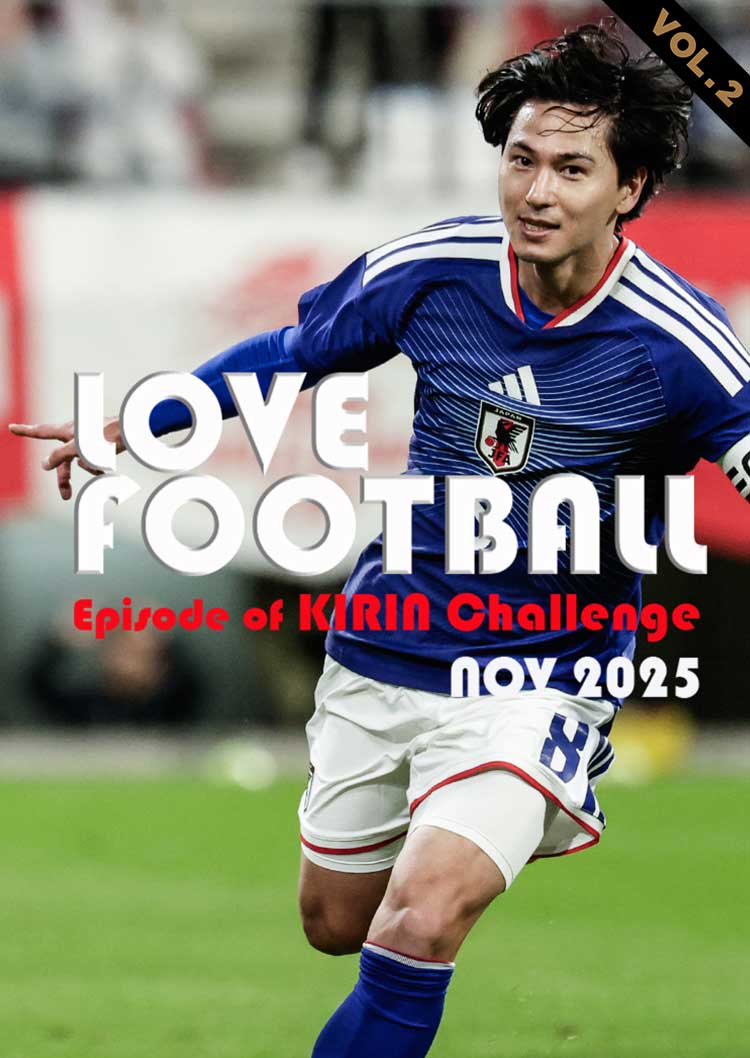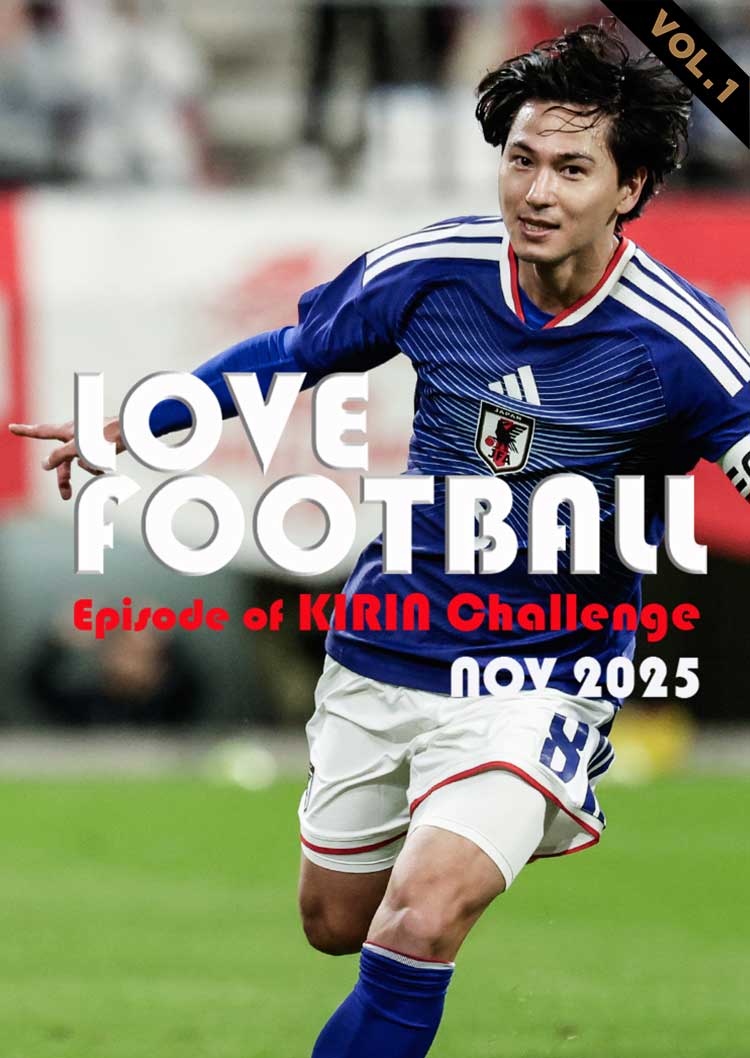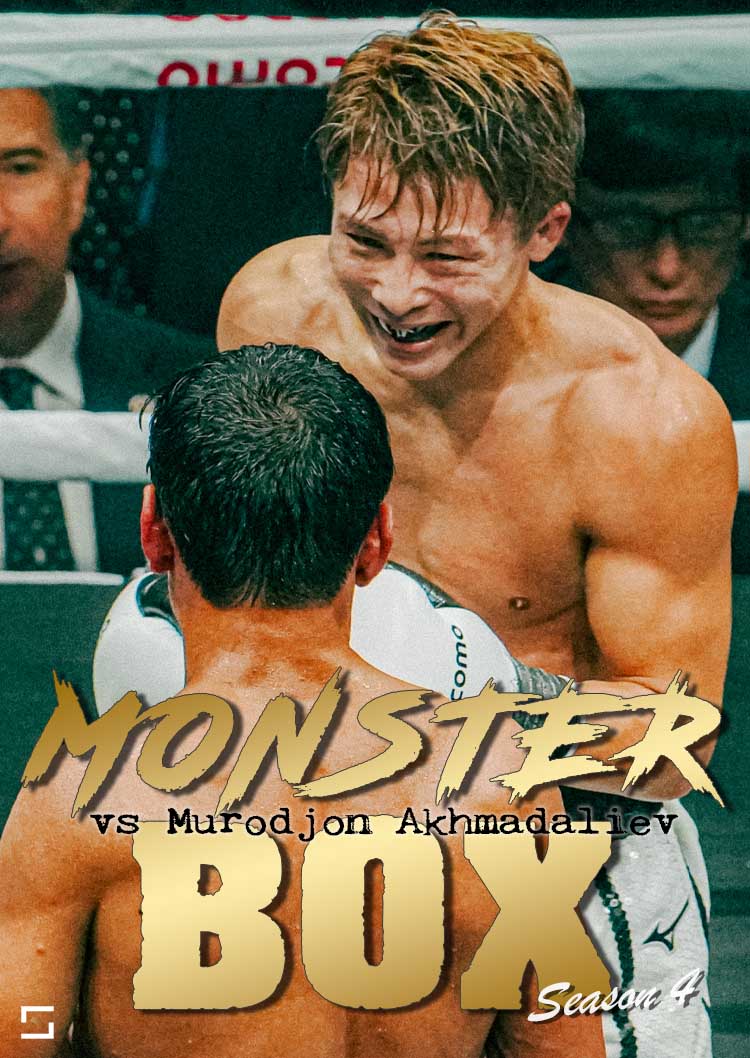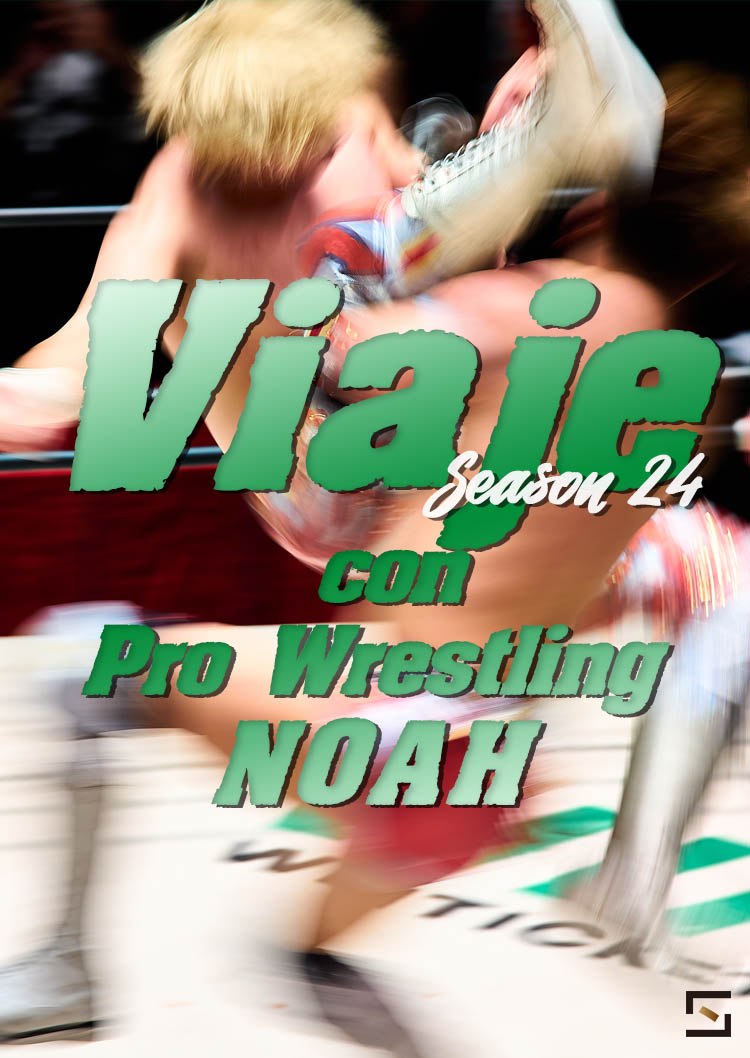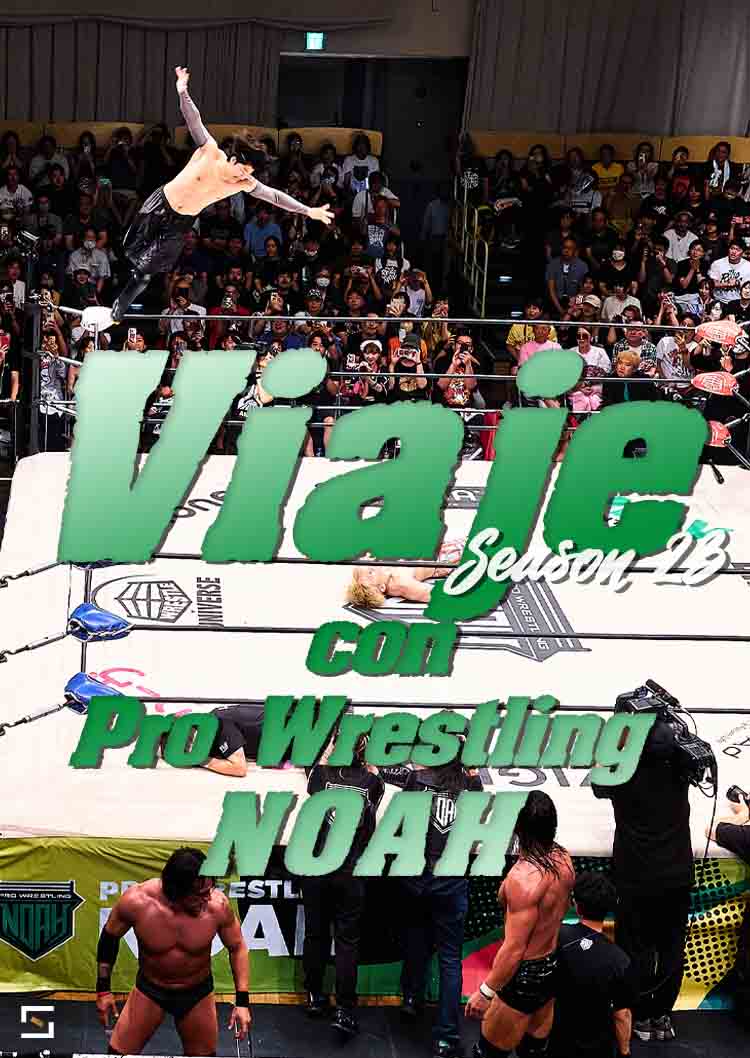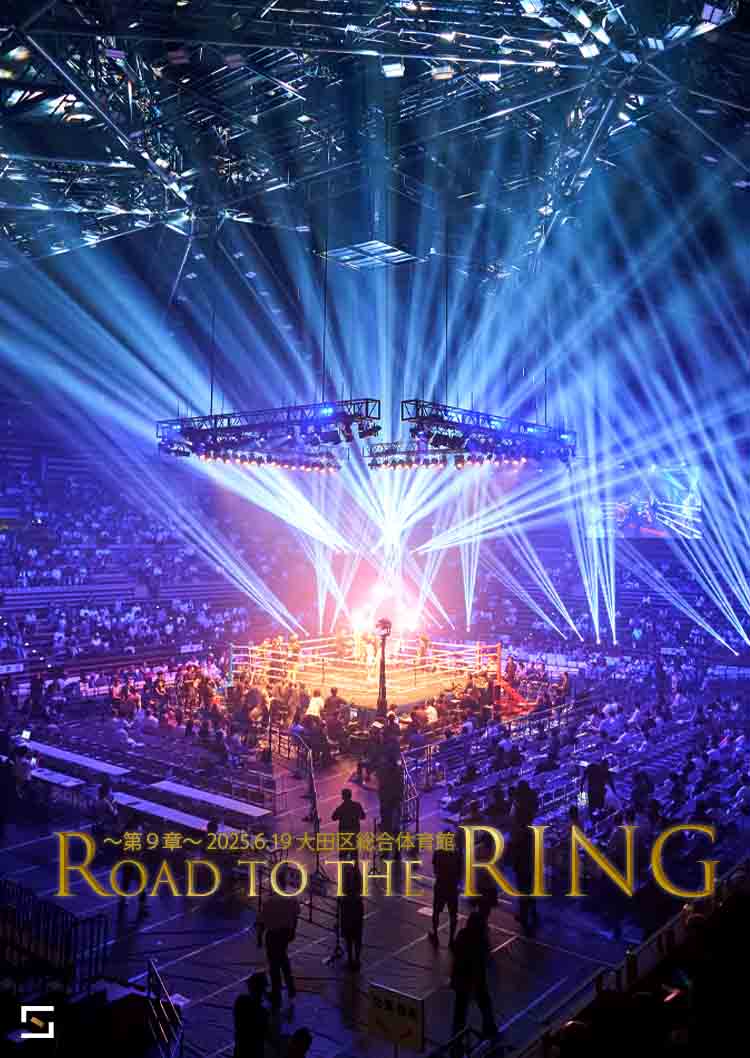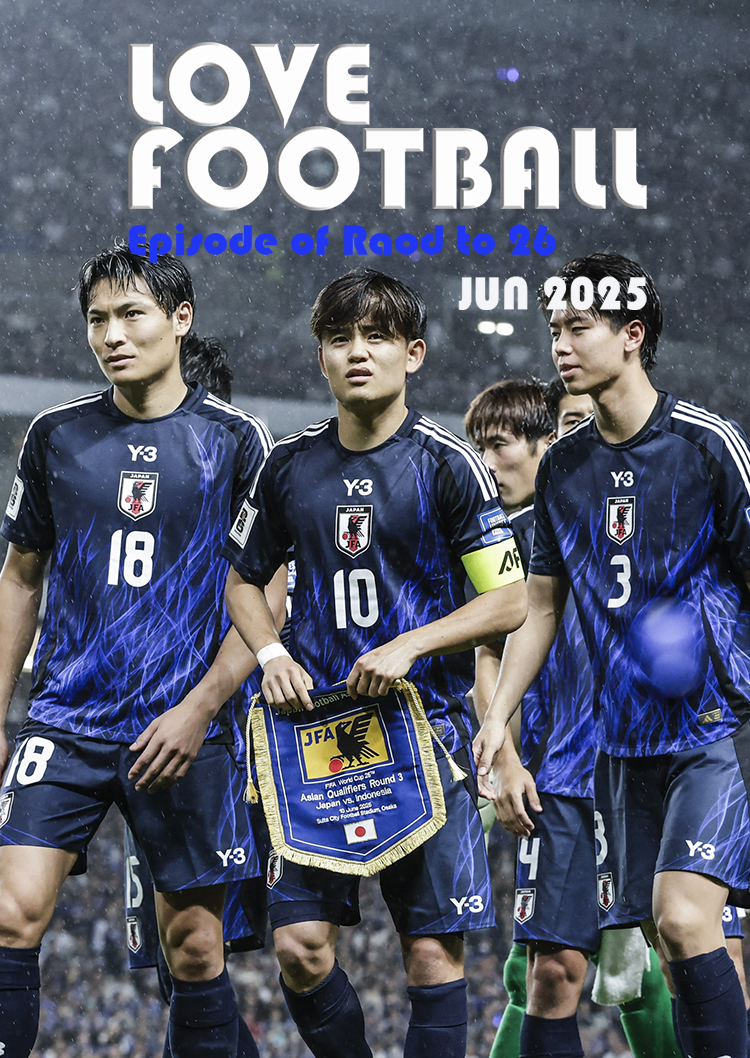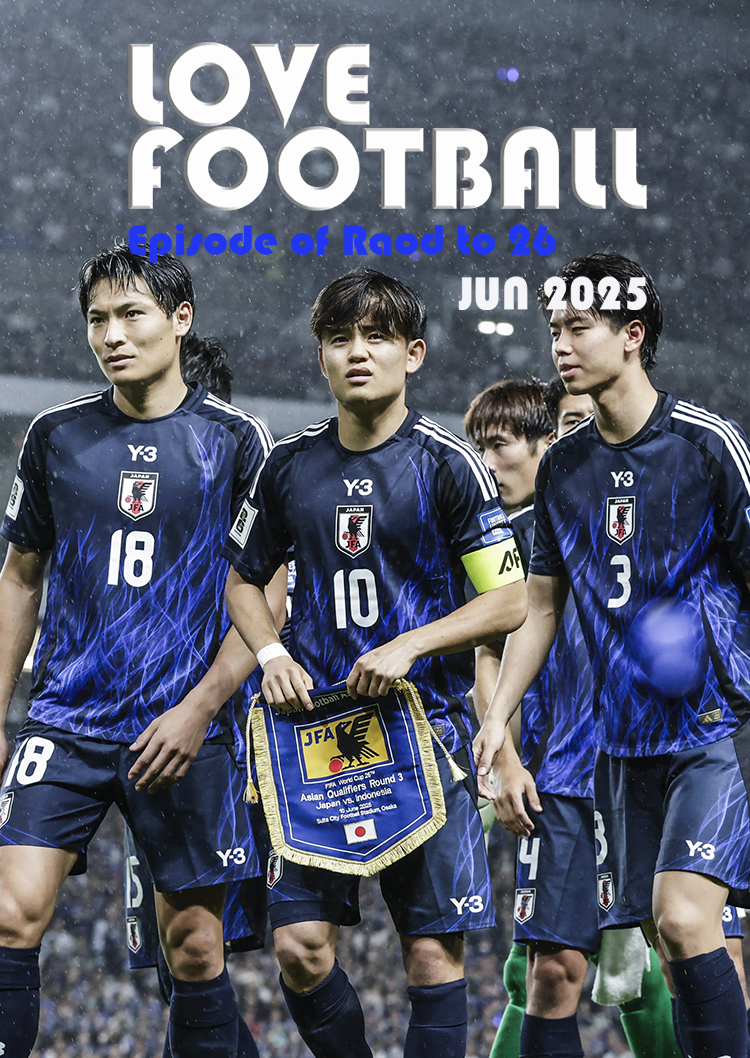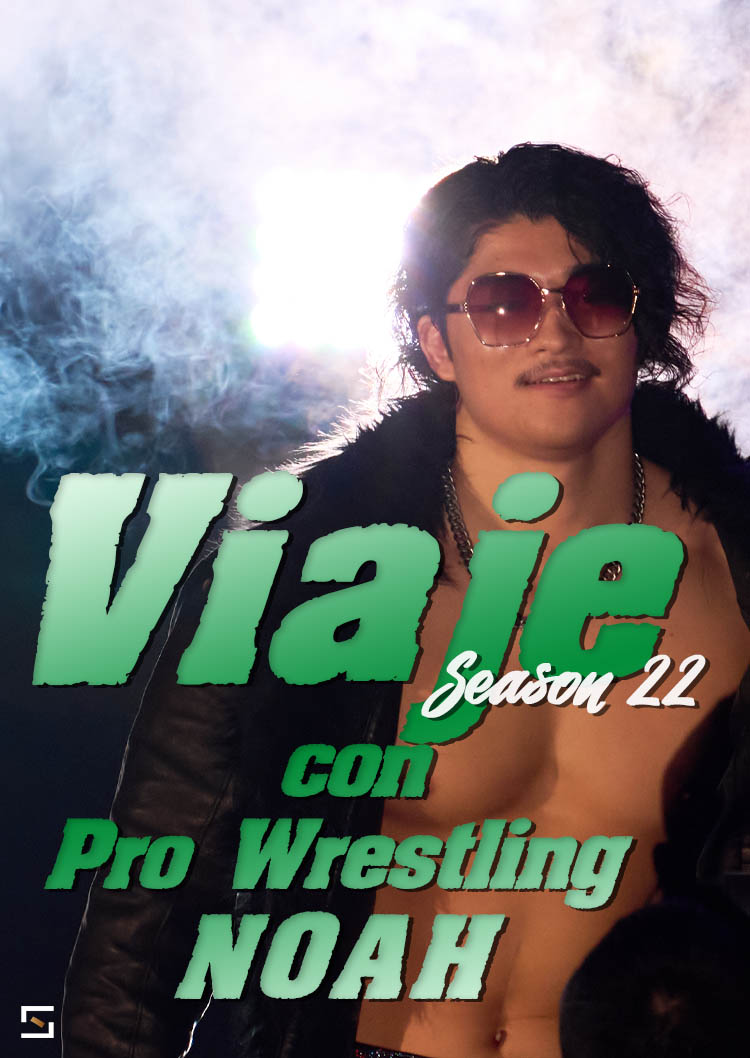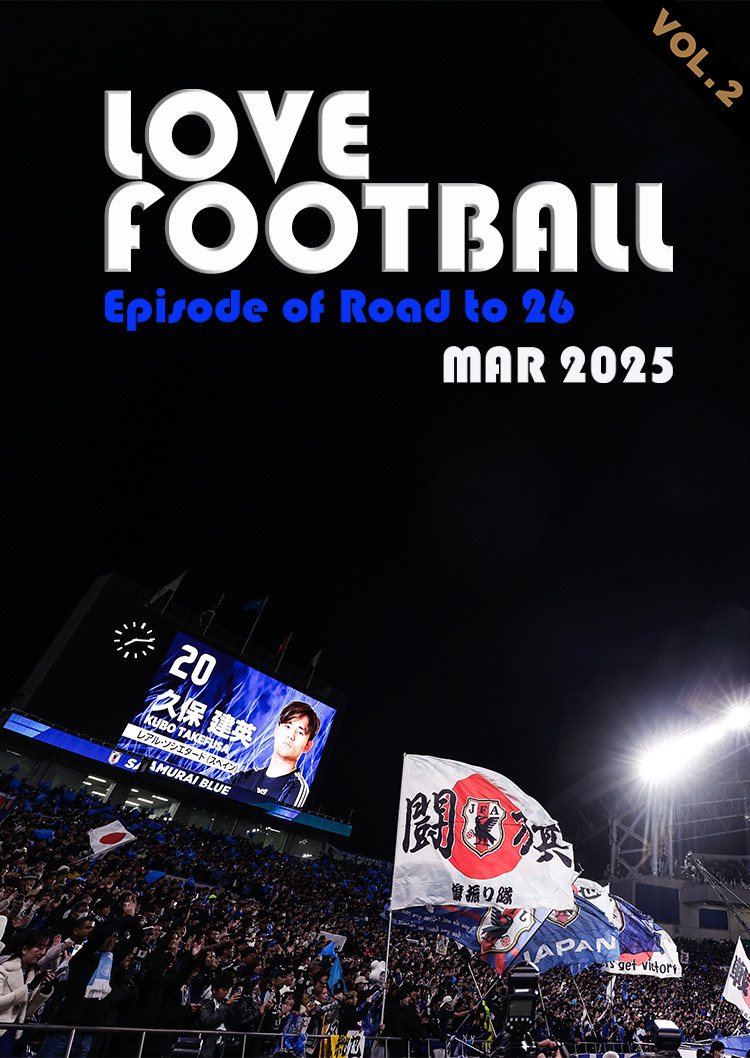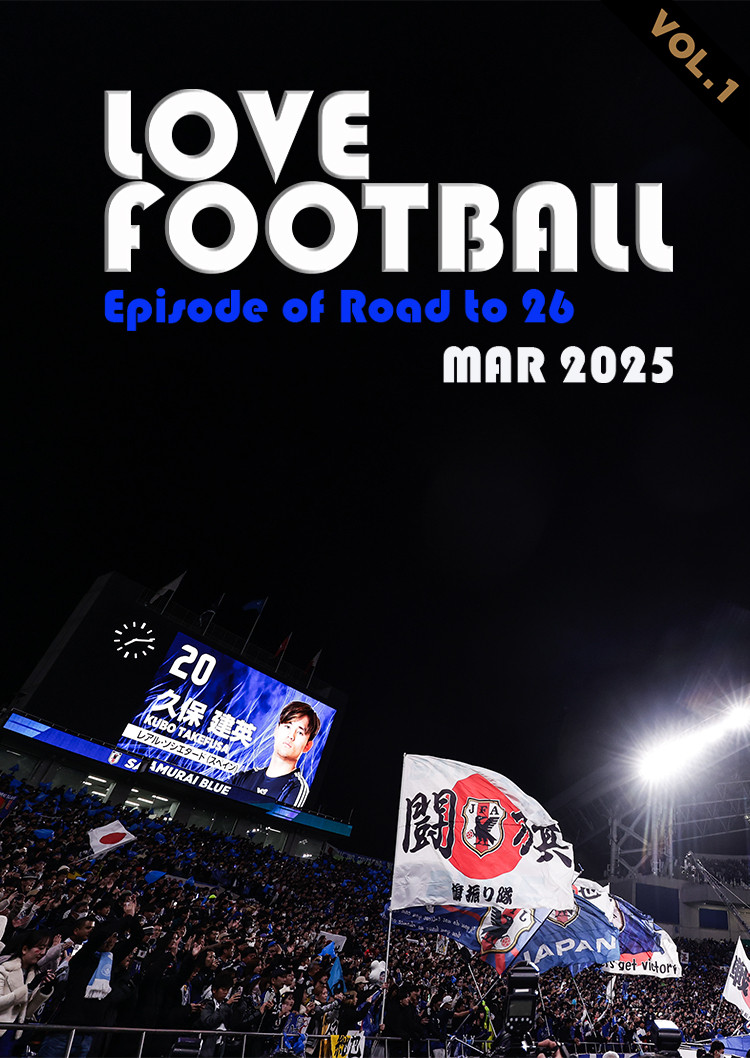部員の人間形成において、大切なことは何か。
部を強くして勝つだけで満たされるとは言えない。
社会を知る、に目を向けるべし。
慶応大学ラグビー部(名称は慶應義塾體育會蹴球部)において卒業後も仕事としてラグビーを続ける割合は他の強豪校と比べると多くない。大学生は年齢的に身体的に大人に達するとはいえ、精神的には大人への階段をのぼっている途中だ。ヘッドコーチを務める栗原徹はサントリー・サンゴリアス在籍中に母校の大学院に進んでおり、スポーツマネジメントを学ぶためにJリーグ・鹿島アントラーズへのインターンシップ経験もある。GMの和田康二は卒業してゴールドマンサックス証券に入社して、ビジネスマンの道を選んできた。大学院システムデザイン・マネジメント研究科の研究員として大学スポーツが持つ価値を探究している顔も持つ。そんな彼らだからこそラグビーのみならず、「社会」により目を向けさせることが可能だったのかもしれない。

部員による地域貢献が、その一助となった。
部の日吉グラウンドは、ワールドカップの決勝舞台となった横浜国際総合競技場と同じ横浜市港北区にある。2017年よりワールドカップに向けてラグビーの認知、普及を広げていく目的もあって、横浜市港北区、港北区体育協会、部の三者が協力して部員による「タグラグビー教室」「ラグビー授業」が実施されてきた。和田はGMとして活動を推進してきたが、2019年はワールドカップイヤーとあって活動も活発化。港北区内の小学校をコーチ、学生が訪問指導した回数は30以上にのぼった。日吉グラウンドでラグビー体験会も行なっている。
分かりやすく、丁寧に、かつ盛り上げながら。
学生主導で授業内容を考えていたという。GMとして直接、学生の活動を目にしてきた和田は彼らの受け身ではない能動的な取り組みに感心した。自主性を養うという栗原の方針も、彼らを前向きに取り組ませた一つの要因となったのかもしれない。
和田は言う。
「学生たちは本当に頑張ってくれて、地域の人も子どもたちも喜んでくれました。とても評判が良くて、うれしい反応が多かったんです。それに学生って子供たちの教え方がじょうずだし、すぐに溶け込める。僕たちもいろんな発見がありました」
彼は大きなアクションを起こしていた。
2018年にOB会が立ち上げた一般社団法人慶応ラグビー倶楽部、大学院システムデザイン・マネジメント研究科と部が連携して、小学生を対象としたスポーツ教室、ラグビー教室を行なう「慶応キッズパフォーマンスアカデミー」を2019年5月に開校するに至った。
あくまで大学院の教育研究事業であるが、ラグビーの発展や地域社会との共生に貢献できるという側面もある。このプロジェクトを推進する役割を担う和田は栗原の協力、理解を得て、可能な範囲で部員にも子供たちの指導を依頼するプランを立てていく。
一方の栗原もあるアイデアを実行に移している。
日吉と言えば慶応大学のキャンパスがあり、学生の町という印象が強い。「普通部通り」「浜銀通り」「サンロード」「日吉中央通り」と4つの商店街があり、落ち着いた風情とともに若者たちでにぎわっている町だ。
しかし地域と慶応のシンボル的な存在でもあるラグビー部にあまり交流がないことを、栗原は「何とかできないか」と考えていた。
「グラウンドのある方面に体のゴツい体格の学生が歩いていたら、町の人も『ラグビー部だな』と分かるじゃないですか。もし町でマナーの良くないことをしたら、学生にとっても部にとってもマイナス。ましてや応援してあげようなんて思わない。ずっとこの日吉にグラウンドがあるのに、あまり深い付き合いがないっていうのはちょっと寂しいんじゃないか、と」
栗原はトップリーグのサンゴリアス時代に、マナーの大切さを学んだという。自分がどう振る舞うかによって、周りの人を爽快にもさせるし、不快にもさせる。爽快にさせられれば、ひいてはそれがチームのためにも自分のためにもなる。
栗原は学生たちにある企画を提案した。4年から1年まで4、5人のグループをつくり、それぞれ日吉限定でランチを食べにいき、店員さんと写真を撮って「蹴球部のことを応援よろしくお願いします」とPRするという企画だ。
試しにやってみたら、学生たちも乗り気だった。どのグループが一番、店員さんと仲良さそうに映っているかを競い合った。
「2019年は1回しかやれなかったけど、部を知ってもらう、ちょっとでも部を応援してもらう。そんな雰囲気が出てきたら、学生たちのモチベーションも上がると思うんです。ドラマの『ノーサイドゲーム』で佐々コーチが、子供たちに応援されるっていうシーンがありましたよね。大学だけじゃなくて、日吉の地域の人に応援されているんだぞってなると自然とマナーの意識も向上していくんじゃないか、と」
栗原のマネジメントは、ラグビーの厳しい練習だけでは終わらない。盟友の和田と話し合いながら、人間形成に対するマネジメントを進めていった。

栗原流改革として、これまでの慶応ラグビーになかったものがある。
それが留学生の受け入れである。
2019年秋、ニュージーランドからアイザイア・マプスア、イサコ・エノサの2人が慶応にやってきた。ラグビーありきではなく、あくまで大学ありき。彼らは受験を受けて合格しており、ラグビーもするが勉学もしっかりやるというスタンスは他の部員と変わらない。
栗原自身、トップリーグで異文化の外国籍選手と一緒にプレーしたり、触れ合ったりしたことが、かけがえのない財産になったという。考え方や、アプローチも違う。そのうえで自分を見つめ直すことができる。学生のうちから経験できるならそれに越したことはない。
留学生の力に頼るという発想ではない。
彼らと接する国際交流が、部員それぞれのマンパワーを引き上げると信じるからだ。栗原は合格が決まった後、2人に会うためにニュージーランドを訪れている。全員面談の一環ではあるものの、彼らの親に大学の説明をするとともに彼らの情報も欲しかったからだ。異国でさびしさを覚えないような声掛けができるようにしたいという思いもあった。
このまま留学生を受け入れなくていいのだろうか。
常識と思われていることを疑ってみる。
ルーツ校としての「いいと思ったら積極的にやっていくのが慶応の本来の良さ」精神に立てば、受け入れに躊躇することはなかった。時代の流れに合わせていけば、今がちょうどそのときと栗原は判断したのである。

しかし一方でグラウンドに目を移せば、厳しい戦いを強いられていた。
関東大学対抗戦第2戦、筑波大学との一戦(9月18日)。フォワード戦で優位に立ちながらも、思うように得点に結びつけることができない。次第にペースを握られるようになり、終盤立て続けにトライを奪われて逆転負けを喫したのだ。筑波に対しては7年ぶりの敗戦であった。
うまくいきそうで、うまくいかない。
栗原が抱いたもどかしさは、これで終わりではなかった。
2020年3月掲載