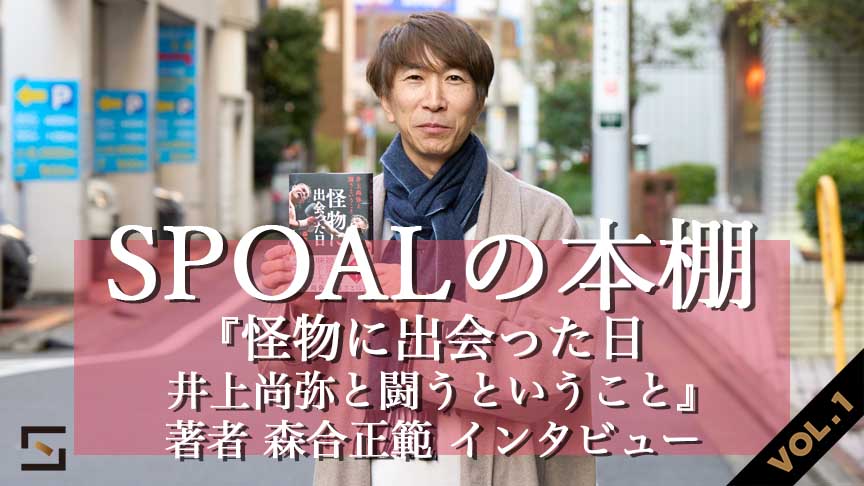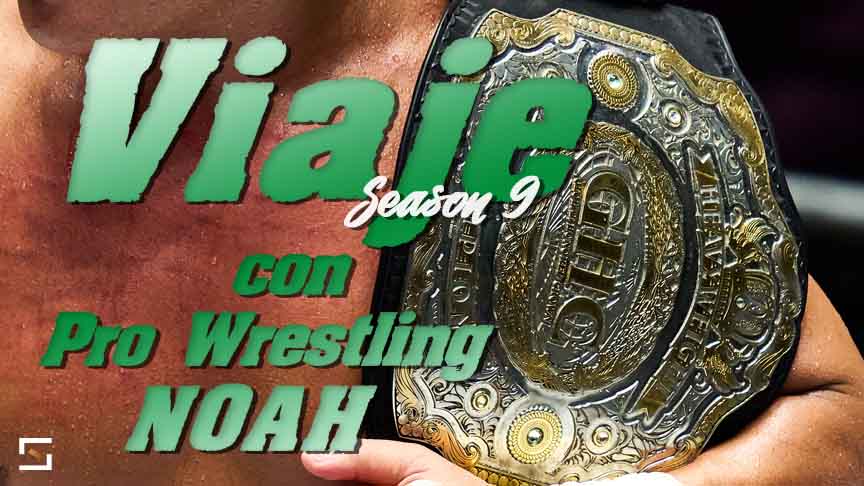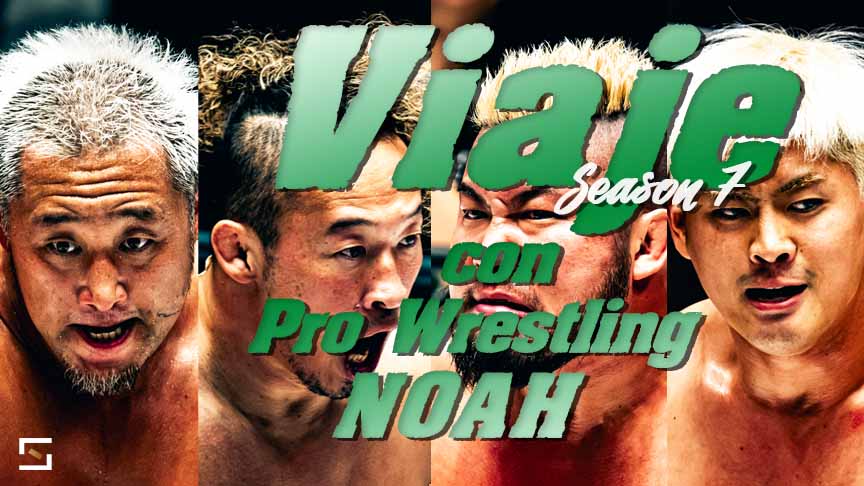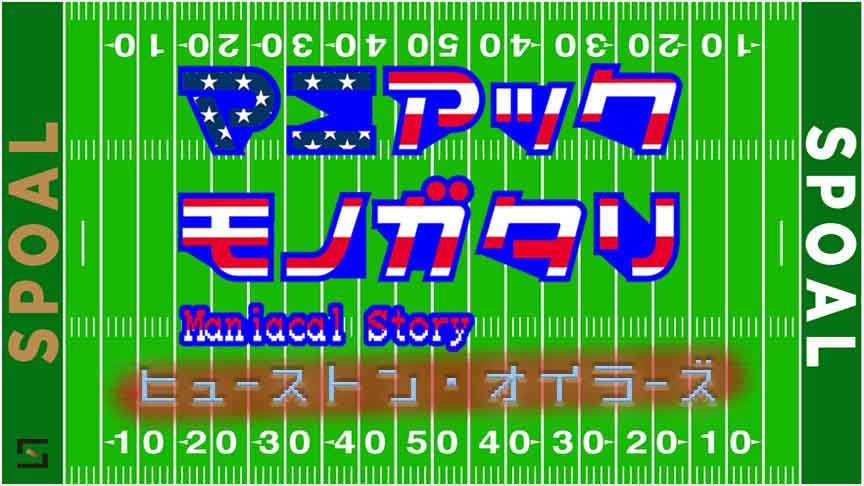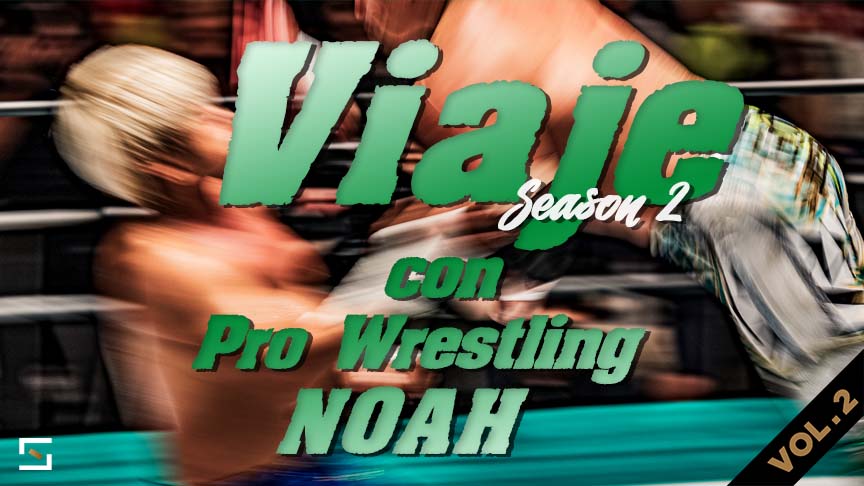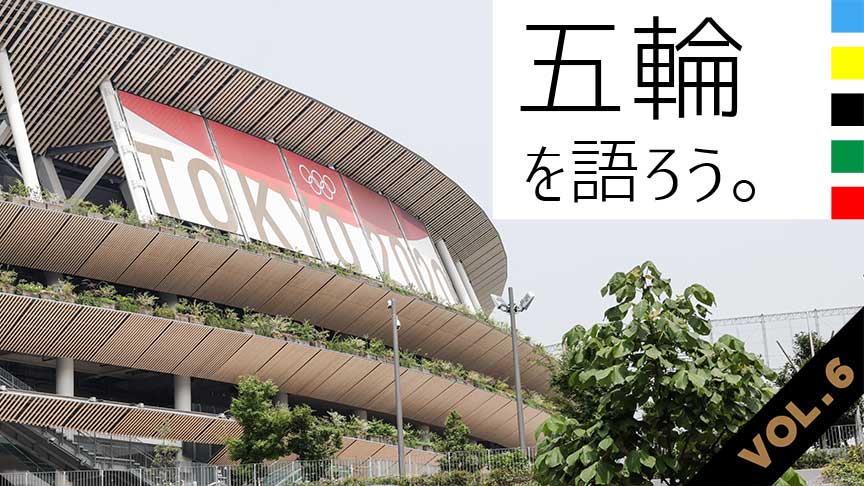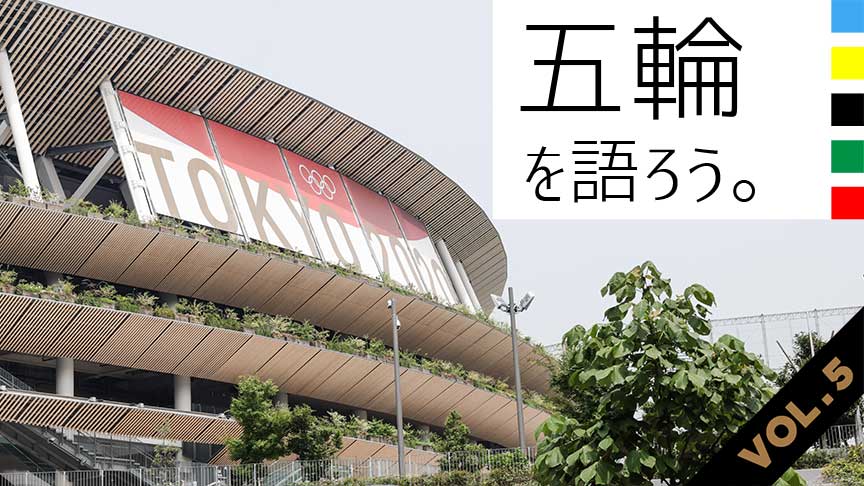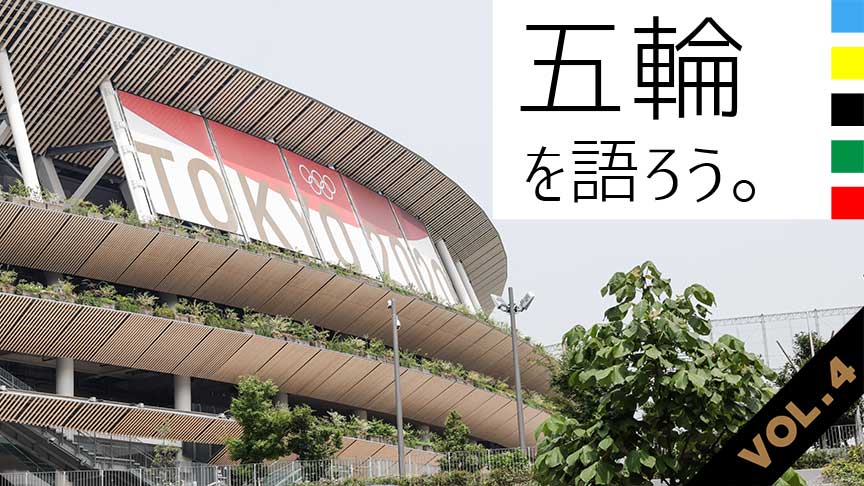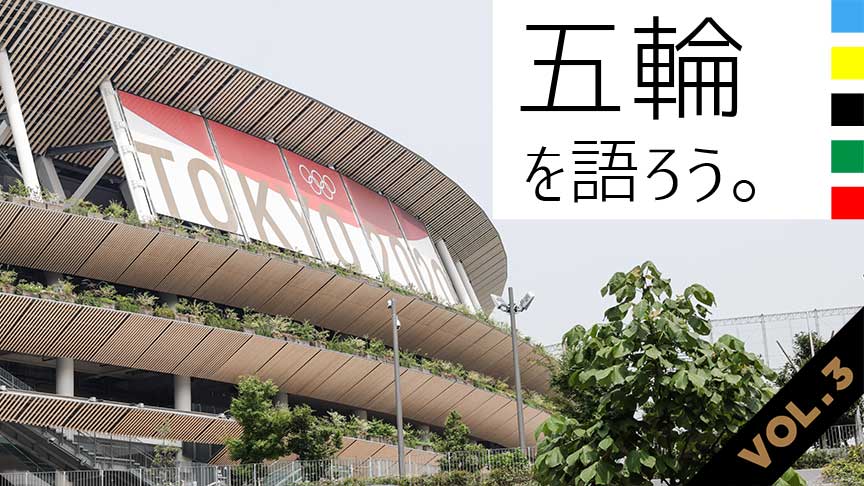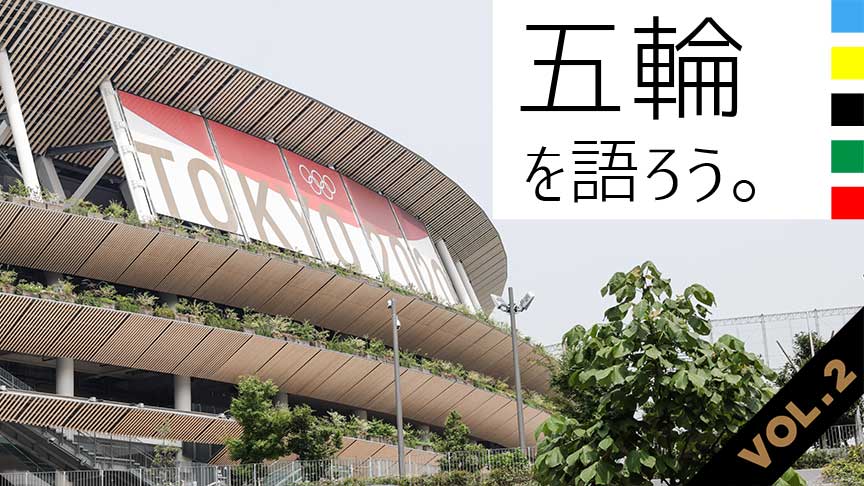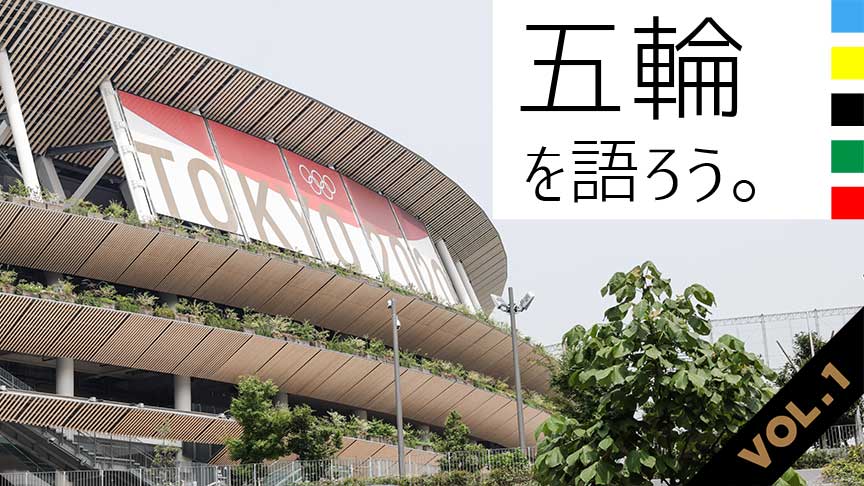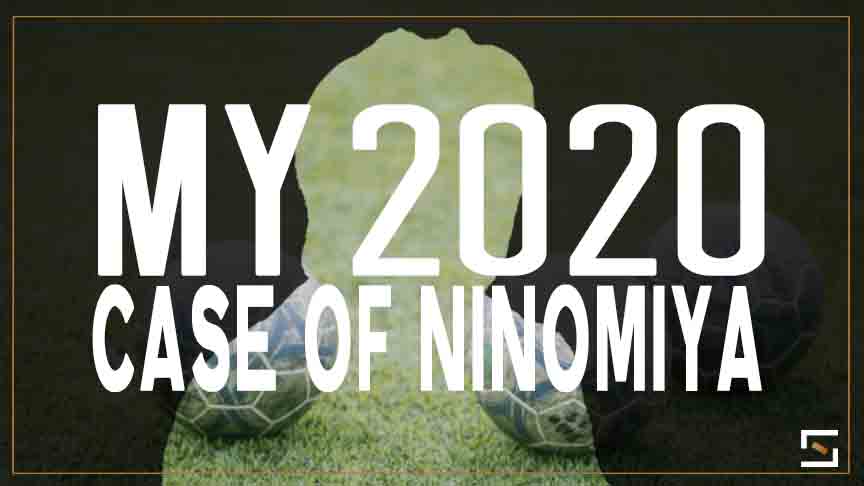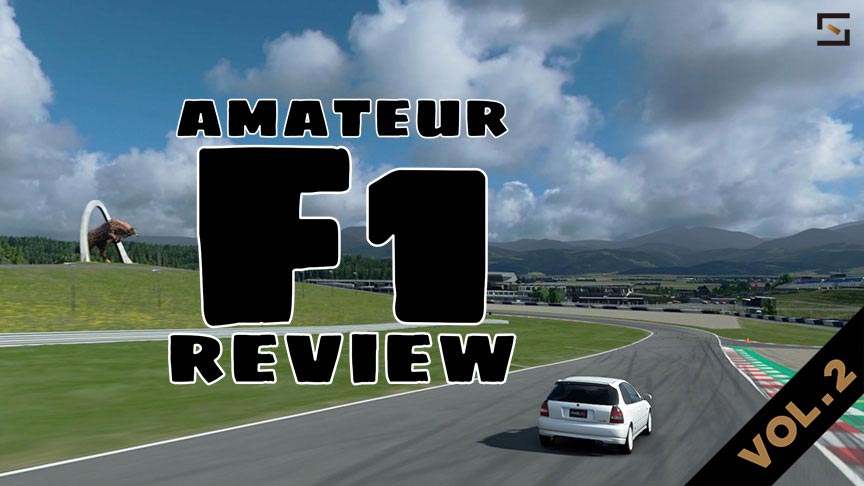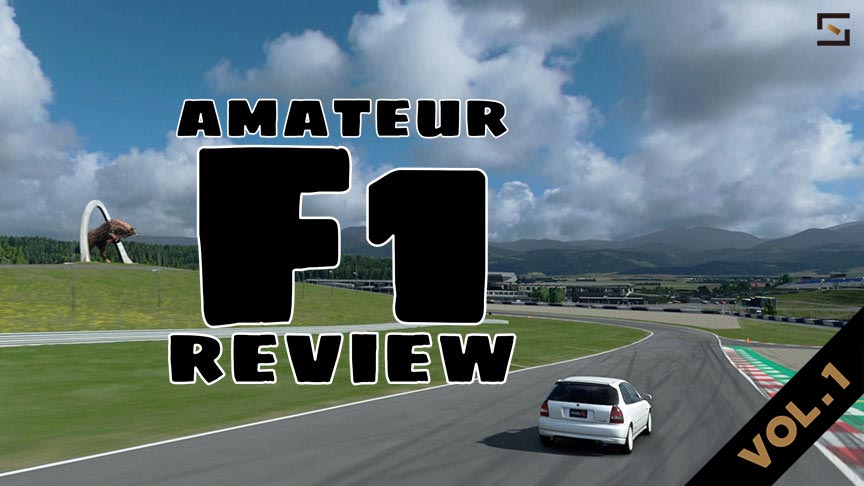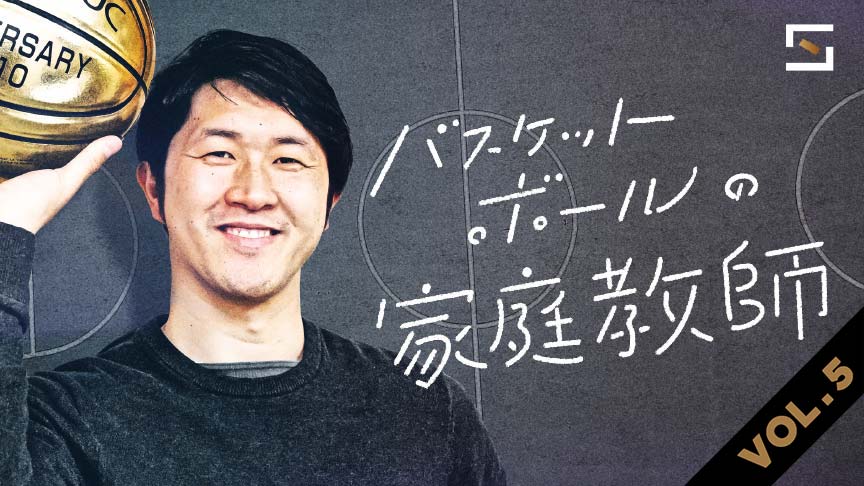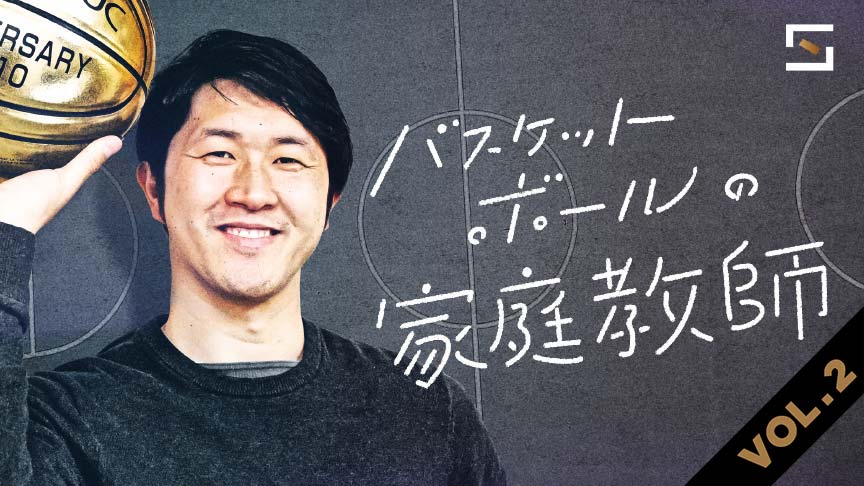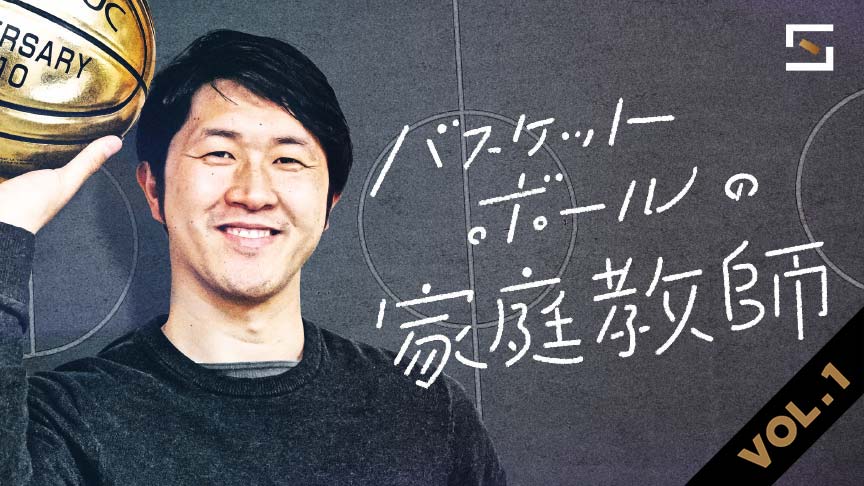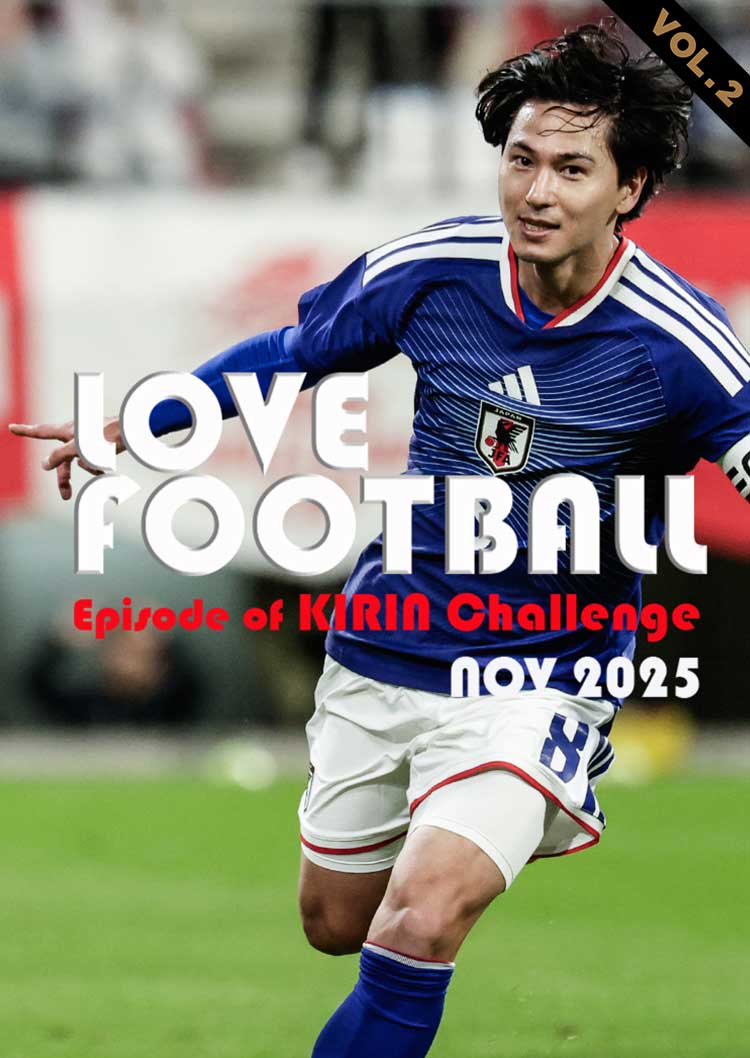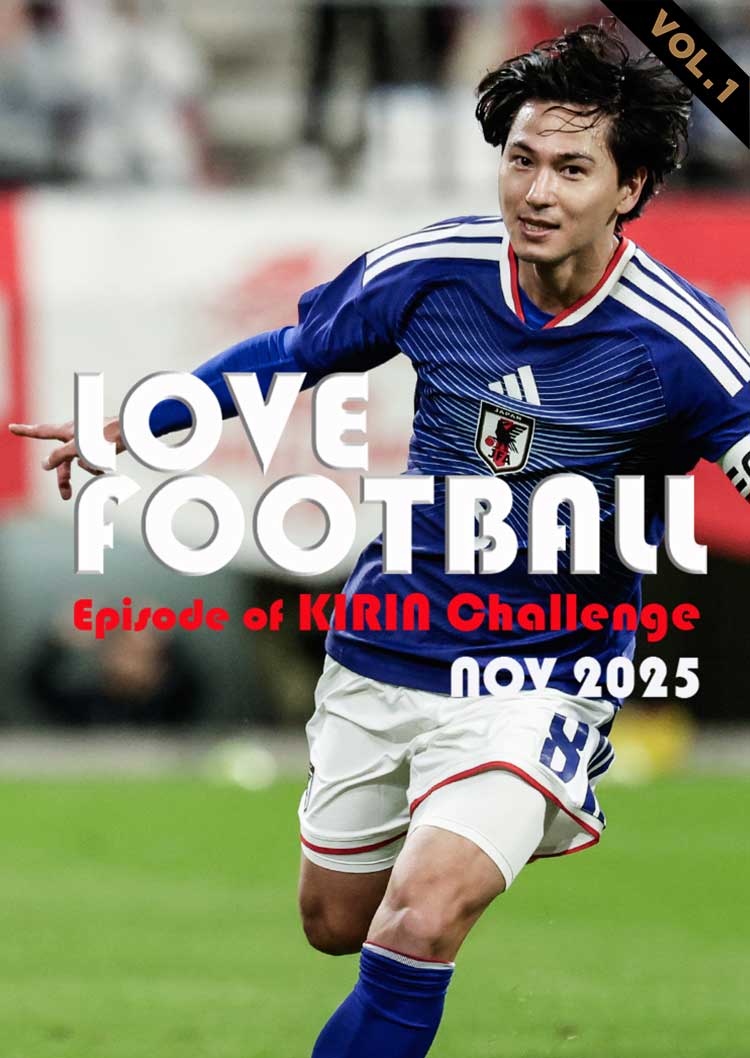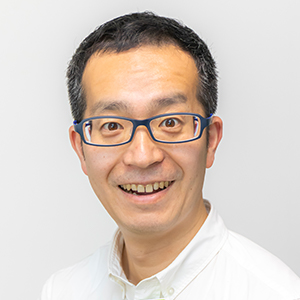初防衛戦から7カ月後、2012年11月3日。
元世界王者トマス・ロハス(メキシコ)はアゴを射抜かれ、真下にストンと落ち、前のめりに倒れた。すべての力を一瞬で吸い取られたように、キャンバスに大きく弾んだ。
これこそがノックアウト。杜の都・仙台に完成して間もないゼビオアリーナ仙台は一瞬にして興奮の坩堝と化した。場内を一周するLEDのライトが王者山中慎介をまばゆく照らしていた。
KOタイムは7回36秒。ワンツーから連打を見舞い、最後は渾身の左ストレートを突き刺した。崩れ落ちた挑戦者は微動だにしない。その異様な光景を目にしてもレフェリーはカウントさえ始めようとさえしていた。裁く者に判断を誤らせるほどのインパクト。カウントなど無用だと分かっていた王者はレフェリーが両手を交差する前に、早々とコーナーのロープに飛び乗っていた。
「最後はフックぽく見えますけど、あれもストレート。近い距離でも(拳を)返して人差し指の付け根で当てる意識があったと思うし、そこで当てれば余計に効きますから。フィニッシュはいつもそうなんですけど、スコーンと抜けるような感じでした」

ロハス戦に向けた過程には知られざる試練もあった。ダルチニャンとの一戦で自信をまとえた一方で、勝利の代償もあったからだ。
ダルチニャンもロハスも同じサウスポーながらタイプはまるで違う。前者は166㎝と170㎝の山中より低く、怒れる雄牛の異名を持つだけに距離を殺して前にプレッシャーをかけてくる相手。だがロハスは山中より高い174㎝で技巧派だ。ロハスに合わせた戦い方をしなければならないのに、一度染み付いたダルチニャン対策がなかなか体から抜けなかった。
山中の入門以来、ずっとパートナーを組んでいる大和心トレーナーはこう明かしていた。
「前回、重心を落としていたのはあくまでダルチニャン用。ロハスは逆に身長があるので、その重心の高さではパンチが届かなくなるんです。それを戻そうとしても、これが難しい。歩くぐらいの高さでボクシングをさせようと、その意識を毎日のように言ってました」
矯正作業に時間が費やされた。焦りも生まれ、精神的なストレスが山中にのしかかっていた。
試合の一カ月前には、妻・沙也乃さんとの間に長男豪祐(ごうすけ)くんが誕生した。トレーニングでのモヤモヤしていた気持ちが晴れたかに思えた。だが一日オフを取って妻の実家がある沖縄に出向いて赤ちゃんと対面を果たしたものの、それでもモチベーションが上がっていかなかった。帰京すると、逆に「うれしい気持ちがいっぱいになって緩みが出ていた」。そこで携帯電話の着信画面にしていた長男の愛くるしい表情の写真を外した。
矯正を完全に終えたのがギリギリの2週間前だったという。もちろん矯正ばかりでなく、距離のある長い左ストレートには磨きをかけ、これまでにはなかった高いガードにも取り組んで習得していった。
心と体がフィットすれば、後は上向いていくだけだ。ボクサーの大きな敵である減量との戦いが、この山中にはない。10㎏前後の調整を強いられるボクサーが多いなか、彼は毎度5㎏ほどの調整で済んでしまう。
試合当日の朝、山中はホテルのジムにいた。
体力を温存する意味であまり体を動かさないのが常識。だが彼は大和トレーナーを誘って、トレッドミルを使って走っていた。
「20分ちょい走りましたかね。ホテルから見える景色がきれいで、気持ちも自然と上がっていったんですよ。それからシャドー(ボクシング)やってみっちり動いて。キレキレすぎて、ちょっと怖かったんですけどね(笑)」
心身ともに最高の状態をつくったという自負が山中にはあった。家族の存在も大きなモチベーションになっていた、リングに向かう前「楽しんでいこう」と言葉をかける大和に、笑みを返した。

真新しい会場のリングに足を踏み入れるといつものように冷静な彼がいた。
ゴングが鳴った。と同時にセコンドにいた大和の目が輝いた。
「対峙したロハスが、山中に圧力を感じたのか下がったんです。これはペースを握れるなと確信を持ったし、山中にも〝相手が下がるパターンだよ〟と伝えました。でも相手のパンチの軌道を確認するまでは打ち込まないようにも決めていました」
上体の柔らかい相手にはボディーから崩す。その鉄則を肝に銘じるように詰めながら、右ジャブ、左ボディーを狙っていった。その一方でガードの意識を高め、荒く振ってくる左右のフックに対する警戒心を緩めなかった。集中したいい立ち上がりだった。2回も冷静に、まずは右を狙い続けた。
山中自身も左が警戒されていることは十分に感じていた。だが、それ以上に自分のフットワークに、ロハスが戸惑っていると見ていた。
「ロハスが手を出せんかったのは、自分に足があるからやと思います。一発打ったら、何かしら動いてパンチをまとめなくさせようと思ってましたから。ガードを高くしていたので、これぐらいならもらっても大丈夫やなとも感じましたね。自分で〝俺、ここまで冷静でいいんか〟って思うぐらい冷静でした。ただね、距離がまだ遠かった。
右フックは下から斜めからいくつかの軌道を練習していて、これが当たったことも相手の手数が減った要因なんかなと思います。ロハスからしてみたら、左だけ警戒しておけばいいということではなくなりましたから」
右はあくまで左への布石に過ぎない。右のジャブ、フックがロハスを困惑させ、左への警戒心を緩めさせていった。
そして6回。浅い感触ながらもついに左ストレートを当てて、体を折らせた。「あんまり打たれ強くないな」と確信を持つことができた。外堀を埋めて徐々に追い込んでから仕留める。ロハスの下半身は明らかに粘りが効かなくなっていた。怖ろしいほど冷静で、怖ろしいほど冷徹なシナリオはここで最終段階に入った。
6回を終わった後のインターバルだった。大和トレーナーからは「豪佑が見てんだぞ!行け!」との声が跳んだ。心にスイッチが入るとともに、不思議な心地にも包まれていた。
「6回は初めてパンチをまとめて、この試合で唯一息が上がってもおかしくないラウンドでした。でも全然息は上がらんし、逆に気持ちいい疲れやったんです。これは調子ええなって思いましたね。凄くいい気分のままであの7回を迎えられた」
7回、最後の連打に要したのはわずか2秒。まず右ジャブを見せてから、左ストレートの強打を浴びせる。続く右アッパーはあくまで軽く、左を打ち抜くために顔を射程距離に入れるためのもの。そして距離が詰まっていたためバックステップで瞬時にポジションを後方にずらす。右ロングフックにアッパーを合わせて頭を打ち抜きたい位置まで運び、最後に左ストレートで打ち抜いたという瞬時の流れだ。
しかしこの一連の動作を本人に尋ねると「一番最初のワンツーは狙ってましたけど、あとは無意識だった」と打ち明ける。
「あそこでステップして距離つくったのを後から映像で見て〝わっ、俺、素晴らしいな〟と思いましたもん(笑)。そこは無意識だったけど、自分の感覚をうまく出せたんかなとは思います」
試合の後、山中はダメージひとつない表情でメディアの前に現れた。
自分の左、どう思います?
集まったメディアから飛んだ率直な質問に、彼はいたずらっぽく笑いながらこう答えている。
「やっぱ凄いんじゃないですかね」――。
2023年3月再公開